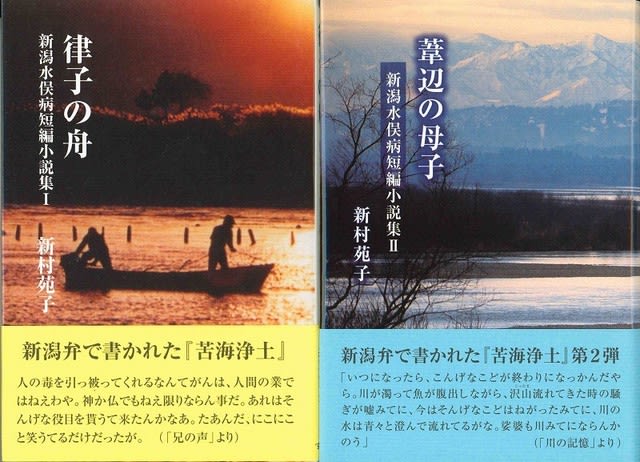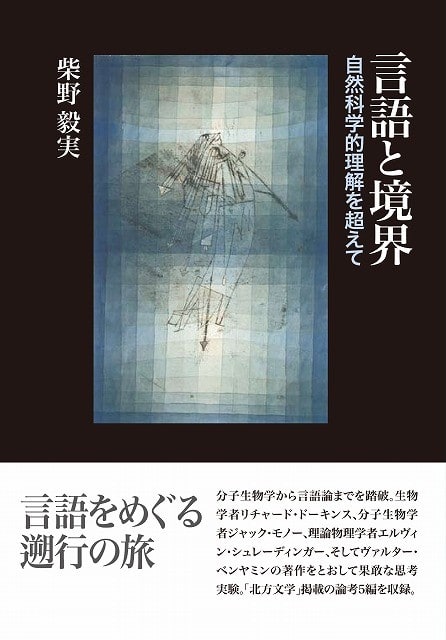
玄文社主人としてこのほど、『言語と境界~自然科学的理解を超えて』を出版しました。本来であれば昨年のうちに発刊の予定だったのですが、腸閉塞による長期入院と自宅療養のため果たせませんでした。今年に入って体調も戻り、準備を進めてきましたが、ようやく出版の運びとなりました。
今度の本は「北方文学」64号から71号まで、4年半にわたって書き継いできた論考をまとめたもので、一貫して言語をテーマに追究した内容になっています。しかし言語論から直接入るのではなく、自然科学とりわけ分子生物学の議論を導入部として、リチャード・ドーキンス、ジャック・モノー、エルヴィン・シュレーディンガー等を論じています。
シュレーディンガーの議論を導きの糸として、文学と言語というものの本質的な関わりについて思索をめぐらし、最後はヴァルター・ベンヤミンの言語論を結語として締めくくるという構成になっています。期せずして時代を遡ることになっていますが、それは言語や人間についての自然科学的理解の限界を指摘したかったからで、こんな書き方をした言語論は今までなかっただろうと思っています。
読みやすい本では決してありませんが、時間をかけて読んでいただければ、人間の言語とは何か、言語は世界の中でどのように機能しているのかについて、私なりに考えたことについて理解していただけるものと信じています。
本書の中核をなすテーマは、シュレーディンガーの次のような文章に負っています。この一文との出会いが決定的であったように思います。カバーにもその文章を使っています。
「つまり意識が複数形で体験されずに、単数形で経験されるという経験的事実によって、この教理は裏付けられているということなのであります。私たちのうちの誰一人として、一つ以上の意識を経験したことはないのですし、これまで世界のどこにもそのような状況証拠の跡すら見つかってはおりません。」
「自然科学的理解を超えて」というサブタイトルにしましたが、私は闇雲に自然科学を否定して、文学的価値観を称揚するものではありません。かつての「近代の超克」のような議論をするつもりはないのです。自然科学の論理を認めた上で、言語に深く関わる文学の原理にアプローチしたつもりです。導入部として自然科学者の議論に沿いながら考えていったことは、結果的によかったのではないかと思っています。
よろしかったら、言語や文学、哲学について興味をお持ちの方々に読んでいただきたいと思っています。お問い合わせは下記のメールアドレスへ。四六判、上製本、272頁、定価(本体3,000円+税)です。