寺尾隆吉が次に取り上げるのは、フアン・ルルフォの『ペドロ・パラモ』である。『ペドロ・パラモ』はメキシコ革命の混乱を「生者と死者が混交し、現実と過去が交錯する」幻想的な物語として描いた作品である。寺尾は〝『ペドロ・パラモ』と死の共同体〟ということに触れて、「魔術的リアリズムの特質は、非理性的視点が個人レベルを越えて、一つの共同体を作り出すところにある」と書いている。
『ペドロ・パラモ』における非理性的視点とは、まさしく墓の下で眠る死者の視点そのものであり、それが個人レベルを越えて、死の共同体を作り出すのだと寺尾は言いたいのだろう。
寺尾の言う「魔術的リアリズム」は定義が多すぎて、適用範囲がむやみと広がってしまう傾向があるが、たとえば「小説の虚構性を前提に、架空の物語に説得力を与えるためにリアリズムを用いる」というような定義ならば受け入れることができる。
この定義は幻想文学の虚構とリアリズム(表象性)をめぐる定義にも近づいていて、『ペドロ・パラモ』はまごうことなき幻想文学の傑作でもあるから、それを適用できるし、さらにはガルシア=マルケスの『百年の孤独』にも適用できる。
しかし、『ペドロ・パラモ』もまた『夜のみだらな鳥』とどのような共通性を持つというのだろう。『ペドロ・パラモ』には『この世の王国』に見られるような、土俗的信仰に対する盲目的な讃美もなければ、楽観的な政治主義もない。しかし、『ペドロ・パラモ』がメキシコの現実と歴史とを描き出していることは紛れもない事実であり、ドノソの『夜のみだらな鳥』にそうしたものを見ることはとてもできない。
前に言ったように『夜のみだらな鳥』は現実や歴史からの逸脱を示しているのであって、参画を示しているのではない。『ペドロ・パラモ』が幻想文学的手法をもって、メキシコの現実や歴史を描いたのだとすれば、それこそ「魔術的リアリズム」と呼ばれるべき方法であって、ほかの定義など必要ないのではないか。
ガルシア=マルケスの『百年の孤独』もまた、幻想文学的手法をもってコロンビアの現実と歴史を、ひいてはラテンアメリカ全体の現実と歴史を描いたものだと言えるだろう。そこに〝語り〟の問題が、ルルフォの場合もガルシア=マルケスの場合も絡んでくることになり、それが魔術的リアリズムにとって重要な要素となることは間違いないが、その〝語り〟とドノソの『夜のみだらな鳥』における〝語り〟が同質のものだとは、私は思わない。
寺尾隆吉は『百年の孤独』について、魔術的リアリズムと関連させて次のように言う。
「『百年の孤独』の最大の特徴は、共同体の建設と「歪曲」された視点の獲得が、物語自体の動力のなかで、新たな登場人物の絶え間ない参加とともに実現されてくる点にある。」
この文章で「共同体の建設」というものと「「歪曲」された視点の獲得」というのが、寺尾の言う「魔術的リアリズムの二本柱ということになるのだが、いかにも苦しげな定義である。もう少し分かりやすい文章を引けば、
「ルルフォとまったく違った仕方ではあるが、ガルシア・マルケスも、超自然的(とされる)事象の発生を可能にする独自の視点を、物語の進行と共に無理なく完成させることに成功した。これによって、架空の世界であることを意識させぬまま、マコンドの共同体全体を読者に受け入れさせることができるのである。」
いいだろう。これで魔術的リアリズムをめぐって、フアン・ルルフォとガルシア=マルケスを結びつけることができる。しかし、『百年の孤独』と『夜のみだらな鳥』の間に、どのような共通項があるというのだろう。
『夜のみだらな鳥』は最初のアスコイティア一族の物語の部分を除いて、超自然的事象を扱うことはないし、それを読者に〝あり得ること〟と説得させることもない。ましてやコマラやマコンドのような架空の共同体(それはそこに住む住人の時間的、空間的帰属意識の共同性を前提とする)が、『夜のみだらな鳥』のどこにあるというのだろう。










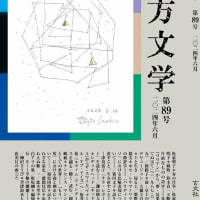
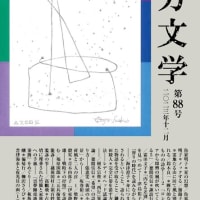

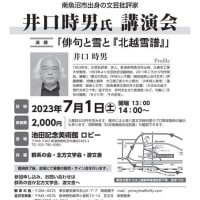

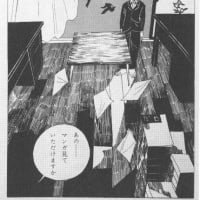
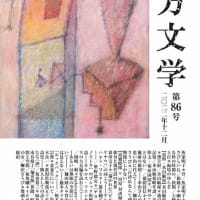
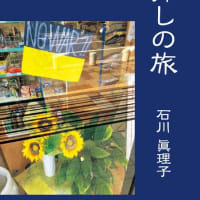
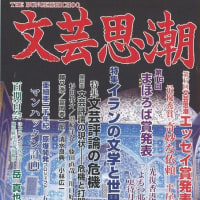
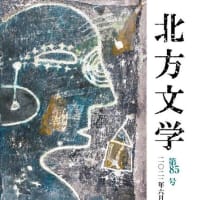

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます