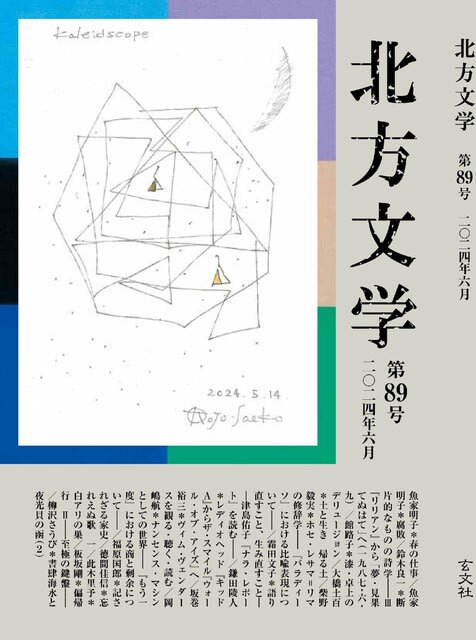「北方文学」第91号を発行しましたので、紹介させていただきます。今号から遠藤真理さんが同人に参加し、極めて特異な力作を発表しています。強力な同人になると思います。同人雑誌の高齢化が言われ、「北方文学」も例外ではありませんが、全国の同人誌の平均年齢が70代、80代であるのに対して、「北方文学」同人には40代、50代、60代に主力となる同人がいて、平均年齢を下げると同時に、雑誌の若さを保持しています。では91号を紹介していきます。
巻頭は鈴木良一の「断片的なものの詩学――Ⅴ」「「詩は身体の骨格」を巡って」です。鈴木のこの連作も5回目となり、かなりこなれてきたような気がします。「詩は身体の骨格」というのは吉本隆明の言葉ですが、この言葉を巡って詩は断片的に生起と消滅を繰り返していきます。基本的には鈴木が生まれ育った新潟市本馬越の現在と過去がモチーフとなって、ノスタルジーが断片の生起を支えています。形式の意図的な破綻を統御しているのも、それなのかもしれません。
次いで館路子の「雪の川縁に火を置く」。雪と白鷺のイメージの中に詩人の過去と野辺の草の名が召喚されていきます。イメージの美しい作品で、この作品もまたノスタルジーに貫かれているのでしょうか。チガヤ、ギシギシ、カワラヨモギ、カラスノエンドウ、ホトケノザなどの植物名がここでは過去の時制を持っています。名詞は基本的に過去形に置かれています。
大橋土百の俳句「いのち薄氷」が続きます。いつものように春夏秋冬の中に生起する情感と思念が歌われていきます。自然は人事のメタファーであったり、歴史への眼差しであったり、変幻自在といったところです。
新しい同人の遠藤真理の「ヒエラルキア・クロイツ」をどういったジャンルに位置付けるかはとても難しい。ただ形式的には西欧的な長詩か。編集後記を参照することで理解の糸口はつかめるかもしれないが、極めて難解な作品です。内容的には天使の十の階層についてのもので、サラフィームームからケルビーム、……自由の天使までの役割が記述されている。西欧の神秘主義を基調とした作品と言えます。
批評はまず、霜田文子の「霊魂へのふるまいについて――ハン・ガン『別れを告げない』―― 」です。昨年ノーベル文学賞を受賞した韓国の作家、ハン・ガンの『別れを告げない』について論じたものです。この作品は1948年に韓国の最終等で起きた住民虐殺事件(四・三事件)を背景にしています。この苛酷な事件へのこだわりを抱えた二人の女性の生が、ごく個人的な痛みとして捉えられていますが、歴史と個人との深い関係の形が大きな強度を持って描かれています。〝霊魂へのふるまい〟というのは、生と死をめぐる魂と肉体についてのプラトンの言葉から来ています。
鎌田陵人もまた、ハン・ガンを中心とした韓国文学について論じた「吊り橋の上で――韓国文学雑感――」を書いています。鎌田もまた歴史に関わる〝痛み〟に触れています。韓国文学理解には、朝鮮近代の苛酷な歴史とそれがもたらした〝痛み〟についての理解が不可欠ということです。また鎌田は斎藤真理子の翻訳に対する姿勢についても論じています。
次は徳間佳信の「忘れ得ぬ歌(3)」。音楽エッセイとして始められたこの連載は、3回目にして本格的な文化論、社会論、政治論としての輪郭を固めつつあります。今回は舟木一夫の「初恋」から始まり、昭和30年代の青春歌謡についての議論が続きます。話はいつしか明治時代からの日本人の恋愛観やセクシュアリティの問題に移っていって、いわゆる「ロマンティックラブ」という概念が、ヨーロッパ・キリスト教の原罪意識を含んだセクシュアリティに至ることなく、マンネリに終始したという結論を導き出しています。
柴野毅実は今年4月に亡くなったペルーのノーベル賞作家、マリオ・バルガス=リョサへの追悼文を書いています。題して「独裁への抵抗者を悼む」。リョサはサルトルの影響を受けて左翼運動に走り、キューバ革命政府の独裁化に直面して転向した作家ですが、左右を問わず生涯一貫して独裁者と闘った人でもあります。柴野が過去に書いた「『シンコ・エスキーナス街の罠』を読む」と「『水を得た魚』における独裁との闘い」の2篇を掲載しています。
書評が3本続きます。霜田文子の新関公子『東京美術学校物語』についての書評の他に、同人の鈴木良一が今年刊行した『新潟県戦後五十年詩史――隣人としての詩人たち』についての藤澤太郎と柴野毅実の書評があります。
今号の小説は4本あります。最初は小説挑戦2作目の海津澄子による「妙子さんと修道院の話」です。彼女が若い時にフランスに渡って修道女としての経験を積んだ体験を踏まえた作品で、修道院の神父と彼に盲目的に従う妙子さんという日本人への告発を含んだ問題作です。小説第2作として処女作より格段に上手くなっていますし、めったに体験できないヨーロッパの修道院の実態を描いて、貴重な作品となっています。
2番目は板坂剛の「偏帰行」連作の最終回「偏帰行 終章」。主人公は転生を繰り返していくのですが、最終章では流産で一度転生に失敗し、霊界で様々なことが明らかにされていきます。「偏帰行」最終章で、前3作とのつながりが分かってきます。それにしても、意識だけの存在となった男を主人公にするなどという禁じ手を、よく使ったなという感じはします。
魚家明子の「猫と口笛」は原稿量の関係で、上下に分けての掲載となります。主人公の主婦が所属する読書会のメンバーの家の火事のために、頼まれて廃校舎に棲む野良猫に餌を与えに行くというストーリーです。後半がないので十分な把握ができませんが、廃校舎で出会う男に絡んで何かドラマが展開していくのでしょうか。
最後は柳沢さうびの「書肆海水と夜光貝の函」の4回目、最終回です。〈2〉と〈3〉では割とストーリーの展開がゆっくりしていましたが、最後は雪崩を打つかのように進行していきます。最初に提示されていてすでに忘れてしまっているような伏線も回収されていき、謎のいくつかも解明されていくことになります。結果、恐ろしいほどのスピード感と圧倒的な密度が実現され、大長編を読み終えたような疲労感を感じてしまうほどです。この一地方都市の現代史と、そこに生きる個性あふれる登場人物たちのドラマは、やはり大長編の長尺を必要としているようです。柳沢の文章はすでに文豪の風格を漂わせています。
目次
鈴木良一 断片的なものの詩学――Ⅴ「「詩は身体の骨格」を巡って」
館 路子 雪の川縁に火を置く
大橋土百 いのち薄氷
遠藤真理 ヒエラルキア・クロイツ――アンゲロイ タンツェン~天使は舞う~
霜田文子 霊魂へのふるまいについて――ハン・ガン『別れを告げない』――
鎌田陵人 吊り橋の上で――韓国文学雑感??
徳間佳信 忘れえぬ歌 (三)
柴野毅実 追悼 マリオ・バルガス=リョサ 独裁への抵抗者を悼む/
『シンコ・エスキーナス街の罠』を読む/『水を得た魚』における独裁との闘い
霜田文子 国際と国粋のせめぎ合いの中で――新関公子著『東京美術学校物語』――藤澤太郎 鈴木良一著『新潟県戦後五十年詩史――隣人としての詩人たち』を読む
柴野毅実 明かしえぬ共同体の隣人たち――『新潟県戦後五十年詩史』の世界――
海津澄子 妙子さんと修道院の話
板坂 剛 偏帰行 終章
魚家明子 口笛と猫(上)
柳沢さうび 書肆海水と夜光貝の函(4)
玄文社の本は地方小出版流通センターを通して、全国の書店から注文できます。