まだ今年は始まったばかりで昨日が観劇初めだったけれど、すでに今年一番良かった舞台になるんじゃないかと思う。
森ノ宮ピロティホールで『レミング』を見た。演出は維新派の松本雄吉さんで、来月同演出家の次の作品に出演するけれど、そういうことを差し引いた感想として、作品に感動するところがあった。
『レミング』の初演を見ていないし、他の演出家による上演も見たことがない。戯曲も読んだことがなく、寺山修司にはげしく惹かれたこともない。内容に関しての予備知識はほとんどない状態で見た。
ある日コック見習いの住む下宿の部屋の壁が突然なくなり、隣人である夫婦、病気の夫と看病する妻の部屋との仕切りがなくなる。大家に修理を依頼してもそんな下宿はどこにもないと言われ、壁のなくなった部屋には現実なのか誰かの空想なのか夢なのか判別のつかない人々が次々とやってくるようになる。都市生活者の往来、隣人の夫婦は病気の夫を看病しているように見えて実は妻の方が病気であったかも知れない、医者を演じているかも知れない患者、患者を演じているかも知れない医者、何十年も同じ映画のシーンを撮り続ける大女優、だったかも知れない女、女優を撮影する監督の役をしているだけなのかも知れない映画監督、カメラを構えて撮影するふりをしているだけなのかも知れない撮影班、往来する都市生活者たちは撮影現場のエキストラかも知れない、さらにそこで撮影しているそれらすべてもフィルムのなかの出来事でしかないのかも知れない、舞台上で起こっているすべては、コック見習いの住む下宿の畳をめくった床下に住むその母の幻想だったかも知れない、コック見習いも精神を煩っているだけなのかも知れない、ほんとうは床下に母などいないのかも知れない。
どの登場人物のありように疑いが掛かっている。それですべての登場人物が誰でもない人に見えてくるというか、最後に残る人物の印象というのが舞台上にいる「誰か」ではなく現実には「表舞台には上がってくることのない人たち」のことだった。社会的な視点から弱者、病者、不適合者と見なされる、言わば社会の辺境にある者の占拠、叛乱のようで、演劇とはそういう価値転倒、現実にははみ出してしまうもの、いかがわしいものを宿す場であるべきと私は思っているので、そういったところに掴まれた。大きな劇場にほぼ満席の観客、贅沢な舞台装置や照明、衣装、キャスティングで主演を立ててわかりやすいドラマを巧みにやってのけるのでなく、上演が終始演劇に対しての批評としてあるように思われた。さらに「演じる」ということに付された疑問はもっと広範囲の、つまり現実を生きる振舞いすべてに対する投げ掛けとしても受け取れる。演じることそれ自体が台詞を発した瞬間に作品に批評されるかのような、それでいてそれを照り返す強い形式を持った演技、演じるということが要求され、それを記号的に機能させることができるキャスティングになっていた。
歌劇と言っていいくらい次々にシーンと音楽と踊りが変わり、場面転換の流れに一切隙がない。そのなかで中盤、奇妙な間のあるシーンがあった。往来もいなくなりコック見習いがひとりで舞台の上手から下手を数回行き来する。靴音がマイクで拾われて聞こえる以外に音は無く、舞台上は極力シンプルな状態になっている。それがけっこう長いので一瞬舞台の機構が止まってしまったのかと思うようなインターバル、空き地のような時間があらわれ、それがとても良かった。
そこからはまた息を吹き返したかのようなテンポの芝居が展開され、ラストシーンに差し掛かると銀色の紙吹雪が舞う。過剰な程舞い続け、この作品の主題になっているステップを全員でしつこいくらいに踏み続ける。終わらない。ザッ ザザッ ザッザッザというリズム。なかなか終わらない。足で踏みながら途中屈んで同じリズムで床をノックするように叩いた。それが今自分たちの立っている場所を確かめているようでもあり、ここはどこなのか、床のずっと奥の奥、裏側のさらに突き抜けた先、足場のない世界の果てを尋ねるノックのようでもあった。プロセニアムの枠の中が着地点を見失ってちょっと狂ってしまったんじゃないか、その狂いに劇場自体が巻き込まれているかのような感覚に陥ることはちょっと今までにない醍醐味だった。














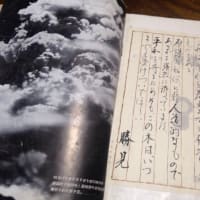
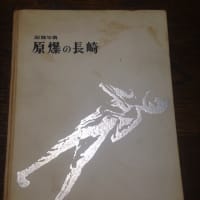




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます