生きていると
齢を重ねていくと
思い出やら荷物やら増えて
その重量でなんとなく物腰も佇まいも暮らしぶりも落ち着くところに落ち着いていつの間にか
そんな顔になる
アイホールのワークショップで70~90代の人たちを見ているとそんなことを思う。
私の生きた時間の約3倍の日々を渡ってきた人々。
病気などの体調の変化以外に体に意識的になるということのなかった人たちが、買い物や通院の為にどこかへ向かって「歩く」のでなく、「ただ歩く」ということを試みている。
足の裏を丁寧に地面に置いていくような、速度を落とした歩行。
本来は背筋を出来るだけまっすぐにして、余計な強張り、無意識の体のクセを意識化し出来るだけニュートラルな姿勢の歩きを目指すが、今回のワークショップ参加者の方々には年月が既に形成してしまった体というものがある。
首や肩の力を抜く事、足の裏の使い方などは或る程度指摘できるのだが、特に背筋の湾曲などはもはやその人の姿となっている。
そういうワークをしながら集中しているとき以外はほとんど一時も止まらず世間話しをして止めるまで止まらない人たちが、黙ってなかなか思い通りに運べない一歩と格闘している。
普段喋っているときは誰々さんというその人だが、ただ歩いている姿をみていると、「老い」というものを傍観しているように思えてくる。
例えば父親に久しぶりに会うと、お父さん歳とったなあと思う。
しかしそのときは「老い」という現象を傍観するというより「老いていく親」を見る私の個人的な感傷の気分が含まれる。
そして私も日々老いている身なのだが、肌の保水力低下のなど加齢に伴う変化は感じつつ、しかしそれを「老い」というふうには捉えていないし、まだ先の事という曖昧な現象としての実感しか今のところない。
ただ「老い」を見るということ。
老いた体を見る。
衰えるという言葉がある。
逆の言葉は栄える。
先日テレビで見た、ローザンヌ国際バレエコンクールの出場者の体。
訓練され鍛え上げられた体はあるルールの中で動きを制限し、それを意識的に完璧にコントロールし、その姿は超人的で価値あるものに見え、栄えているように見える。
老いた体と衰えという言葉が結びつくのは身体機能の低下による。
まっすぐ立たない背骨、思うように稼働しない関節部。
動きに制限が出てくる。
そうなるように鍛えた訳でもなく、意識的にコントロールしているのでもなく、そうなった体。
動きに制限があるという共通点はあるが、意識的なコントロールの有無の差。
コントロールできない「老い」
意識的にコントロールできないという事は、自分ではどうしようもない力が働きかけているという事で、いくら抗おうとその力から逃れられない。
ローザンヌに出ていた10代のダンサー達もいつか老いる。
誰にでも平等に働きかける「老い」は特別なことではない。
それに連れての体の変化は「今まで出来ていた事が出来なくなる」ことなので、それは実感として可能から不可能に、つまり衰えとして捉えられてしまう。
目に見える「老い」た体。
「老い」を受け止めた体で歩いている姿。
そこからは単なる衰えいう形容ではない佇まいが見て取れる。
それは選別、排除によって作り上げられたものではなく、寛大さ、受容、によってある体であると思われる。
生まれたときから孕んでいる「老い」が時によって人を押し広げていくような。
そうやって私たちを押し広げついにはこの体にさえ収まらなくなる。
絶景のような広大さ。
そんな広がりを人の中に見る事が出来るだろうか。
齢を重ねていくと
思い出やら荷物やら増えて
その重量でなんとなく物腰も佇まいも暮らしぶりも落ち着くところに落ち着いていつの間にか
そんな顔になる
アイホールのワークショップで70~90代の人たちを見ているとそんなことを思う。
私の生きた時間の約3倍の日々を渡ってきた人々。
病気などの体調の変化以外に体に意識的になるということのなかった人たちが、買い物や通院の為にどこかへ向かって「歩く」のでなく、「ただ歩く」ということを試みている。
足の裏を丁寧に地面に置いていくような、速度を落とした歩行。
本来は背筋を出来るだけまっすぐにして、余計な強張り、無意識の体のクセを意識化し出来るだけニュートラルな姿勢の歩きを目指すが、今回のワークショップ参加者の方々には年月が既に形成してしまった体というものがある。
首や肩の力を抜く事、足の裏の使い方などは或る程度指摘できるのだが、特に背筋の湾曲などはもはやその人の姿となっている。
そういうワークをしながら集中しているとき以外はほとんど一時も止まらず世間話しをして止めるまで止まらない人たちが、黙ってなかなか思い通りに運べない一歩と格闘している。
普段喋っているときは誰々さんというその人だが、ただ歩いている姿をみていると、「老い」というものを傍観しているように思えてくる。
例えば父親に久しぶりに会うと、お父さん歳とったなあと思う。
しかしそのときは「老い」という現象を傍観するというより「老いていく親」を見る私の個人的な感傷の気分が含まれる。
そして私も日々老いている身なのだが、肌の保水力低下のなど加齢に伴う変化は感じつつ、しかしそれを「老い」というふうには捉えていないし、まだ先の事という曖昧な現象としての実感しか今のところない。
ただ「老い」を見るということ。
老いた体を見る。
衰えるという言葉がある。
逆の言葉は栄える。
先日テレビで見た、ローザンヌ国際バレエコンクールの出場者の体。
訓練され鍛え上げられた体はあるルールの中で動きを制限し、それを意識的に完璧にコントロールし、その姿は超人的で価値あるものに見え、栄えているように見える。
老いた体と衰えという言葉が結びつくのは身体機能の低下による。
まっすぐ立たない背骨、思うように稼働しない関節部。
動きに制限が出てくる。
そうなるように鍛えた訳でもなく、意識的にコントロールしているのでもなく、そうなった体。
動きに制限があるという共通点はあるが、意識的なコントロールの有無の差。
コントロールできない「老い」
意識的にコントロールできないという事は、自分ではどうしようもない力が働きかけているという事で、いくら抗おうとその力から逃れられない。
ローザンヌに出ていた10代のダンサー達もいつか老いる。
誰にでも平等に働きかける「老い」は特別なことではない。
それに連れての体の変化は「今まで出来ていた事が出来なくなる」ことなので、それは実感として可能から不可能に、つまり衰えとして捉えられてしまう。
目に見える「老い」た体。
「老い」を受け止めた体で歩いている姿。
そこからは単なる衰えいう形容ではない佇まいが見て取れる。
それは選別、排除によって作り上げられたものではなく、寛大さ、受容、によってある体であると思われる。
生まれたときから孕んでいる「老い」が時によって人を押し広げていくような。
そうやって私たちを押し広げついにはこの体にさえ収まらなくなる。
絶景のような広大さ。
そんな広がりを人の中に見る事が出来るだろうか。














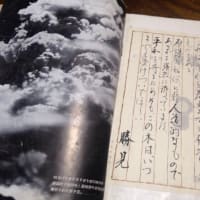
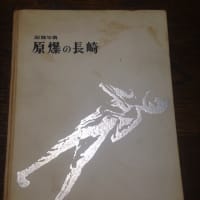




覗くたびに凄いことを書いていて吃驚ですが、いかにも書きながら考えているという感じがわかるのでスリリングです 何も考えず書き始めると、言葉と考えが相談してこういうまさぐるような文章になる。のではないかと 内容にかかわらずエロティックな文触がありますね と思うのは僕だけか。
micaさんは老いを身体的な差異として興味をひかれているところがあるようですが、石内都さんの写真などどう思います?僕は石内さんご本人をおみかけしたことがあるが、逆にすごく若作りしていて、恐ろしかった。
東京は「老い」に抗う街です。老人の身体に「広がり」をみるような余裕ないです。
若作りと関係があるけれど、近年はもう流行語になっているアンチエイジングが僕はすごく気になります。「アンチエイジングされた身体」の逆説的な「老い様」は、micaさんがここに書いているような「広がり」を欠いていて、だからこそ深刻で切実な「老い」を暴露しているように思えたりする。僕は東京に来て、あまりにもそういう身体を持った人々が多いのでおびえまくっています。怖い。だからこそすごく興味があるし、それ関連の雑誌を見たり、調べたりもします。ダイエットの影響で過食症/拒食症になっているとか、ファッションへの傾倒によってタトゥーやピアッシングをしたり、そういうことだらけで、そのひとつひとつはいちいち切実な身体の問題を孕んでいるけれど、本人たちはインタヴューを読んだり話をしてみるととても純粋というか、欲望と行為の間に屈折のない人々だったりし、求道者的な素直さを覗かせることがある たぶん錯覚でしょうが。
micaさんの書いている「広がり」は一種の精神性だと思うけれど、そうした「広がり」は長く社会的な美徳であったはずなのに、どうしたことか などと考え、また ぼくの感覚が古いのもあるのだろうな。改める気はないけど。
筒井康隆が、現実の場面をそのまま描写して小説にできるケースを3つあげていました。裁判、通夜、同窓会です。『同窓会』は確実に「老い」を眺める視線ですよね。
ちょっと思い出したので。
石内都さんの作品、体についた痕跡、シワや傷跡を撮ったものからは、或る時間を生きてきた皮膚、何かしらの出来事による損傷が治癒して傷口が閉じていった、そういうものをたくわえた体の語られない物語があるような奥行きを感じた。
目に見える傷跡として残っていないようなものも皮膚の裏にはあり、体は痕跡そのものなのだと思った。そこには「老い」を見つめることの豊かさがあると思う。しかし対象として「老い」を見つめる事と自らが「老いる」ことの感覚には差があり、どうしても老いる事は豊かであると言い切れないところがある。若作りもしてしまうかも。
加齢とともに体にあらわれる痕跡をどうにかして消し去ろうとするアンチエイジングは確かに「老い」ることを浮き彫りにしていて、ちょうど今日の朝刊に「30日で20歳以上若返り!シワのない美顔になる!」という美容液の折り込みチラシが入っていた。どう見ても実際より老けた加工を施されたbeforeと、30代にしか見えなくなったafterの笑う山本さん63歳。
痕跡の消去。老いの拒絶。不老の夢はいつの時代にもあるようだけど。
どうしても歳をとってしまう、そのことを受け入れて受け入れつつやがては自分を手放さなければならないが、技術の発達も手伝い、老いる事はまるでデジタル操作で修正可能であるような感覚があるように思う。
拒食と過食を繰り返す女性の日記を読んだ事がある。
食べることを嫌悪しつつそれでも食べてしまい、とり込んでしまったものが体に吸収される前にどうにかして消費、排出することに徹する日々。
少しでも体重が増えようものならまとわる肉を、自分を嫌悪し、はやく鎖骨や肋骨に会いたいと書いていた。
一般的な美容目的から逸脱し、危機を招き寄せ、骨に近づこうとするその様子に「危機に立つ身体」「生きたまま突っ立ている死体」など舞踏的身体のイメージを思い起こす。病める舞姫 というのは冗談で。
生きるには食べなければならないということが繋がっていない。これは拒食に限った事ではないけれど。
地域と時代に応じた体の造形はこれまでも為されて来たことだが、アンチエイジングや拒食を例に挙げるとそれがバーチャルな感覚に移行しているように思われる。
民族的な美意識によるもの、儀式的なもの、権力を表すもの、それぞれ風土と生活に根付いたものであったが、なんだか現状この国ではそういうものでなく、体はそれぞれの場所、所有物で意のままに操作可能なものとして扱われている。
個人主義が個々の在り方を作っているのでなく、ほんとうはひとりで居る事が出来ないほどに他者の声が蔓延し、絶えず侵入し、姿のない他者に浸されながら固い体を携えて驚嘆されるほど痩せてみたり若返ってみたり。
どーしたらいいのかわからないということが見える。
これがバーチャルな感覚で表現された切実さ なのか。
それでも80や90、どのように老いていくのだろう。
と、『脱衣』で書いていた「潜在的身体」「裸形」というのは、何も身に付いていない体、を言う言葉を考えていて、どっちもそんなニュアンスで、「私」は様々なものの重ね合わさったものという感じるが、そういうものを全部剥いだ場合「私」は無くなるということになる。いやでも、なんかあるような気がして、あるとして、X代入として言葉をおかないと先に進まなかったというようなあんまり考えてない言葉です。