
どこかで見てふと目にとまった画家や作家の名前を携帯のメール保存欄に残している。よほど気になるとすぐに図書館で画集を探したりネットで調べたりするが、メモしたきりそのままになっているものも結構ある。
もう何をしている人なのかすっかり忘れた名前の羅列をひとつずつ調べるのも面倒になってしまい、消去するにもせっかく蒔かれた出会いの可能性を無にする、と思うと気が進まないので結局そのままになる。
そんなメモの中にヴラマンクという名前があった。
これは比較的新しいもので、仕事で通っていたアトリエに置いてあった「絵画と痕跡」だったか、そんな企画展の図録で見た絵の作者である。
休憩中になんとなく手に取りぱらぱらめくっていると、雪道を描いた一枚の絵に見入ってしまった。
厚く塗られた絵の具が雪道を走った車の跡を描いていた。タイヤの摩擦で地面の土と雪が溶けて混ざってまた冷え固まって出来た痕跡が妙に生々しく魅力的だった。
帰ってから調べてみた。
モーリス・ド・ヴラマンク(Maurice de Vlaminck)1876~1958年
フォーヴィスム(野獣派)に分類される19世紀末~20世紀のフランスの画家。
ヴラマンクは、徹底した自由主義者で、自分の才能以外の何ものも信じず、何ごとにも束縛されたり、服従することを嫌った。絵画についてもあらゆる伝統や教育を拒否し、少年時代に多少絵の手ほどきを受けた程度で、ほとんど独学であった。
1900年、シャトゥー出身の画家、アンドレ・ドランと偶然知り合って意気投合し、共同でアトリエを構える。1901年には、パリで開かれていたゴッホ展を見に行き、そこでドランを通じてアンリ・マティスに紹介されている。
数日後、造形大の図書館で画集を探してみた。4冊程あり、雪道、街角など風景を描いたものが多い。明るい色彩の絵もある。
画集の解説を読んでいて気付いたのだが、以前この日記にも描いたが(自景)、佐伯祐三が初めてパリに渡り、憧れの画家に自分の絵を見せて「アカデミック!」と一蹴されたという、その画家がヴラマンクだったのだ。
相当なショックで佐伯祐三の絵は次の様に変容した。
渡仏前

渡仏後

ヴラマンクの言葉で印象的だったもの
「白い布の上に白い皿、その上に角砂糖と卵を置いて鉛筆で描け、塩と砂糖と雪が描き分けられるようになれ」
絵画に於ける伝統や教育を否定し、ほぼ独学で絵を描いたヴラマンクのこの言葉。
単に技法に頼るのではない方法で、自分の感覚でなんとか分け入って微細に質感を追求する、その姿を想像したとき以前ある踊り手が、テクニックとは物質よ と言っていたのを思いだした。
体が出会った他者や物をどのようにフォルムとして可視化するか。
「如何に」「何を」するか ではなく「何を」「如何に」するか
方法は素材によって引き出されなければならない














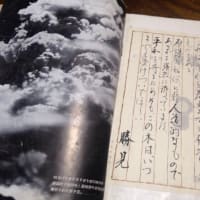
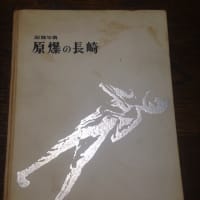




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます