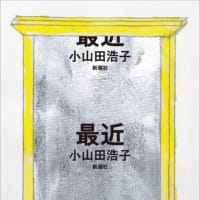国指定史跡 国の重要文化財 世界遺産暫定リスト記載 富岡製糸場
国指定史跡 国の重要文化財 世界遺産暫定リスト記載 富岡製糸場 
官営工場として創業された工場は、やがて民間の企業へと払い下げとなりました。しかし、操業停止までの115年間にわたり休むことなく製糸工場として活躍し続けました。一貫して同一製品の生産がおこなわれたことと、操業停止後も今日までほとんど旧状を変じることなく保存管理されてきたことにより、建造物は創業当初のままで残されています。・・・案内より
 守衛所
守衛所正面にみえるのは
 東繭倉庫
東繭倉庫  明治5年建築
明治5年建築1階は事務所・作業所などとして使用 2階に乾燥させた繭を貯蔵していたそうです。

東繭倉庫アーチ中央のキーストーン





以前来たときは見ることができなかった、東繭倉庫の内部が公開されていました。


 西繭倉庫
西繭倉庫  明治5年建築 外観見学のみ
明治5年建築 外観見学のみ東繭倉庫と同様2回を繭の貯蔵庫として使用していました。




 女工館
女工館  明治6年建築 外観見学のみ
明治6年建築 外観見学のみ日本人女工に器械による糸繰りの技術を教える為に雇われたフランス人女性教師の住居として建設されました。

ベランダの天井には板が格子状に組まれ、当時の日本建築にはない特徴がみられます。これは長崎でもみられました。

 製糸場
製糸場  明治5年建築
明治5年建築創業当初はフランス式の繰糸器300釜が設置され世界最大規模の工場だったそうです。




繭から生糸と繰る作業が行われていた製糸場内部も公開されていました。
建物は トラスト構造 という従来の日本にはない建築工法を用い、柱のない広い空間が保たれているそうです。
さらに採光の為の多くのガラス窓、屋根の上に蒸気抜きの越屋根が取り付けられていました。




 ブリューナ館
ブリューナ館  明治6年建築 外観見学のみ
明治6年建築 外観見学のみ指導者して雇われたフランス人ポール・ブリューナが家族と暮らしていた住居。


床下に当時造られたレンガ造りの地下室が現在も残っています。非公開。これみてみたかったのですが右上の写真のみ。

 検査人館
検査人館  外観見学のみ 明治6年建築
外観見学のみ 明治6年建築生糸や機会の検査を担当したフランス人男性技術者の住居として建設されました。現在は改修され事務所として使用されています。
2階には皇族や政府の役人が訪れた際に使用したとされる 貴賓室 が大理石製のマントルピースを備えた形で、ほぼ当時のまま残されているそうです。非公開。




 煙突
煙突 

ブリューナ館奥の立ち入り禁止区域に建っていた
 寄宿舎
寄宿舎  望遠でパチリ
望遠でパチリ

 休日でしたので入場後、何人か集まるとボランティアガイドの方と一緒にまわり、説明を聞く事が出来ました。質問もわかる範囲で答えてくれますので見学時には是非ご一緒に。
休日でしたので入場後、何人か集まるとボランティアガイドの方と一緒にまわり、説明を聞く事が出来ました。質問もわかる範囲で答えてくれますので見学時には是非ご一緒に。 駐車場から富岡製糸場に向かう道すがら見つけたもの。 洋館もありました。
駐車場から富岡製糸場に向かう道すがら見つけたもの。 洋館もありました。





 以前来たときは小学生になっていた子供達も一緒でした。
以前来たときは小学生になっていた子供達も一緒でした。飽きちゃって砂利を拾って投げ始めたり、追いかけっこしたりとワンパク爆裂していましたので
 こら~っ!と叫んで、とっ捕まえていたので見た気がしなく、もーっ!
こら~っ!と叫んで、とっ捕まえていたので見た気がしなく、もーっ!  と、さっさと見て、とっとと帰って来てしまいました。
と、さっさと見て、とっとと帰って来てしまいました。 今回はゆ~~~っくり見学できました。
今回はゆ~~~っくり見学できました。