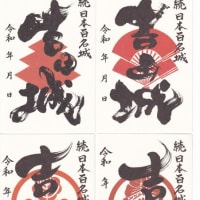お城検索は→こちら
村岡山(むろこやま)城址
天正2年(1574)、平泉寺と対立していた七山家を中心とする一向一揆は、ここ村岡山に一夜で城を築きました。平泉寺はすぐに村岡山を攻めましたが、逆に攻撃を受け焼き討ちされてしまいます。一揆勢が立て籠もり勝利につながった村岡山は、「勝ち山」と名付けられ、今の勝山の地名にも繋がっています。
天正3年(1575)、織田信長が越前の一揆を鎮圧し、勝山地域にはその家臣柴田義宣がやって来ました。義宣は一揆の残党に敗れ討ち死にしますが、その養子勝安が一揆を滅ぼし、本拠地を袋田(今の市役所付近)に移して勝山の町の原型を作りました。
村岡山は、九頭竜川流域や石川県と勝山を結ぶ街道筋を見渡すことができる地にあります。城跡の西側は、一揆勢が立て籠もった城の痕跡を残しています。そして、主郭の櫓台や、主郭を取り巻く大規模な堀、土塁や濠を組み合わせた複雑な出入り口(虎口)は、柴田氏が一揆勢の作った城に大きく手を加えたもので、一向一揆と織田政権との戦いを今に伝えるものであると言えます。村岡町連合壮年会、、、現地説明板より
場所は福井県勝山市村岡寺尾、ザックリ言って「福井県立恐竜博物館」の近く、向かい側の山という感じです。

中部縦貫道「勝山IC」下車すぐに県道260号線を右折。九頭竜川を渡り、「新保交差点」で国道416号線へ右折。滝波川を渡り「郡町交差点」を左折すると、左手に「福井県立恐竜博物館」入り口があります。
注、、、写真は帰路に撮ったもので、正面が恐竜博物館となります。

この交差点を恐竜博物館とは反対の右に曲がり100mほど行くと川を渡った先の右手に「寺尾ふれあい会館」(村岡町寺尾27-14)があります。寺尾ふれあい会館から道沿いに10m程先に「村岡山城現地説明板」や「村岡山登山口」の標識が建っています。

また、ふれあい会館脇の側道からも登山口に通じており、

両方の道は途中で合流して「西国三十三か所」登山道となります。

登山道の登りはキツイですが整備されており、随所に案内標識があるので励まされます。

また、「西国三十三か所」ということで、傍らにはいたるところ石仏が建立されていました。

東に開けた一画に休憩所が設けられ、銀色の玉子みたいなものが見えてきました。これが「福井県立恐竜博物館」です。

しばらくすると右手に深い縦溝が現れました。

「畝状空堀群」です。
登山道は空堀と並行して登って行き、左右に雄大な竪堀を望むことができ、まるで竪堀の堀底を登っているようです。

登りきるといよいよ郭に達します。
上から見下ろした畝状空堀群

ここで当日の行程を縄張り図で示します。
現地説明板より、、、(ブログ管理者加筆)

竪堀沿いの登山道は「郭4」に至り、直進すると「郭1」に進みますが、自分は「郭3」の方へ向かいました。
西側の郭を隔てる空堀にいきなり驚かされます。

「郭4」
南東から北西に直線的に延びる尾根の南東端にあって、侵入した敵を一旦受け止める升方みたいな感じですね。

「虎口」
郭3と郭4を仕切る出入り口。敵の侵入速度を抑制する機能があって、郭4で滞留しそうです。

「郭3」
郭4の北側にあって、上段の郭2とは深い空堀で遮断されています。つまり、敵が郭4から侵入してもこの郭で更に閉じ込められてしまいます。

「空堀2」
上段の郭2と隔てる深い堀

空堀北東端
この先は崖となっており、斜面には竪堀で敵が回り込むのを防御している

空堀南端
尾根を切断して上段の郭1,2への侵入を防御している

「土塁」
上段の郭2側に設けられた土塁で郭3から直登する敵への防御

「郭1」
主郭直下の郭で、最大の面積があります。
下段の郭4とは空堀で仕切られ、上段の主郭を取り囲むように広大な空堀が巡っています。

郭1は南西方向に細長く延びた郭で、主郭から見ると土橋の先にその削平地が見て取れる。現在は休憩施設が設置されています。

郭1の南西側、ちょうど土橋の反対側あたりに「郡口」に至る登山道があります。

「西国三十三か所」ということで、いたるところ石仏が建立されていました。


「郭2」
郭1の北東側にあり、郭1と共に主郭の直下を守っています。

「櫓台」
郭2の北東端にあって、直下を走る街道を監視していた見張り台でしょうね。

櫓台から南西方向、郭2・郭3と連なっている様子がわかります。

「空堀1」
主郭の北東以外の、3面を取り囲む広大な空堀。
北東端、郭2との間にあってその先は崖に落とし込まれている。

郭2から空堀に架かる土橋を渡り主郭へ

同土橋から見た空堀、南西方向
写真右側が主郭切岸、左側が郭1

堀底に降りて進んでみると、南角には「折れ」があります。

同

南西側空堀
写真右側は主郭切岸、左側は郭1南西側

空堀の突当りは土橋となっており、土橋の基礎法面には石積みが見られます。

「土橋」
郭1から空堀に架かる土橋を渡り主郭へ登っていく

主郭上からみた土橋、空堀、郭1

土橋上より空堀南東方向
南隅の折れが分かる

土橋上より空堀北西方向
日当たりが良いせいか藪化しています。その先空堀は、南西から北西へL字型に屈折していますが進むことはできませんでした。

「主郭」
尾根のピークにあって周囲より4~5mの小高い丘のような形状をしている。
その頂上部を削平した郭で北側以外の3面を土塁で囲んでいる。

主郭西側の櫓台

主郭東側の土塁

主郭からの眺望

以上、尾根南東部(東)が柴田氏が改修したと言われている城郭部分です。
その先尾根北西部(西)には、それに先立って七山家を中心とした一向一揆勢が築いた部分が残っています。
郭1の北西端にある小径から西尾根へ降りていきますが、土塁から堀切に降りていく辺りは藪が茂っています。

細長い尾根上のアップダウンの地形を巧みに利用し、隆起したところは削平し、陥没した地形は堀切とし土橋でつないでいる。
郭5から郭8まで、それの連続です。
堀切と土橋

「郭5」

堀切と土橋

「郭6」

堀切と土橋

「郭7」

土橋と竪堀

「郭8」

郭8段郭

郭8段郭最西端

眺望

村岡山、西側からの遠景
恐竜の口の辺りが郭8西端と思われます。

【村岡山城】
《むろこやまじょう》
名称(別名);
所在地;福井県勝山市村岡寺尾
城地種類;山城
標高/比高;256m/150m
築城年代;天正2年(1574年)
廃城年代;天正8年(1580年)
築城者;七山家一向一揆
主な改修者;柴田氏
主な城主;七山家一向一揆、柴田義宣、柴田勝安
文化財区分;なし
主な遺構;曲輪、土塁、堀切(空堀)、畝状竪堀、檜台、虎口、土橋、碑
近年の主な復元等;
地図;
村岡山(むろこやま)城址
天正2年(1574)、平泉寺と対立していた七山家を中心とする一向一揆は、ここ村岡山に一夜で城を築きました。平泉寺はすぐに村岡山を攻めましたが、逆に攻撃を受け焼き討ちされてしまいます。一揆勢が立て籠もり勝利につながった村岡山は、「勝ち山」と名付けられ、今の勝山の地名にも繋がっています。
天正3年(1575)、織田信長が越前の一揆を鎮圧し、勝山地域にはその家臣柴田義宣がやって来ました。義宣は一揆の残党に敗れ討ち死にしますが、その養子勝安が一揆を滅ぼし、本拠地を袋田(今の市役所付近)に移して勝山の町の原型を作りました。
村岡山は、九頭竜川流域や石川県と勝山を結ぶ街道筋を見渡すことができる地にあります。城跡の西側は、一揆勢が立て籠もった城の痕跡を残しています。そして、主郭の櫓台や、主郭を取り巻く大規模な堀、土塁や濠を組み合わせた複雑な出入り口(虎口)は、柴田氏が一揆勢の作った城に大きく手を加えたもので、一向一揆と織田政権との戦いを今に伝えるものであると言えます。村岡町連合壮年会、、、現地説明板より
場所は福井県勝山市村岡寺尾、ザックリ言って「福井県立恐竜博物館」の近く、向かい側の山という感じです。

中部縦貫道「勝山IC」下車すぐに県道260号線を右折。九頭竜川を渡り、「新保交差点」で国道416号線へ右折。滝波川を渡り「郡町交差点」を左折すると、左手に「福井県立恐竜博物館」入り口があります。
注、、、写真は帰路に撮ったもので、正面が恐竜博物館となります。

この交差点を恐竜博物館とは反対の右に曲がり100mほど行くと川を渡った先の右手に「寺尾ふれあい会館」(村岡町寺尾27-14)があります。寺尾ふれあい会館から道沿いに10m程先に「村岡山城現地説明板」や「村岡山登山口」の標識が建っています。

また、ふれあい会館脇の側道からも登山口に通じており、

両方の道は途中で合流して「西国三十三か所」登山道となります。

登山道の登りはキツイですが整備されており、随所に案内標識があるので励まされます。

また、「西国三十三か所」ということで、傍らにはいたるところ石仏が建立されていました。

東に開けた一画に休憩所が設けられ、銀色の玉子みたいなものが見えてきました。これが「福井県立恐竜博物館」です。

しばらくすると右手に深い縦溝が現れました。

「畝状空堀群」です。
登山道は空堀と並行して登って行き、左右に雄大な竪堀を望むことができ、まるで竪堀の堀底を登っているようです。

登りきるといよいよ郭に達します。
上から見下ろした畝状空堀群

ここで当日の行程を縄張り図で示します。
現地説明板より、、、(ブログ管理者加筆)

竪堀沿いの登山道は「郭4」に至り、直進すると「郭1」に進みますが、自分は「郭3」の方へ向かいました。
西側の郭を隔てる空堀にいきなり驚かされます。

「郭4」
南東から北西に直線的に延びる尾根の南東端にあって、侵入した敵を一旦受け止める升方みたいな感じですね。

「虎口」
郭3と郭4を仕切る出入り口。敵の侵入速度を抑制する機能があって、郭4で滞留しそうです。

「郭3」
郭4の北側にあって、上段の郭2とは深い空堀で遮断されています。つまり、敵が郭4から侵入してもこの郭で更に閉じ込められてしまいます。

「空堀2」
上段の郭2と隔てる深い堀

空堀北東端
この先は崖となっており、斜面には竪堀で敵が回り込むのを防御している

空堀南端
尾根を切断して上段の郭1,2への侵入を防御している

「土塁」
上段の郭2側に設けられた土塁で郭3から直登する敵への防御

「郭1」
主郭直下の郭で、最大の面積があります。
下段の郭4とは空堀で仕切られ、上段の主郭を取り囲むように広大な空堀が巡っています。

郭1は南西方向に細長く延びた郭で、主郭から見ると土橋の先にその削平地が見て取れる。現在は休憩施設が設置されています。

郭1の南西側、ちょうど土橋の反対側あたりに「郡口」に至る登山道があります。

「西国三十三か所」ということで、いたるところ石仏が建立されていました。


「郭2」
郭1の北東側にあり、郭1と共に主郭の直下を守っています。

「櫓台」
郭2の北東端にあって、直下を走る街道を監視していた見張り台でしょうね。

櫓台から南西方向、郭2・郭3と連なっている様子がわかります。

「空堀1」
主郭の北東以外の、3面を取り囲む広大な空堀。
北東端、郭2との間にあってその先は崖に落とし込まれている。

郭2から空堀に架かる土橋を渡り主郭へ

同土橋から見た空堀、南西方向
写真右側が主郭切岸、左側が郭1

堀底に降りて進んでみると、南角には「折れ」があります。

同

南西側空堀
写真右側は主郭切岸、左側は郭1南西側

空堀の突当りは土橋となっており、土橋の基礎法面には石積みが見られます。

「土橋」
郭1から空堀に架かる土橋を渡り主郭へ登っていく

主郭上からみた土橋、空堀、郭1

土橋上より空堀南東方向
南隅の折れが分かる

土橋上より空堀北西方向
日当たりが良いせいか藪化しています。その先空堀は、南西から北西へL字型に屈折していますが進むことはできませんでした。

「主郭」
尾根のピークにあって周囲より4~5mの小高い丘のような形状をしている。
その頂上部を削平した郭で北側以外の3面を土塁で囲んでいる。

主郭西側の櫓台

主郭東側の土塁

主郭からの眺望

以上、尾根南東部(東)が柴田氏が改修したと言われている城郭部分です。
その先尾根北西部(西)には、それに先立って七山家を中心とした一向一揆勢が築いた部分が残っています。
郭1の北西端にある小径から西尾根へ降りていきますが、土塁から堀切に降りていく辺りは藪が茂っています。

細長い尾根上のアップダウンの地形を巧みに利用し、隆起したところは削平し、陥没した地形は堀切とし土橋でつないでいる。
郭5から郭8まで、それの連続です。
堀切と土橋

「郭5」

堀切と土橋

「郭6」

堀切と土橋

「郭7」

土橋と竪堀

「郭8」

郭8段郭

郭8段郭最西端

眺望

村岡山、西側からの遠景
恐竜の口の辺りが郭8西端と思われます。

【村岡山城】
《むろこやまじょう》
名称(別名);
所在地;福井県勝山市村岡寺尾
城地種類;山城
標高/比高;256m/150m
築城年代;天正2年(1574年)
廃城年代;天正8年(1580年)
築城者;七山家一向一揆
主な改修者;柴田氏
主な城主;七山家一向一揆、柴田義宣、柴田勝安
文化財区分;なし
主な遺構;曲輪、土塁、堀切(空堀)、畝状竪堀、檜台、虎口、土橋、碑
近年の主な復元等;
地図;