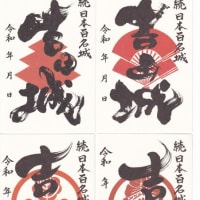お城検索は→こちら
いしかわ城郭カード→こちら
荒山合戦古戦場
【枡形山】
荒山合戦記によると、天正10年(1582)6月2日、本能寺の変で織田信長が自刃したのを機に、石動山衆徒は越後の上杉景勝に支援を求め、畠山(能登国守護)の遺臣である温井備中守景勝と三宅備後守長盛の両氏と共に、6月23日、枡形山に築かれていた荒山砦に籠りました。
これに対して羽柴秀吉は前田利家に石動山攻撃を命じ、利家は三千人の兵を率いて石動山へ向かい、6月25日未明に石動山と枡形山の中間にあたる柴峠に布陣しました。そして、荒山砦の普請に向かう温井・三宅軍を急襲し、これを破った勢いに乗じて砦に攻め入り、ついに荒山砦は陥落したのです(荒山合戦)
この合戦に勝利した利家軍は、翌26日に一気に石動山院に攻め入って、一山に火を放ち、栄華を誇った石動山の堂塔伽藍はことごとく焼き尽くされたのでした。(石動山の合戦)
、、、
現地案内板より
元々は石動山城郭群の一つとして築城されたと考えられ、
織田信長の死を能登奪還の好機と捉えた上杉景勝が石動山と結び、遊佐・温井・三宅氏を荒山城に送り込む。これに驚いた能登領主前田利家は、柴田勝家と佐久間盛政に援軍を依頼し、荒山城は落城。
その後、越中領主となった佐々成政が能越国境の城として使用。成政が天正12年9月、末森城攻めに失敗し敗退。以降は前田方の城郭として使用されるが富山の役で羽柴秀吉に降伏すると、能越国境の緊張状態は解消され、廃城になったと思われる。、、、中世城郭図面集Ⅲ 著者佐伯氏による
場所は富山県氷見市小滝及び、石川県中能登町
富山県氷見市から、石川県中能登町に至る「県道18号線」の「荒山峠」付近で、林道「城石線」へ入るとすぐ右手に「荒山城址」の標識と駐車場が見える。

県道18号荒山峠(氷見側)
祠と記念碑が建っている

県道18号と林道「城石線」分岐

林道「城石線」沿いにある「荒山城址」

道沿いに石碑が建っています

広い駐車場にはトイレや案内看板が整備されています

案内看板脇が登城口となっています

荒山城縄張りと工程 越中中世城郭図面集Ⅲより

駐車場から登ること約5分で城郭に到着。休憩所の東屋が先ず目に飛び込んでくる。

さらにその上には見張り台をイメージした展望台が設置されています。木造のように見えますが、コンクリート製の丸太で組み立てられています。

見張り台があるのは縄張り図の「F郭」
ここから下の北側斜面には「E郭」、「⑦横堀」、東屋が建つ「曲輪」、とひな壇状に並んでいるのがわかります。その先を下ったところが駐車場の方向です。

F郭背後の切岸の付け根部分には浅い溝が彫って有り、

その先は西側谷に突き出た平坦地にまで伸びて大きな横堀となっています。

この「横堀」が、西側に突き出た曲輪と主郭側を分断しています。

西側に突き出た曲輪から、向かい側の主郭方向。
主郭下西側帯曲輪に登る階段付近。

西側に突き出た曲輪からF郭に戻り主郭下帯曲輪の下段にある通路を進み、先ほど見えた「階段」から主郭下西側帯曲輪へと登る。

「主郭下西側帯曲輪」

その先にある「主郭下北側帯曲輪」は一段高くなっています。

主郭下北側帯曲輪から見る「主郭北面」
ここから主郭に登るための「階段」が東側の隅にあり、

「階段」の先はクランクして「虎口」に至る。

標高486.3m、枡形山の頂上にある「主郭削平地」

ここにはベンチや休憩所などの施設は無いが、360度のパノラマが展開し、
北西は能登半島越しの千里浜と日本海まで、

南東は氷見沖から富山湾越しの立山連峰の、両方が楽しめる。

主郭南東隅の虎口

虎口下段の「C郭」は
②竪堀と組み合わせることにより「内枡形」の構造となっているそうです。

「②竪堀」
写真左側に見える斜面にぽっかり空いた窪み

ここから一旦主郭下北帯曲輪まで戻り、その北側隅にある階段を使って「主郭下東面帯曲輪」へ降ります。

更に階段を降りD郭に行きます。

「D郭」は通路のような曲輪だそうですが、これは通路以外の何物でもないと感じましたが、、、。

D郭から東側の谷と下を通る林道

D郭は北から南へと一直線に伸び「横堀」によって北東尾根と分断されている。

ここから北東尾根(石動山方面)と主郭下南面への分岐となる。
まず、主郭下南面に向かい南東側の横堀と南側の横堀を確認したいと思います。
主柿下南面は雑木林に覆われ、急な斜面と段々となった小さな平坦面が組み合わさっています。

「②竪堀」でしょうか?
しかし図面より小規模なのでとても内枡形を構成する重要な施設には思えないので、勘違いかも知れません。

「主郭下南面の横堀」
主郭南隅下の額に掘られた横堀と思われます。

ここから先ほどの南東尾根の分岐に戻ります。
「主郭下南東側横堀」

この横堀はさきほど歩いてきたD郭先の、北東尾根を分断する横堀に繋がっているのではないかと思います。
そしてその横堀の隣、北東尾根側に「二重の堀」が切ってありました。
D郭先端の横堀と並行で、尾根に対しては垂直の位置関係です。

北東尾根を石動山方向に進みますが、今歩いているところはは堀なんでしょうか?
写真左手が尾根の頂点で、左右の谷方向に向かって下り斜面となります。
尾根の頂上は樹木に覆われ、今は歩くことが困難です。従ってこの堀のような人工的な部分を歩いています。

この「通路?」と平行に掘られた「空堀」
尾根付け根の「二重の堀」辺りから尾根最初の「切堀」までの50mにも及ぶ長大なものです。

先ほどの主郭下南面横堀、主郭下南東面横堀、そしてこの尾根南側横堀の三点セット。
徹底的に南側を防御し、特に南東尾根から城郭に入り込む隙を与えない徹底した守りの施設。
「南東尾根最初の堀切」

「南東尾根二番目の堀切」は北側斜面にだけ彫られているが、最初の堀切より大規模です。

その先尾根は石動山に通じる。

ここからは折り返しになります。
D郭を通り、E郭東側の階段に出ます。F郭に立てられた見張り台が見えてます。

E郭下、北尾根の東面に掘られた「空堀」でしょうか?

かなり深い切込みで主郭への侵入を防いでいるように見えます。
現在の登城ルートから見ると離れているので実感がわきませんが、当時この堀によって搦手方向の道が分断されたのかもしれません。

さらに北尾根の西側に掘られた「空堀」でしょうか?
この堀の先は通路になっているようですがクマザサの藪が酷くて進めませんでした。

北東尾根から主郭へは急な崖が立ちはだかり、D郭やC郭を通ってぐるっと回り込むしかありませんが、
北尾根から主郭へは比較的なだらかになっています。
なので北尾根の東西にそれぞれ空堀を備え、さらに主郭下には数段に渡って曲輪を配置して防御を固めたんでしょうね。
主郭への南東側虎口「C郭」や、北側虎口「主郭下北面帯曲輪」はある意味「外枡形」だったのかもしれません。
築城から歴代城主の変遷をみると、「石動山城郭群」→「前田氏」→「佐々氏」→「前田氏」の改修の跡が想像されるようで、コンパクトですが面白い「輪郭式山城??」で、整備が行き届いた展望公園とも言ってよいのではないでしょうか。
荒山峠の祠と記念碑

休憩所と展望台

展望台からの眺望






おまけ画像w
休憩所に置かれた天然木を加工した人のオブジェ
顔と下半身のアレがとってもオチェメで、地元愛に癒されました(^^)/

※2022年6月12日 いしかわ城郭カードリンク、写真追加
【荒山城】
《荒山合戦古戦場》

名称(別名);枡形山城
所在地;富山県氷見市小滝及び、石川県中能登町
城地種類;山城
標高/比高;486.3m/210m
築城年代;16世紀
廃城年代;16世紀末
築城者;天平寺?
主な改修者;
主な城主;菊地氏、天平寺、佐々氏、前田氏
文化財区分;
主な遺構;削平地、切岸、土塁、堀切、竪堀、横堀
近年の主な復元等;物見櫓、東屋
※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ
地図;
いしかわ城郭カード→こちら
荒山合戦古戦場
【枡形山】
荒山合戦記によると、天正10年(1582)6月2日、本能寺の変で織田信長が自刃したのを機に、石動山衆徒は越後の上杉景勝に支援を求め、畠山(能登国守護)の遺臣である温井備中守景勝と三宅備後守長盛の両氏と共に、6月23日、枡形山に築かれていた荒山砦に籠りました。
これに対して羽柴秀吉は前田利家に石動山攻撃を命じ、利家は三千人の兵を率いて石動山へ向かい、6月25日未明に石動山と枡形山の中間にあたる柴峠に布陣しました。そして、荒山砦の普請に向かう温井・三宅軍を急襲し、これを破った勢いに乗じて砦に攻め入り、ついに荒山砦は陥落したのです(荒山合戦)
この合戦に勝利した利家軍は、翌26日に一気に石動山院に攻め入って、一山に火を放ち、栄華を誇った石動山の堂塔伽藍はことごとく焼き尽くされたのでした。(石動山の合戦)
、、、
現地案内板より
元々は石動山城郭群の一つとして築城されたと考えられ、
織田信長の死を能登奪還の好機と捉えた上杉景勝が石動山と結び、遊佐・温井・三宅氏を荒山城に送り込む。これに驚いた能登領主前田利家は、柴田勝家と佐久間盛政に援軍を依頼し、荒山城は落城。
その後、越中領主となった佐々成政が能越国境の城として使用。成政が天正12年9月、末森城攻めに失敗し敗退。以降は前田方の城郭として使用されるが富山の役で羽柴秀吉に降伏すると、能越国境の緊張状態は解消され、廃城になったと思われる。、、、中世城郭図面集Ⅲ 著者佐伯氏による
場所は富山県氷見市小滝及び、石川県中能登町
富山県氷見市から、石川県中能登町に至る「県道18号線」の「荒山峠」付近で、林道「城石線」へ入るとすぐ右手に「荒山城址」の標識と駐車場が見える。

県道18号荒山峠(氷見側)
祠と記念碑が建っている

県道18号と林道「城石線」分岐

林道「城石線」沿いにある「荒山城址」

道沿いに石碑が建っています

広い駐車場にはトイレや案内看板が整備されています

案内看板脇が登城口となっています

荒山城縄張りと工程 越中中世城郭図面集Ⅲより

駐車場から登ること約5分で城郭に到着。休憩所の東屋が先ず目に飛び込んでくる。

さらにその上には見張り台をイメージした展望台が設置されています。木造のように見えますが、コンクリート製の丸太で組み立てられています。

見張り台があるのは縄張り図の「F郭」
ここから下の北側斜面には「E郭」、「⑦横堀」、東屋が建つ「曲輪」、とひな壇状に並んでいるのがわかります。その先を下ったところが駐車場の方向です。

F郭背後の切岸の付け根部分には浅い溝が彫って有り、

その先は西側谷に突き出た平坦地にまで伸びて大きな横堀となっています。

この「横堀」が、西側に突き出た曲輪と主郭側を分断しています。

西側に突き出た曲輪から、向かい側の主郭方向。
主郭下西側帯曲輪に登る階段付近。

西側に突き出た曲輪からF郭に戻り主郭下帯曲輪の下段にある通路を進み、先ほど見えた「階段」から主郭下西側帯曲輪へと登る。

「主郭下西側帯曲輪」

その先にある「主郭下北側帯曲輪」は一段高くなっています。

主郭下北側帯曲輪から見る「主郭北面」
ここから主郭に登るための「階段」が東側の隅にあり、

「階段」の先はクランクして「虎口」に至る。

標高486.3m、枡形山の頂上にある「主郭削平地」

ここにはベンチや休憩所などの施設は無いが、360度のパノラマが展開し、
北西は能登半島越しの千里浜と日本海まで、

南東は氷見沖から富山湾越しの立山連峰の、両方が楽しめる。

主郭南東隅の虎口

虎口下段の「C郭」は
②竪堀と組み合わせることにより「内枡形」の構造となっているそうです。

「②竪堀」
写真左側に見える斜面にぽっかり空いた窪み

ここから一旦主郭下北帯曲輪まで戻り、その北側隅にある階段を使って「主郭下東面帯曲輪」へ降ります。

更に階段を降りD郭に行きます。

「D郭」は通路のような曲輪だそうですが、これは通路以外の何物でもないと感じましたが、、、。

D郭から東側の谷と下を通る林道

D郭は北から南へと一直線に伸び「横堀」によって北東尾根と分断されている。

ここから北東尾根(石動山方面)と主郭下南面への分岐となる。
まず、主郭下南面に向かい南東側の横堀と南側の横堀を確認したいと思います。
主柿下南面は雑木林に覆われ、急な斜面と段々となった小さな平坦面が組み合わさっています。

「②竪堀」でしょうか?
しかし図面より小規模なのでとても内枡形を構成する重要な施設には思えないので、勘違いかも知れません。

「主郭下南面の横堀」
主郭南隅下の額に掘られた横堀と思われます。

ここから先ほどの南東尾根の分岐に戻ります。
「主郭下南東側横堀」

この横堀はさきほど歩いてきたD郭先の、北東尾根を分断する横堀に繋がっているのではないかと思います。
そしてその横堀の隣、北東尾根側に「二重の堀」が切ってありました。
D郭先端の横堀と並行で、尾根に対しては垂直の位置関係です。

北東尾根を石動山方向に進みますが、今歩いているところはは堀なんでしょうか?
写真左手が尾根の頂点で、左右の谷方向に向かって下り斜面となります。
尾根の頂上は樹木に覆われ、今は歩くことが困難です。従ってこの堀のような人工的な部分を歩いています。

この「通路?」と平行に掘られた「空堀」
尾根付け根の「二重の堀」辺りから尾根最初の「切堀」までの50mにも及ぶ長大なものです。

先ほどの主郭下南面横堀、主郭下南東面横堀、そしてこの尾根南側横堀の三点セット。
徹底的に南側を防御し、特に南東尾根から城郭に入り込む隙を与えない徹底した守りの施設。
「南東尾根最初の堀切」

「南東尾根二番目の堀切」は北側斜面にだけ彫られているが、最初の堀切より大規模です。

その先尾根は石動山に通じる。

ここからは折り返しになります。
D郭を通り、E郭東側の階段に出ます。F郭に立てられた見張り台が見えてます。

E郭下、北尾根の東面に掘られた「空堀」でしょうか?

かなり深い切込みで主郭への侵入を防いでいるように見えます。
現在の登城ルートから見ると離れているので実感がわきませんが、当時この堀によって搦手方向の道が分断されたのかもしれません。

さらに北尾根の西側に掘られた「空堀」でしょうか?
この堀の先は通路になっているようですがクマザサの藪が酷くて進めませんでした。

北東尾根から主郭へは急な崖が立ちはだかり、D郭やC郭を通ってぐるっと回り込むしかありませんが、
北尾根から主郭へは比較的なだらかになっています。
なので北尾根の東西にそれぞれ空堀を備え、さらに主郭下には数段に渡って曲輪を配置して防御を固めたんでしょうね。
主郭への南東側虎口「C郭」や、北側虎口「主郭下北面帯曲輪」はある意味「外枡形」だったのかもしれません。
築城から歴代城主の変遷をみると、「石動山城郭群」→「前田氏」→「佐々氏」→「前田氏」の改修の跡が想像されるようで、コンパクトですが面白い「輪郭式山城??」で、整備が行き届いた展望公園とも言ってよいのではないでしょうか。
荒山峠の祠と記念碑

休憩所と展望台

展望台からの眺望






おまけ画像w
休憩所に置かれた天然木を加工した人のオブジェ
顔と下半身のアレがとってもオチェメで、地元愛に癒されました(^^)/

※2022年6月12日 いしかわ城郭カードリンク、写真追加
【荒山城】
《荒山合戦古戦場》

名称(別名);枡形山城
所在地;富山県氷見市小滝及び、石川県中能登町
城地種類;山城
標高/比高;486.3m/210m
築城年代;16世紀
廃城年代;16世紀末
築城者;天平寺?
主な改修者;
主な城主;菊地氏、天平寺、佐々氏、前田氏
文化財区分;
主な遺構;削平地、切岸、土塁、堀切、竪堀、横堀
近年の主な復元等;物見櫓、東屋
※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ
地図;