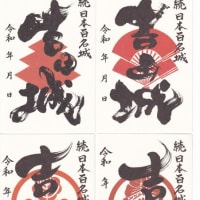岐阜県指定史跡 【明知城跡】
遠山十八城のひとつで土塁を主とした山城。
美濃国東濃地方の地頭
「岩村遠山家」→こちら
「苗木遠山家」→こちら
「明知遠山家」を「遠山三家」と呼ぶ。
この明智町では「明智光秀」生誕の地として、NHK大河「麒麟がくる」放映に併せて大河館がオープンし連日ミーハーなファンで賑わっている。

その大河館(大正ロマン館)近くに遠山家菩提寺・龍護寺がある。

明智遠山氏と土岐明智氏の系譜の中で「明智光秀」が土岐氏の流れを汲むと列せられている。

しかも歴代遠山氏の墓地とは別に「明智光秀公御霊廟」まで建立されている。

異説もあろうが、先ずは明智町に敬意を表し参拝する。

その龍護寺を少し行くと山へ向かう脇道があり、その先に「白鷹(明知)城跡」がある。

最初に迎えてくれるのは「馬場」
ここで下馬し、馬を繋いで徒歩で登城したのか?さしずめ駐車場かな?

「稲荷神社登城口」より登城

遊歩道横には実際に「稲荷神社」があって参道と鳥居、拝殿がある。

ピークは過ぎたようだが紅葉と鳥居の組み合わせが美しい。

ひなびた本殿の湯塗りの扉に錆びた釣り灯篭がシルエットになり風情がある。

脇にある石灯篭にも「桔梗紋」が刻まれ、木漏れ日が何とも言えない郷愁を誘う。

いきなりの道草でしたが、改めて遊歩道「大手道」に戻り歩を進める。

ここで縄張り図と工程を紹介します。

堀切のような「土塁」を施した曲輪跡

「大手門東砦」
ここが侵入者を食い止める重要な仕掛けだったのでしょうね。

「枡形」
大手道を直角にクランクさせ敵の侵入速度を低下させ、砦の上部から停滞した敵を狙い撃ちする構造と機能だと考えられます。

「曲輪」
なんの施設だったのか、説明はありませんでした。

「畝状空堀」
下から攻め上ってくる敵を、細い溝状の道(畝)に誘導することで一列にさせ、正面から狙い撃ちする防御施設。

「堀切」
かなり大規模な溝幅と高さを有する堀切で上部の本丸を遮断していた。

現在は休憩所として「東屋」が設置されています。
この堀切を別角度で見てみます。

上にある「曲輪」から見下ろすと侵入が容易でないことがわかります。

ここで「堀切」から「本丸」までの位置関係を立体的に、高さで比較説明したイラストを紹介します。
下から「堀切」、「枡形虎口」、「帯曲輪」、「二の丸」、「本丸」と配置され守りが固められているのがわかります。

「武者走り」
堀切から土橋までの細い道は家臣の登城に使われていたんでしょうか。

「虎口曲輪」
下に堀切と東屋が見えます。

「帯曲輪」

「腰曲輪」
本丸の高台下にあって本丸を防御する役割があった。

「出丸」
立体イラストでは「土橋」の先に配置されています。

先端にはかなりの削平地があり

土塁も築かれ、一部には石垣のようなものも露出しており興奮しました。

出丸の先端部は「切岸」となっており、容易に登ってこれないようになっています。

出丸「礎石」
数少ない石の遺構にさらに興奮。櫓か何かの礎石なんでしょうかね。

「二の丸」から階段を登ると「本丸」

「本丸」標識

休憩所や縄張り図の案内看板も設置されている

先端部からの展望

明知城は信濃・三河・岡崎に通じる交通の要衝にあり、織田、武田、豊臣、徳川の攻防で取ったり取られたり。
最終的には徳川政権で廃城となり明智遠山氏は徳川家の旗本として江戸で存続。
菩提寺・龍護寺の系譜系図によれば、末裔に「町奉行・遠山金四郎」TVでお馴染み遠山の金さんの名前も見受けられる(笑)

【明知城】
《》
名称(別名); 白鷹城
所在地;岐阜県恵那市明智町
城地種類;平山城
築城年代;宝治元年(1247年)
築城者;遠山景重
主な城主;明知遠山氏
文化財区分;県指定史跡
近年の主な復元等;
天守の現状、形態;
※出典、、、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
地図;
遠山十八城のひとつで土塁を主とした山城。
美濃国東濃地方の地頭
「岩村遠山家」→こちら
「苗木遠山家」→こちら
「明知遠山家」を「遠山三家」と呼ぶ。
この明智町では「明智光秀」生誕の地として、NHK大河「麒麟がくる」放映に併せて大河館がオープンし連日ミーハーなファンで賑わっている。

その大河館(大正ロマン館)近くに遠山家菩提寺・龍護寺がある。

明智遠山氏と土岐明智氏の系譜の中で「明智光秀」が土岐氏の流れを汲むと列せられている。

しかも歴代遠山氏の墓地とは別に「明智光秀公御霊廟」まで建立されている。

異説もあろうが、先ずは明智町に敬意を表し参拝する。

その龍護寺を少し行くと山へ向かう脇道があり、その先に「白鷹(明知)城跡」がある。

最初に迎えてくれるのは「馬場」
ここで下馬し、馬を繋いで徒歩で登城したのか?さしずめ駐車場かな?

「稲荷神社登城口」より登城

遊歩道横には実際に「稲荷神社」があって参道と鳥居、拝殿がある。

ピークは過ぎたようだが紅葉と鳥居の組み合わせが美しい。

ひなびた本殿の湯塗りの扉に錆びた釣り灯篭がシルエットになり風情がある。

脇にある石灯篭にも「桔梗紋」が刻まれ、木漏れ日が何とも言えない郷愁を誘う。

いきなりの道草でしたが、改めて遊歩道「大手道」に戻り歩を進める。

ここで縄張り図と工程を紹介します。

堀切のような「土塁」を施した曲輪跡

「大手門東砦」
ここが侵入者を食い止める重要な仕掛けだったのでしょうね。

「枡形」
大手道を直角にクランクさせ敵の侵入速度を低下させ、砦の上部から停滞した敵を狙い撃ちする構造と機能だと考えられます。

「曲輪」
なんの施設だったのか、説明はありませんでした。

「畝状空堀」
下から攻め上ってくる敵を、細い溝状の道(畝)に誘導することで一列にさせ、正面から狙い撃ちする防御施設。

「堀切」
かなり大規模な溝幅と高さを有する堀切で上部の本丸を遮断していた。

現在は休憩所として「東屋」が設置されています。
この堀切を別角度で見てみます。

上にある「曲輪」から見下ろすと侵入が容易でないことがわかります。

ここで「堀切」から「本丸」までの位置関係を立体的に、高さで比較説明したイラストを紹介します。
下から「堀切」、「枡形虎口」、「帯曲輪」、「二の丸」、「本丸」と配置され守りが固められているのがわかります。

「武者走り」
堀切から土橋までの細い道は家臣の登城に使われていたんでしょうか。

「虎口曲輪」
下に堀切と東屋が見えます。

「帯曲輪」

「腰曲輪」
本丸の高台下にあって本丸を防御する役割があった。

「出丸」
立体イラストでは「土橋」の先に配置されています。

先端にはかなりの削平地があり

土塁も築かれ、一部には石垣のようなものも露出しており興奮しました。

出丸の先端部は「切岸」となっており、容易に登ってこれないようになっています。

出丸「礎石」
数少ない石の遺構にさらに興奮。櫓か何かの礎石なんでしょうかね。

「二の丸」から階段を登ると「本丸」

「本丸」標識

休憩所や縄張り図の案内看板も設置されている

先端部からの展望

明知城は信濃・三河・岡崎に通じる交通の要衝にあり、織田、武田、豊臣、徳川の攻防で取ったり取られたり。
最終的には徳川政権で廃城となり明智遠山氏は徳川家の旗本として江戸で存続。
菩提寺・龍護寺の系譜系図によれば、末裔に「町奉行・遠山金四郎」TVでお馴染み遠山の金さんの名前も見受けられる(笑)

【明知城】
《》
名称(別名); 白鷹城
所在地;岐阜県恵那市明智町
城地種類;平山城
築城年代;宝治元年(1247年)
築城者;遠山景重
主な城主;明知遠山氏
文化財区分;県指定史跡
近年の主な復元等;
天守の現状、形態;
※出典、、、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
地図;