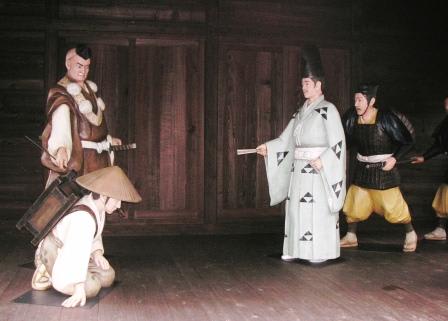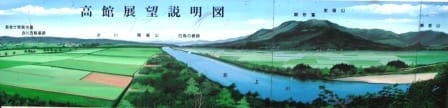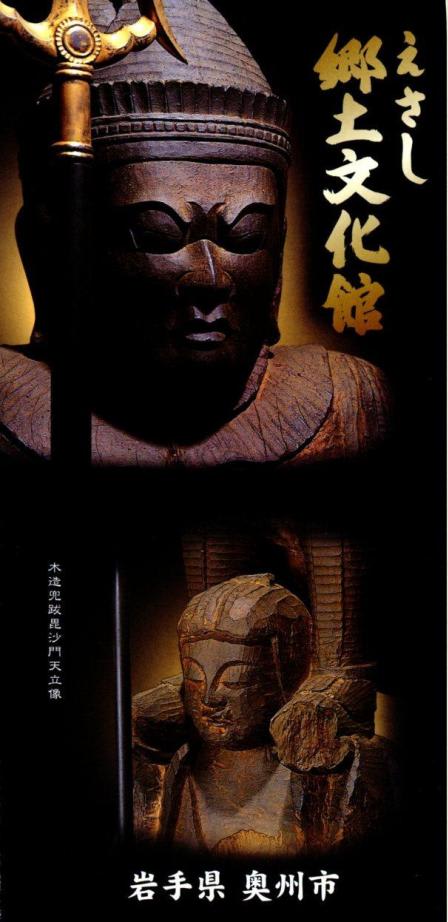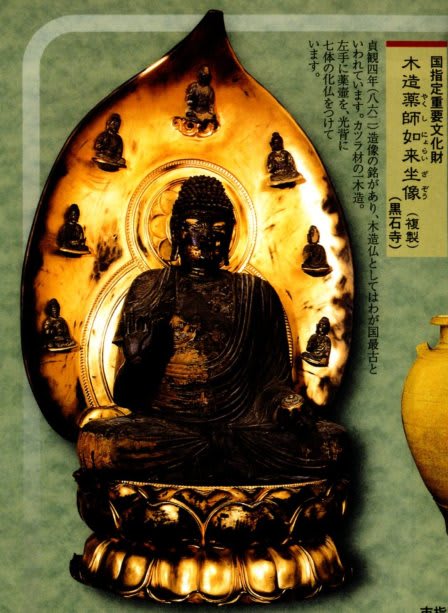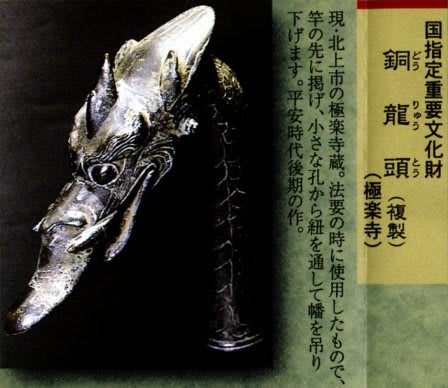福山市西町にある「広島県立歴史博物館」の特別展「姫谷焼-備後に花開いた初期色絵磁器-」を見に行きました。
「姫谷焼」は、江戸時代の初め20年間、広島県福山市加茂町姫谷で作られた焼きものです。
日本の色絵磁器の産地には有田・九谷が知られていますが、この姫谷は第3の産地だったようです。
地元でも15年ぶりの展示だそうで、残存する約100点の内、約50点が揃った展示で、めったにないチャンスです。
最近、「広島県立歴史博物館」の入館料は、大幅に値下げされ、一般で290円になっていました。
高校生まで無料なので、もっと利用者が増えるといいですね。

広島県立歴史博物館の玄関に「姫谷焼」の大きな看板がありました。
看板の向って右に、皿へ絵を描いているマンガのキャラ「イチエモン」があります。
姫谷焼の伝説の陶工「市右衛門」から考えたようです。
館内に「市右衛門」の墓の写真パネルがあり、姫谷焼窯跡の近くにあると紹介されていました。
■看板の内容を転記します。
幻のやきもの
15年ぶりに出会う姫谷焼
平成20年度春の展示
姫谷焼(ひめたにやき)
一備後に花開いた初期色絵磁器-
4月25日(金)→6月8日(日)
広島県立歴史博物館

パンフレットに掲載されていたお皿の絵柄(左)と、お皿の写真です。
赤・黄・緑・青・紺とカラフルですが、素朴さのある美しい絵柄です。
■「姫谷焼」のパンフレットに記載された案内文を転記します。
幻の姫谷焼
広島県の備後地方には、古くから姫谷焼と呼ばれる色絵磁器の血がいくつか伝えられてきました。これらのやきものは、現在の福山市加茂町百谷にある姫谷という場所で焼かれたものと伝えられていました。しかし、いつ、だれが、何のために製作したのか、どのような作品が製作されたのかなど、その実体は明らかでない点が多く、長らく幻の姫谷焼とも呼ばれていました。
窯跡の発掘調査
戦前には、当時の深安郡広瀬村大字姫谷(現在の福山市加茂町百谷)に姫谷焼の窯跡が存在することがつきとめられました。そして、戦後の昭和52・53年までに何度かの発掘調査が実施され、姫谷焼の研究は大きく進展しました。
現在では、姫谷焼は有田焼(佐賀県)・九谷焼(石川県)とともに江戸時代前期に製作された初期色絵磁器の一つであること、色絵のほかに染付・白磁・青磁・陶器なども製作していたこと、17世紀後半の限られた時期に製作されたことなどが明らかになっています。
15年ぶりの展示会
姫谷焼の作品には個人蔵のものが多く、それらを鑑賞する機会は決して多くありません。そこで、このたび広島県立歴史博物館では福山ロータリークラブとの共催により、地元に伝えられている代表的な姫谷焼の作品に触れるための展示会を介画しました。
姫谷焼の展展会としては、平成5年に福山城博物館で開催されて以来、15年ぶりの企画です。ぜひこの機会に、江戸時代前期の一時期、備後に花開いたやきもの文化の精華をお発しみください。

パンフレットに掲載されていたお絵皿の写真です。
古さを感じさせない落ち着いた親しみの持てる絵柄です。
展示品の中には同じ絵柄の皿が数枚並んでいるものがありました。
よく見ると少しづつ絵の違いがあるものの、それぞれが美しく、熟練した職人の手書きの技能を感じさせられます。
地元の江戸時代の文献「西備名区」(馬屋原呂平)では、福山藩主となった水野勝成が若い頃、親から勘当されて諸国を徘徊していた頃、姫谷焼の窯に滞在し、作業を手伝ったことや、後に福山藩主として赴任した後、窯の主人を援助して苦労の多い焼き物作りから引退させたことが書かれています。
しかし、陶器の生産開始年代と、水野勝成が諸国を徘徊していた時代に明らかなズレがあるそうです。
4代藩主の水野勝種が関っていた説もあり、姫谷焼にはまだ多くの謎に包まれているようです。
初代福山藩主水野勝成は、徳川家康の従兄で、福山駅近くにある「天下橋」も家康(天下様)との縁で造られたと言われています。
バラ祭りの5月18日、福山市船町商店街の景品付きクイズで「天下橋」が問題になっていました。
「姫谷焼」は、江戸時代の初め20年間、広島県福山市加茂町姫谷で作られた焼きものです。
日本の色絵磁器の産地には有田・九谷が知られていますが、この姫谷は第3の産地だったようです。
地元でも15年ぶりの展示だそうで、残存する約100点の内、約50点が揃った展示で、めったにないチャンスです。
最近、「広島県立歴史博物館」の入館料は、大幅に値下げされ、一般で290円になっていました。
高校生まで無料なので、もっと利用者が増えるといいですね。

広島県立歴史博物館の玄関に「姫谷焼」の大きな看板がありました。
看板の向って右に、皿へ絵を描いているマンガのキャラ「イチエモン」があります。
姫谷焼の伝説の陶工「市右衛門」から考えたようです。
館内に「市右衛門」の墓の写真パネルがあり、姫谷焼窯跡の近くにあると紹介されていました。
■看板の内容を転記します。
幻のやきもの
15年ぶりに出会う姫谷焼
平成20年度春の展示
姫谷焼(ひめたにやき)
一備後に花開いた初期色絵磁器-
4月25日(金)→6月8日(日)
広島県立歴史博物館

パンフレットに掲載されていたお皿の絵柄(左)と、お皿の写真です。
赤・黄・緑・青・紺とカラフルですが、素朴さのある美しい絵柄です。
■「姫谷焼」のパンフレットに記載された案内文を転記します。
幻の姫谷焼
広島県の備後地方には、古くから姫谷焼と呼ばれる色絵磁器の血がいくつか伝えられてきました。これらのやきものは、現在の福山市加茂町百谷にある姫谷という場所で焼かれたものと伝えられていました。しかし、いつ、だれが、何のために製作したのか、どのような作品が製作されたのかなど、その実体は明らかでない点が多く、長らく幻の姫谷焼とも呼ばれていました。
窯跡の発掘調査
戦前には、当時の深安郡広瀬村大字姫谷(現在の福山市加茂町百谷)に姫谷焼の窯跡が存在することがつきとめられました。そして、戦後の昭和52・53年までに何度かの発掘調査が実施され、姫谷焼の研究は大きく進展しました。
現在では、姫谷焼は有田焼(佐賀県)・九谷焼(石川県)とともに江戸時代前期に製作された初期色絵磁器の一つであること、色絵のほかに染付・白磁・青磁・陶器なども製作していたこと、17世紀後半の限られた時期に製作されたことなどが明らかになっています。
15年ぶりの展示会
姫谷焼の作品には個人蔵のものが多く、それらを鑑賞する機会は決して多くありません。そこで、このたび広島県立歴史博物館では福山ロータリークラブとの共催により、地元に伝えられている代表的な姫谷焼の作品に触れるための展示会を介画しました。
姫谷焼の展展会としては、平成5年に福山城博物館で開催されて以来、15年ぶりの企画です。ぜひこの機会に、江戸時代前期の一時期、備後に花開いたやきもの文化の精華をお発しみください。

パンフレットに掲載されていたお絵皿の写真です。
古さを感じさせない落ち着いた親しみの持てる絵柄です。
展示品の中には同じ絵柄の皿が数枚並んでいるものがありました。
よく見ると少しづつ絵の違いがあるものの、それぞれが美しく、熟練した職人の手書きの技能を感じさせられます。
地元の江戸時代の文献「西備名区」(馬屋原呂平)では、福山藩主となった水野勝成が若い頃、親から勘当されて諸国を徘徊していた頃、姫谷焼の窯に滞在し、作業を手伝ったことや、後に福山藩主として赴任した後、窯の主人を援助して苦労の多い焼き物作りから引退させたことが書かれています。
しかし、陶器の生産開始年代と、水野勝成が諸国を徘徊していた時代に明らかなズレがあるそうです。
4代藩主の水野勝種が関っていた説もあり、姫谷焼にはまだ多くの謎に包まれているようです。
初代福山藩主水野勝成は、徳川家康の従兄で、福山駅近くにある「天下橋」も家康(天下様)との縁で造られたと言われています。
バラ祭りの5月18日、福山市船町商店街の景品付きクイズで「天下橋」が問題になっていました。