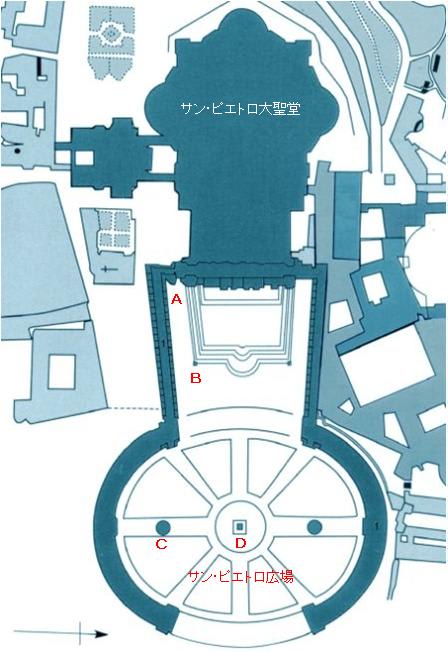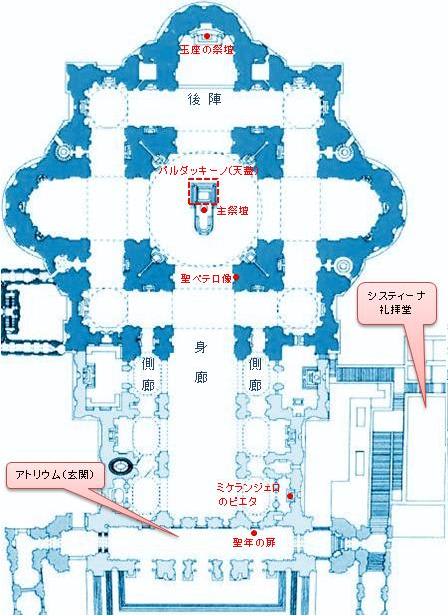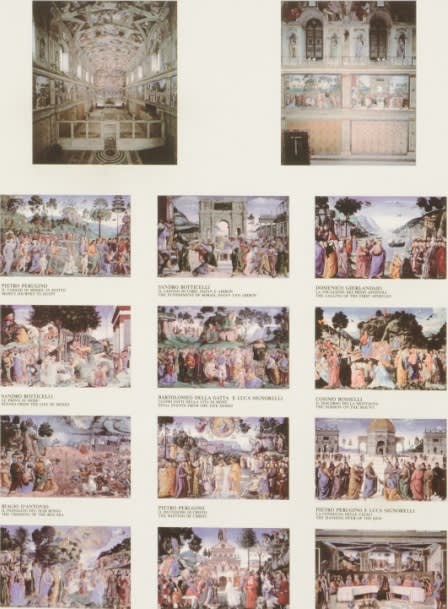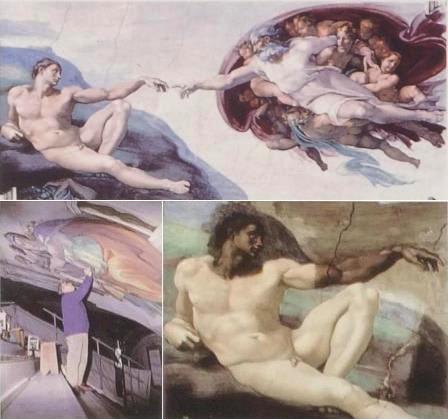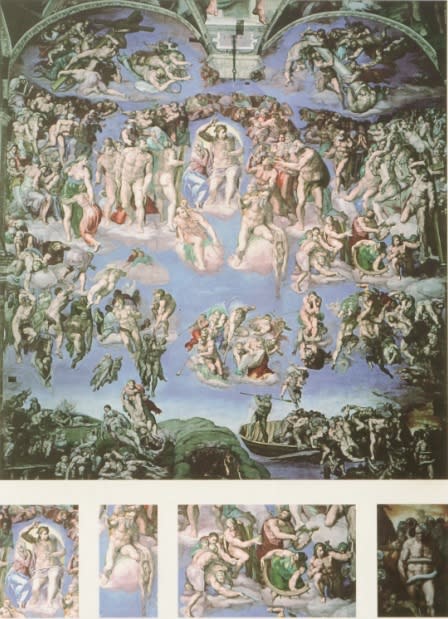ゴールデンウィークに行った北陸の旅行の続きです。
5月2日、能登地方の「気多大社」に続いて「阿岸本誓寺[あぎしほんせいじ]」に行きました。

「阿岸本誓寺」の山門前の風景です。
門の脇の石碑に「能登阿岸 新巻山本誓寺」とあり、真宗大谷派の寺院です。
向かって左の立て札には石川県や、輪島市に登録された文化財などが案内されています。
冒頭には県指定古文書として阿岸本誓寺古文書471点が記載されており、歴史的に高い価値を持つ数百年前の古文書が伝わってきたようです。
向かって右に道路が広くなった駐車場スペースがあり、静かな集落の中に建つ寺院でした。

能登半島の地図です。
「阿岸本誓寺」は、赤丸の場所で、能登半島の海岸を一周する国道249号から右折し、約1Km進むと右手に見えて来ます。
山沿いの小さな集落の中に大きな茅葺の屋根を見つけ、路地を右に曲がると山門の正面でした。

山門の脇に珍しい「鼓楼」がありました。
かつては時を告げる太鼓の音が響いていたものと思われます。
山門を入ると「鐘楼」もあり、それぞれの役割がどうなっていたのか興味があるところです。
老朽化したためか、二階の板壁に白いボードが立て掛けられ、少し痛々しい感じです。(雪害対策だったのかも知れませんが・・・)

山門の門扉に二つの家紋がありました。
徳川家の「三つ葉葵」、二条家の「二条藤」と言われる下がり藤の紋です。
「二条藤」の紋は、1839年(天保10)関白左大臣の二条家の息女「五百姫」が本誓寺住職家に嫁いでいることによるものと思われます。
「三つ葉葵」の紋は、1610年(慶長15)、「阿岸本誓寺」が鳳至郡(能登半島北西部)の触頭[ふれがしら]寺院となり、徳川幕府や、加賀藩の宗教統治の一翼を担うようになったとされ、そのことによるものでしょうか。

山門を額とした風景画のように茅葺の本堂の堂々とした姿が現れてきました。
5月にもかかわらず左手に満開の桜も見え、すばらしい風景にしばらく立ち止まって見ていました。
五木寛之さんの「百寺巡礼」のDVDで、「阿岸本誓寺」を見て北陸の旅を思いつきましたが、実物の風景には格別な思いがこみ上げてきます。

山門を入ると、左手前方に鐘楼と、枝を広げた満開の桜がありました。
桜の前の石碑には、「石川県指定 アギシコギクザクラ」とあり、毎年4月中旬から5月上旬を開花時期とするのようです。
阿岸本誓寺の「アギシコギクザクラ」は、二条家から花嫁と共に当地に持ち込まれた原木の子孫のようです。
■鐘楼前に桜の案内板がありました。
*******************************************************************************
石川県指定天然記念物 アギシコギクザクラ
指定年月日 昭和四十三年八月六日
指定理由 天然記念物基準植物の部 第一種
山桜系の一種で一花に八十枚~百四十枚の花弁をつける。つぼみは始め桜赤色を呈するが開くに従い外輪の花冠から淡色となりほとんど白色になる。
石川県教育委員会
輪島市教育委員会
*******************************************************************************
前回掲載の「気多大社」の「気多の白菊桜」が、山桜系で、花びらも多くあり、開花時期も同じであることから、同じルーツの桜だったのかも知れません。

たくさんの花びらがつく「アギシコギクザクラ」の花です。
前回掲載の「気多の白菊桜」の写真と比較しても違いはよく分かりません。

山門を入り、右手に建つ庫裏です。
高い身分の二条家と姻戚関係になった歴史を持つ阿岸住職の住まいは、やはり格調の高い玄関です。
民衆の信仰に支えられて、守り続けられた素朴な茅葺屋根とは対照的ですが、時代をしっかりと生き延びてきたことがうかがえます。

庫裏から本堂への渡り廊下がありました。
建物をつなぐ渡り廊下は、福井の永平寺や、金沢市の大乘寺などでも見られましたが、雪の多い地方では特に必要だったものと思われます。
渡り廊下の向こうに見える建物は書院のようです。

茅葺の本堂が美しく見えると思われるポイントを探して撮った風景です。
全国でも最大級の大きさを誇る茅葺屋根の建物ですが、瓦葺の建物にない素朴なやさしさが感じられます。

本堂の前には苔生した石段が印象的でした。
大勢の人が出入り出来るように石段や、建物の入口はかなりの広さで造られています。
しかし、驚くほど苔生したこの石段は、過疎が進む地方の苦しい実態を映しているようです。
五木寛之さんの「百寺巡礼」のDVDでは大勢の地元の人が集い、住職の説教に耳を傾け、五木さんの飛び入りの講話もありました。
■本堂石段横に案内板がありました。
*******************************************************************************
石川県指定有形文化財 建造物
阿岸本誓寺 本堂
本堂 一棟
附 棟札 二棟
一、指定年月日 平成四年十月九日
二、指定の理由
阿岸本誓寺本堂は、文永五年(1268)善了法師の創建と伝えられ、鳳至郡百六ヶ寺の触頭[ふれがしら]をつとめた県下有数の真宗大谷派寺院で有り、大規模建造物にもかかわらず、豪快な茅葺き屋根を保持していることは県内はもとより全国的にも稀有な文化財である。
三、説明
本堂は、入母屋造り、平入り、総茅葺きで、正面に四本柱の三間向拝を設ける。
規模は、正面桁行柱間九間(24.12m)梁行柱間十間(23.95m)棟高22.5mの大規模な建物である。
本堂内部は、畳130帖を敷きつめた外陣、中央後方に須弥壇[しゅみだん]を安置する内陣、外陣の正面及び左右に広縁をめぐらしている。
棟札には、越後国三嶋郡間瀬村の大工篠原嘉左衛門藤原副重を棟梁として、 安永九年(1780)に起工し、十二年間の歳月をかけ寛政四年(1792)に棟上げしたことが記されている。
平成六年三月三十一日
石川県教育委員会
輪島市教育委員会
*******************************************************************************

本堂に向かって左側の風景です。
小さな建物は「和合堂」と名付けられた納骨堂で、その前にしだれ桜が美しく咲き乱れていました。
さびれを感じる境内の風景ですが、この周囲だけは華やいだ雰囲気に支配されていました。
5月2日、能登地方の「気多大社」に続いて「阿岸本誓寺[あぎしほんせいじ]」に行きました。

「阿岸本誓寺」の山門前の風景です。
門の脇の石碑に「能登阿岸 新巻山本誓寺」とあり、真宗大谷派の寺院です。
向かって左の立て札には石川県や、輪島市に登録された文化財などが案内されています。
冒頭には県指定古文書として阿岸本誓寺古文書471点が記載されており、歴史的に高い価値を持つ数百年前の古文書が伝わってきたようです。
向かって右に道路が広くなった駐車場スペースがあり、静かな集落の中に建つ寺院でした。

能登半島の地図です。
「阿岸本誓寺」は、赤丸の場所で、能登半島の海岸を一周する国道249号から右折し、約1Km進むと右手に見えて来ます。
山沿いの小さな集落の中に大きな茅葺の屋根を見つけ、路地を右に曲がると山門の正面でした。

山門の脇に珍しい「鼓楼」がありました。
かつては時を告げる太鼓の音が響いていたものと思われます。
山門を入ると「鐘楼」もあり、それぞれの役割がどうなっていたのか興味があるところです。
老朽化したためか、二階の板壁に白いボードが立て掛けられ、少し痛々しい感じです。(雪害対策だったのかも知れませんが・・・)

山門の門扉に二つの家紋がありました。
徳川家の「三つ葉葵」、二条家の「二条藤」と言われる下がり藤の紋です。
「二条藤」の紋は、1839年(天保10)関白左大臣の二条家の息女「五百姫」が本誓寺住職家に嫁いでいることによるものと思われます。
「三つ葉葵」の紋は、1610年(慶長15)、「阿岸本誓寺」が鳳至郡(能登半島北西部)の触頭[ふれがしら]寺院となり、徳川幕府や、加賀藩の宗教統治の一翼を担うようになったとされ、そのことによるものでしょうか。

山門を額とした風景画のように茅葺の本堂の堂々とした姿が現れてきました。
5月にもかかわらず左手に満開の桜も見え、すばらしい風景にしばらく立ち止まって見ていました。
五木寛之さんの「百寺巡礼」のDVDで、「阿岸本誓寺」を見て北陸の旅を思いつきましたが、実物の風景には格別な思いがこみ上げてきます。

山門を入ると、左手前方に鐘楼と、枝を広げた満開の桜がありました。
桜の前の石碑には、「石川県指定 アギシコギクザクラ」とあり、毎年4月中旬から5月上旬を開花時期とするのようです。
阿岸本誓寺の「アギシコギクザクラ」は、二条家から花嫁と共に当地に持ち込まれた原木の子孫のようです。
■鐘楼前に桜の案内板がありました。
*******************************************************************************
石川県指定天然記念物 アギシコギクザクラ
指定年月日 昭和四十三年八月六日
指定理由 天然記念物基準植物の部 第一種
山桜系の一種で一花に八十枚~百四十枚の花弁をつける。つぼみは始め桜赤色を呈するが開くに従い外輪の花冠から淡色となりほとんど白色になる。
石川県教育委員会
輪島市教育委員会
*******************************************************************************
前回掲載の「気多大社」の「気多の白菊桜」が、山桜系で、花びらも多くあり、開花時期も同じであることから、同じルーツの桜だったのかも知れません。

たくさんの花びらがつく「アギシコギクザクラ」の花です。
前回掲載の「気多の白菊桜」の写真と比較しても違いはよく分かりません。

山門を入り、右手に建つ庫裏です。
高い身分の二条家と姻戚関係になった歴史を持つ阿岸住職の住まいは、やはり格調の高い玄関です。
民衆の信仰に支えられて、守り続けられた素朴な茅葺屋根とは対照的ですが、時代をしっかりと生き延びてきたことがうかがえます。

庫裏から本堂への渡り廊下がありました。
建物をつなぐ渡り廊下は、福井の永平寺や、金沢市の大乘寺などでも見られましたが、雪の多い地方では特に必要だったものと思われます。
渡り廊下の向こうに見える建物は書院のようです。

茅葺の本堂が美しく見えると思われるポイントを探して撮った風景です。
全国でも最大級の大きさを誇る茅葺屋根の建物ですが、瓦葺の建物にない素朴なやさしさが感じられます。

本堂の前には苔生した石段が印象的でした。
大勢の人が出入り出来るように石段や、建物の入口はかなりの広さで造られています。
しかし、驚くほど苔生したこの石段は、過疎が進む地方の苦しい実態を映しているようです。
五木寛之さんの「百寺巡礼」のDVDでは大勢の地元の人が集い、住職の説教に耳を傾け、五木さんの飛び入りの講話もありました。
■本堂石段横に案内板がありました。
*******************************************************************************
石川県指定有形文化財 建造物
阿岸本誓寺 本堂
本堂 一棟
附 棟札 二棟
一、指定年月日 平成四年十月九日
二、指定の理由
阿岸本誓寺本堂は、文永五年(1268)善了法師の創建と伝えられ、鳳至郡百六ヶ寺の触頭[ふれがしら]をつとめた県下有数の真宗大谷派寺院で有り、大規模建造物にもかかわらず、豪快な茅葺き屋根を保持していることは県内はもとより全国的にも稀有な文化財である。
三、説明
本堂は、入母屋造り、平入り、総茅葺きで、正面に四本柱の三間向拝を設ける。
規模は、正面桁行柱間九間(24.12m)梁行柱間十間(23.95m)棟高22.5mの大規模な建物である。
本堂内部は、畳130帖を敷きつめた外陣、中央後方に須弥壇[しゅみだん]を安置する内陣、外陣の正面及び左右に広縁をめぐらしている。
棟札には、越後国三嶋郡間瀬村の大工篠原嘉左衛門藤原副重を棟梁として、 安永九年(1780)に起工し、十二年間の歳月をかけ寛政四年(1792)に棟上げしたことが記されている。
平成六年三月三十一日
石川県教育委員会
輪島市教育委員会
*******************************************************************************

本堂に向かって左側の風景です。
小さな建物は「和合堂」と名付けられた納骨堂で、その前にしだれ桜が美しく咲き乱れていました。
さびれを感じる境内の風景ですが、この周囲だけは華やいだ雰囲気に支配されていました。