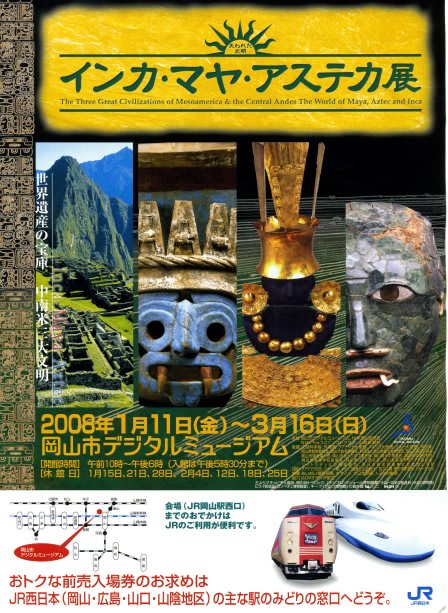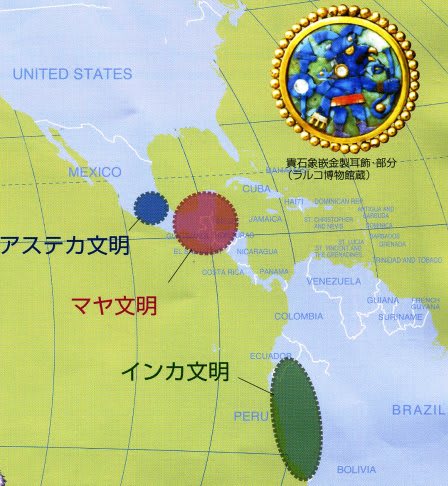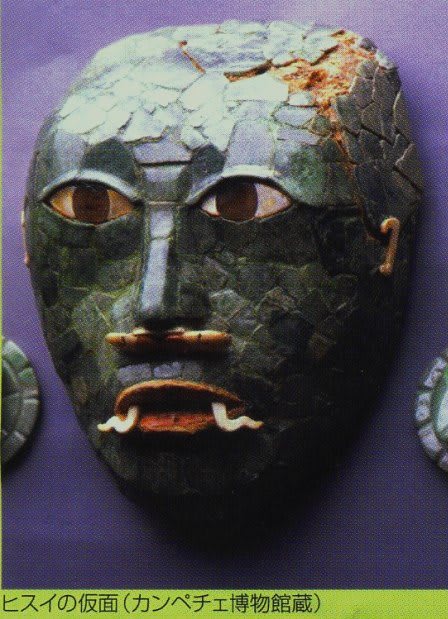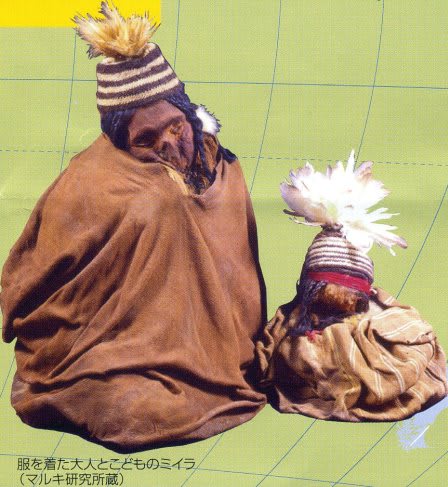今回は、沖縄旅行の思い出を中断、次回から再開します。
7月5日、福山市霞町に福山市の中央図書館を中心とした施設「まなびの館ローズコム」が開館しました。
約38万冊の本が備えられているそうですが、2フロアー全体に本棚が並んでいました。
7月5~6日は、開館の記念イベント「ローズコム七夕フェスタ」が開催されました。

7月5日の夜、久松通商店街の土曜夜店の見物を兼ねて最初にローズコムへ行きました。
上の看板の写真に2日間のイベント予定が案内されていました。

ローズコムの敷地に野外ステージがあり、座席エリアは一面芝生です。
バラ祭りのパレードで何度か見た「備後新選組」の踊りが終わり、「備後ばらバラよさこい踊り隊」の登場です。
「備後ばらバラよさこい踊り隊」は、通称「ビンバラ」と言うようです。
写真は、最初の挨拶が始まった場面です。
妻の知り合いの人が踊るので、一番前に座り、デジカメで何枚も撮りましたが、ブレや、ボケの写真が多くなってしまいました。
踊りは、20:15から約10分間でしたが、とても楽しい気持ちになる踊りでした。

踊りが始まり、しばらくすると揃いの黒い衣装に変化があり、ピンクと、緑の袖が現われました。
バラ祭りのパレードでも見ましたが、夜のステージで見ると新鮮な感じがします。

踊りも佳境に入り、赤い縁のメガネをかけた女性が、ステージの前に出てきて後ろの踊りとは違う動きで、右から左に踊りながら歩いて行きました。
とても楽しそうです。

「備後ばらバラよさこい踊り隊」にはかわいい小学生から元気な年配の方までいて、とても親しみのあるチームです。
踊りは激しい動きも多く、この踊りはスポーツ系のようです。

⑥今年の5月18日、「福山ばら祭」のパレードで見た「備後ばらバラよさこい踊り隊」です。
楽しく元気で踊っていました。

踊りはいよいよ最後に近づき、盛り上がっています。
「備後ばらバラよさこい踊り隊」は、「高知よさこい祭全国大会」へ出場し、4回連続で受賞しているそうです。
「福山ばら祭」のパレードで、チームの紹介があり、初めて知りました。
==========================================================================
■「高知よさこい祭全国大会」のサイトに昨年までの受賞チームが掲載されていましたので転記します。
なんと2006年には「備後新選組」も受賞し、福山から2チームが受賞していました。
2007年
武政英策賞 京町・新京橋 ゑびすしばてん連 高知県
最優秀賞「輝」 六陸~RIKU~ 東北地区合同
優秀賞「彩」 備後ばらバラよさこい踊り隊 広島県★
優秀賞「粋」 ぞっこん町田'98 東京都
優秀賞「睦」 早稲田大学“踊り侍” 東京都
優秀賞「艶」 甲斐◇風林火山 山梨県
優秀賞「豪」 伊予からの風 純信連 愛媛県
ぺギー葉山賞 させぼ飛躍年隊2007 長崎県
2006年
武政英策賞 とらっく((社)高知県トラック協会)
最優秀賞「輝」 ぞっこん町田'98 東京都
優秀賞「彩」 琉楽座 沖縄県
優秀賞「粋」 鳥取県よさこい踊り子隊 鳥取県
優秀賞「睦」 備後新選組 広島県●
優秀賞「艶」 原宿よさこい連 東京都
優秀賞「豪」 備後ばらバラよさこい踊り隊 広島県★
ぺギー葉山賞 梼原 高知県
2005年
武政英策賞 上町よさこい鳴子連
優秀賞「粋」 六陸〜RIKU〜
優秀賞「睦」 KAKOGAWA踊っこ祭り 加古乃花舞
優秀賞「艶」 ALL☆STAR
優秀賞「豪」 早稲田よさこいプロジェクト×踊り侍
優秀賞「夢」 武州よさこい上總組
ぺギー葉山賞 備後ばらバラよさこい踊り隊★
2004年
武政英策賞 とらっく((社)高知県トラック協会)
優秀賞「粋」 備後ばらバラよさこい踊り隊★
優秀賞「睦」 六陸〜RIKU〜
優秀賞「艶」 夢遊人
優秀賞「豪」 伊予からの風 純信連
優秀賞「夢」 武州よさこい上總組
ぺギー葉山賞 上町よさこい鳴子連
==========================================================================
7月5日、福山市霞町に福山市の中央図書館を中心とした施設「まなびの館ローズコム」が開館しました。
約38万冊の本が備えられているそうですが、2フロアー全体に本棚が並んでいました。
7月5~6日は、開館の記念イベント「ローズコム七夕フェスタ」が開催されました。

7月5日の夜、久松通商店街の土曜夜店の見物を兼ねて最初にローズコムへ行きました。
上の看板の写真に2日間のイベント予定が案内されていました。

ローズコムの敷地に野外ステージがあり、座席エリアは一面芝生です。
バラ祭りのパレードで何度か見た「備後新選組」の踊りが終わり、「備後ばらバラよさこい踊り隊」の登場です。
「備後ばらバラよさこい踊り隊」は、通称「ビンバラ」と言うようです。
写真は、最初の挨拶が始まった場面です。
妻の知り合いの人が踊るので、一番前に座り、デジカメで何枚も撮りましたが、ブレや、ボケの写真が多くなってしまいました。
踊りは、20:15から約10分間でしたが、とても楽しい気持ちになる踊りでした。

踊りが始まり、しばらくすると揃いの黒い衣装に変化があり、ピンクと、緑の袖が現われました。
バラ祭りのパレードでも見ましたが、夜のステージで見ると新鮮な感じがします。

踊りも佳境に入り、赤い縁のメガネをかけた女性が、ステージの前に出てきて後ろの踊りとは違う動きで、右から左に踊りながら歩いて行きました。
とても楽しそうです。

「備後ばらバラよさこい踊り隊」にはかわいい小学生から元気な年配の方までいて、とても親しみのあるチームです。
踊りは激しい動きも多く、この踊りはスポーツ系のようです。

⑥今年の5月18日、「福山ばら祭」のパレードで見た「備後ばらバラよさこい踊り隊」です。
楽しく元気で踊っていました。

踊りはいよいよ最後に近づき、盛り上がっています。
「備後ばらバラよさこい踊り隊」は、「高知よさこい祭全国大会」へ出場し、4回連続で受賞しているそうです。
「福山ばら祭」のパレードで、チームの紹介があり、初めて知りました。
==========================================================================
■「高知よさこい祭全国大会」のサイトに昨年までの受賞チームが掲載されていましたので転記します。
なんと2006年には「備後新選組」も受賞し、福山から2チームが受賞していました。
2007年
武政英策賞 京町・新京橋 ゑびすしばてん連 高知県
最優秀賞「輝」 六陸~RIKU~ 東北地区合同
優秀賞「彩」 備後ばらバラよさこい踊り隊 広島県★
優秀賞「粋」 ぞっこん町田'98 東京都
優秀賞「睦」 早稲田大学“踊り侍” 東京都
優秀賞「艶」 甲斐◇風林火山 山梨県
優秀賞「豪」 伊予からの風 純信連 愛媛県
ぺギー葉山賞 させぼ飛躍年隊2007 長崎県
2006年
武政英策賞 とらっく((社)高知県トラック協会)
最優秀賞「輝」 ぞっこん町田'98 東京都
優秀賞「彩」 琉楽座 沖縄県
優秀賞「粋」 鳥取県よさこい踊り子隊 鳥取県
優秀賞「睦」 備後新選組 広島県●
優秀賞「艶」 原宿よさこい連 東京都
優秀賞「豪」 備後ばらバラよさこい踊り隊 広島県★
ぺギー葉山賞 梼原 高知県
2005年
武政英策賞 上町よさこい鳴子連
優秀賞「粋」 六陸〜RIKU〜
優秀賞「睦」 KAKOGAWA踊っこ祭り 加古乃花舞
優秀賞「艶」 ALL☆STAR
優秀賞「豪」 早稲田よさこいプロジェクト×踊り侍
優秀賞「夢」 武州よさこい上總組
ぺギー葉山賞 備後ばらバラよさこい踊り隊★
2004年
武政英策賞 とらっく((社)高知県トラック協会)
優秀賞「粋」 備後ばらバラよさこい踊り隊★
優秀賞「睦」 六陸〜RIKU〜
優秀賞「艶」 夢遊人
優秀賞「豪」 伊予からの風 純信連
優秀賞「夢」 武州よさこい上總組
ぺギー葉山賞 上町よさこい鳴子連
==========================================================================