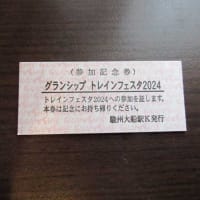昭和の初め頃、蒸気機関車を筆頭に電車や電気機関車までもが流線形ばやりだった事があります。もちろん私自身はリアルタイムでそれを経験していないのですが、当時を偲ばせる形式のNゲージモデルはなかなかの充実度を見せます。
そんな訳で今回は流線型機特集の第一陣としてC55を取り上げたいと思います。
SNShouo71IMG_7497.jpg
C55の流線形で最も入手しやすいモデルはマイクロエースではないかと思います。私も動力改良版が出た位のタイミングで入線させています。
ほぼワンオフと言っていいボディ構成と3シリンダーという個性的な中身のC53をポルシェやフェラーリに例えるなら中身はコンベンショナルな2シリンダ(実質C54のバージョンアップ版)と量産向けのボディ(流線型機としては異例な20両の大所帯)を纏ったC55はさしずめフォードムスタングかカローラレビンに例えられましょうか。


デザインはC53やEF55に比べると日本人好みのあっさり感が感じられます。事実上の試作機扱いで緊張感のあるマッス感が売りのC53に対し、適度の肩の力が抜けたとでもいうのか凄味のない見ていてリラックスできる格好ではあります。
動力が改良版との事で走りについて問題はありませんが、デザインがデザインなだけに建築限界ぎりぎりまで膨らませたボディはなかなかの迫力です。

そしてNゲージの完成品としては初の中村精密のC55
従来の中村製蒸気の殆どがダイカスト鋳造ボディで細密感に欠ける(という評判)だったのに対し、流線型ボディのC55とC53は真鍮板で造形されている為非常にすっきりしたプロポーションになっているのが特長だそうですが実際現物を見ると、最近の細密志向の蒸機モデルの隣にいても引けを取らない存在感を見せます。
プラ成形の様な独特な肉厚感もなく非常にすっきり(特にキャブの窓周り)したスタイルが特徴。更に塗装も一旦黒を吹いてから帯に相当する部分のみを磨きだすという手の込んだ事をしておりこれもすっきり感に貢献しているようです。

プロポーションはマイクロのそれに比べるとかなりスリムな印象です。
中村の蒸気の大半がそうであるように本機もテンダードライブです。走行性は・・・
従来機より機関車部が軽いらしく先輪が時々止まったりします(笑)が走り自体はパワフルです。テンダードライブとはいえ、非常に強力なユニットを使っている印象でした。
EF55やC53と共にイベント車のスターエンジンです。
それにしても流線型の車両といえば例の「はやぶさ」をはじめとした新幹線、特急電車など平成に入ってからでも数多くの種類が出ているのですが、空力とかがよく解っていなかったこの時期(昭和初期)の流線型車両には実際の性能はともかくデザインに勢いがあって最近好きになってきた感じがします。
(余談ですがこの頃の「冒険ダン吉」に「象が牽引する列車」が出てくるのですが、その象が「日本でもはやっている最新型だから」とこの型のC55みたいなカバーを身に纏っていた話があります。それ位当時の流線型は今以上に華やかなイメージがあったのでしょう)
そんな訳で今回は流線型機特集の第一陣としてC55を取り上げたいと思います。
SNShouo71IMG_7497.jpg
C55の流線形で最も入手しやすいモデルはマイクロエースではないかと思います。私も動力改良版が出た位のタイミングで入線させています。
ほぼワンオフと言っていいボディ構成と3シリンダーという個性的な中身のC53をポルシェやフェラーリに例えるなら中身はコンベンショナルな2シリンダ(実質C54のバージョンアップ版)と量産向けのボディ(流線型機としては異例な20両の大所帯)を纏ったC55はさしずめフォードムスタングかカローラレビンに例えられましょうか。


デザインはC53やEF55に比べると日本人好みのあっさり感が感じられます。事実上の試作機扱いで緊張感のあるマッス感が売りのC53に対し、適度の肩の力が抜けたとでもいうのか凄味のない見ていてリラックスできる格好ではあります。
動力が改良版との事で走りについて問題はありませんが、デザインがデザインなだけに建築限界ぎりぎりまで膨らませたボディはなかなかの迫力です。

そしてNゲージの完成品としては初の中村精密のC55
従来の中村製蒸気の殆どがダイカスト鋳造ボディで細密感に欠ける(という評判)だったのに対し、流線型ボディのC55とC53は真鍮板で造形されている為非常にすっきりしたプロポーションになっているのが特長だそうですが実際現物を見ると、最近の細密志向の蒸機モデルの隣にいても引けを取らない存在感を見せます。
プラ成形の様な独特な肉厚感もなく非常にすっきり(特にキャブの窓周り)したスタイルが特徴。更に塗装も一旦黒を吹いてから帯に相当する部分のみを磨きだすという手の込んだ事をしておりこれもすっきり感に貢献しているようです。

プロポーションはマイクロのそれに比べるとかなりスリムな印象です。
中村の蒸気の大半がそうであるように本機もテンダードライブです。走行性は・・・
従来機より機関車部が軽いらしく先輪が時々止まったりします(笑)が走り自体はパワフルです。テンダードライブとはいえ、非常に強力なユニットを使っている印象でした。
EF55やC53と共にイベント車のスターエンジンです。
それにしても流線型の車両といえば例の「はやぶさ」をはじめとした新幹線、特急電車など平成に入ってからでも数多くの種類が出ているのですが、空力とかがよく解っていなかったこの時期(昭和初期)の流線型車両には実際の性能はともかくデザインに勢いがあって最近好きになってきた感じがします。
(余談ですがこの頃の「冒険ダン吉」に「象が牽引する列車」が出てくるのですが、その象が「日本でもはやっている最新型だから」とこの型のC55みたいなカバーを身に纏っていた話があります。それ位当時の流線型は今以上に華やかなイメージがあったのでしょう)