41番目 ~ 70番目 地蔵 歩行月日2013/09/23
歩行時間:9時間14分 休憩時間:1時間46分 延時間:11時間00分
出発時間:6時05分 到着時間:17時05分
歩 数: 48、000歩 GPS距離:35.8km
行程表
静岡駅 0:15> 41番 0:07> 42番 0:07> 43番 0:07> 44番 0:13> 45番 0:15> 46番
0:33> 47番 0:32> 48番 0:13> 49番 0:42> 50番 0:05> 51番 0:50> 52番 0:16> 53番
0:10> 54番 0:05> 55番 0:13> 56番 0:08> 57番 0:20> 58番 0:43> 59番 0:10> 60番
0:08> 61番 0:17> 62番 0:25> 63番 ~0:10>~ 69番 0:45> 70番 0:25> 草薙駅
67番目(41番) 安南寺
安南寺は新善光寺の前にあった。安南などと聞くと何となく東南アジアを連想してしまうが、安南寺には何の
説明も無かった。で、仕方なく安南を調べてみるとベトナムの中北部の地名と分かったが、それが寺の名前と
関係しているのかは分からない。案外この寺の元あった場所が安倍川の南だったのかもしれない。
山門を入った横に苔むした宝塔があったが、説明がないので謂れは分からない。鐘突き堂の前にも大きな
陶器の土瓶も置いてあり、これは若しかしてベトナムの安南焼かと思ったが、こちらにも説明が無いので
分からない。少々不親切な寺だ。


安南寺の宝塔 安南寺の大土瓶
地蔵は地蔵堂に大量生産型の六地蔵を祀ってあったが興味は湧かなかった。それより露座の子育て地蔵の
横に置かれた、四角錐に地蔵がビッシリ彫ってある地蔵塚(?)の方が興味を惹かれた。
こんな地蔵像を見るのは初めてだった。


安南寺山門 安南寺の地蔵塚
安南寺の地図
68番目(64番) 少林寺(拳法)
安南寺の隣が少林寺で、この寺も名前に興味が湧いた。少林寺と言えば、いわずと知れた少林寺拳法の
発祥の寺だ。この寺は関係あるのだろうか? この寺にも案内板は無いので自分で調べるしかない。
先ず驚いたのは少林寺拳法とは、日本発祥の武術で、しかも戦後日本人の「宋道臣」が創始者だった事だ。
私の想像していた中国発祥の拳法は「小林拳」といい、こちらの創始者は、伝説や近年の文献によると禅宗の
開祖の達磨大師ともいわれていて、明代の嵩山少林寺で武術を練習していたらしい。
となれば当然この少林寺は、拳法とは何ら関係が無いのだ。マー少林寺は臨済宗なので禅宗には違いないが。
百地蔵のHPでは、少林寺には延命地蔵があるとなっていたが、境内にあったのは新し六地蔵だけだった。


少林寺 少林寺の六地蔵
少林寺の地図
69番目(65番) 菩提樹院(国分尼寺)
寺団地最後の菩提樹院の山門前に建っている案内板を見て興味を惹かれた。
先ず驚いたのが案内板に 「旧国分尼寺」 とあった事だ。
私のホームグランドとしている大崩山塊の焼津市花沢に法華寺という寺がある。その寺の説明に
「当山は奈良時代の聖武天皇の御宇、法華罪の駿河国分尼寺として建立されたといわれる」書いてある。
これを読んだ時は、国府の駿府から離れている焼津の、しかも山の中にある寺が国分尼寺? と疑問を
感じ調べてみると、曹洞宗静岡県第一宗務所青年会 のHPに
「当山は天台宗に属し、奈良時代第45代聖武天皇の御宇、法華滅罪の駿河国分尼寺として建立された」と
あった。その時は宗教家の団体が書いてあるのだから間違いないだろうと思ったいた。
だが今回菩提樹院も国分尼寺かもしれないと分かり、再度HPと案内板を読み返してみると、その文章の
内容も構成も殆ど同じだった。これはどちらかが引用したとも思われる。
更に、案内板が立っている場所は法華寺の境内ではなく、大分離れた場所の見晴台にあるのも不自然だ。
それに比べ、菩提樹院の案内板は
「養老5年、勅命により法相宗定額寺(国分寺や尼寺に次ぐ寺格の寺)北川辺に建立。その後、盛衰を繰り
返し、徳川家康公が駿府城を築くに際し、寺町(常盤公園)に移す。その後、静岡大火や静岡大空襲により
焼失するも、昭和20年の区画整理により移転した」(概略)
焼津の住民の私としては、法華寺が国分尼寺だとしたいが、どうも分が悪そうだ。
境内に入ると、今度は「伝 駿河国分寺の塔心礎」の案内板があった。これまた変な話で駿河の国分寺は
前回の百地蔵巡りの最後に寄った国分寺のはずだ。それなのに国分寺の礎石が旧国分尼寺の菩提樹院に
あるとは納得しがたい。だが静岡市の建てた案内板には
「昭和5年、駿府城内から発見され、国分尼寺の後身の伝承を持つ菩提樹院に寄進された。」となっている。
果たして本物と判定した国分寺の塔心礎を、単なる伝承を持つだけの寺院い寄進してしまうだろうか?
更に案内板には「34cmの直径の孔を穿った鑿の痕跡は、本来は寺院の心礎として用いられたもので、中央の
孔は舎利孔であったと考えられる。この舎利孔の大きさは、甲斐や伊豆の国分寺の物とほぼ同じである。」
この石が国分寺の塔心礎と判定されたのは、孔の大きさからだったようだ。
案内板はまだ続いていて、江戸時代には「孔を広げて駿府城内にあった社の手水鉢としていた」とも書いてある。
駿河国分寺は武田信玄の駿河進攻で焼払われたが、江戸時代の安永6年(1777)には、その国分寺跡に
「日本六拾六國於國分寺立之」の石塔が建てられている。それなのに同じ時代に国分寺跡から発掘された
この石を加工して、社の手水鉢として使っただろうか? 私には理解できない。
尤も案内板には、「伝 駿河国分寺の塔心礎」 と 「伝」 が付いてはいたが。


菩提樹院山門 「伝駿河国分寺の塔心礎」
菩提樹院の地図
菩提樹院には、まだ気になる物が有った。それは由比正雪の首塚だ。寺の案内板によると
「由比正雪は駿府宮ヶ崎の紺屋に生まれ、江戸へ出て楠流軍学を学んだあと、牛込に道場を構えて軍学を
指南した。時に、徳川幕府の悪政を改革せんと、幕府転覆を計り、自ら久能山に立て籠もり、東西の同志に
号令せんとしたが、事前に露見し、駿府梅屋町の旅籠梅屋に於いて、同志9名と共に自刃した。同志と共に
安倍川畔にさらし首になるが、縁者の女人が秘かにその首を盗み、寺町の菩提樹院へ葬った。それがこの
首塚で、寺の移転と同時に首塚も移転された。」
何も案内板にケチを付けるのが趣味ではないが、この案内板の「由比正雪は駿府宮ヶ崎の紺屋に生まれ」を
覚えていてください。百地蔵の遍路できっと「由比正雪の生家」の前を通るので ------
イヤー!ここにもさらし首を盗んだ女性がいた。静岡県内では江戸時代の大盗賊の一人、日本座衛門の首を
磐田見付の鈴ヶ森処刑場から盗んで、東海道の金谷宿に埋葬した女性がいたが、由比正雪にもそんな女性が
傍にいたのですね。 しかし、とまた妄想が湧いてくる。
さっきお詣りしてきた来迎院の「宮城野・信夫」の話を覚えていますか。あの二人の女性は由比正雪の恩に
報いるため、処刑場の近くに庵を建てて、正雪の菩提を生涯弔ったとあった。どうせ庵を建てるなら正雪の首が
葬られている菩提樹の首塚の近くに建てて、冥福を祈ればよいと思ってしまうのだが ------
アッ若しかして 正雪の首を盗んだのが女性だったので、宮城野と信夫は嫉妬心を感じていたのかな。


由比正雪の首塚 由比正雪の銅像
70番目(71番) 桃原寺
寺団地の中の5寺は簡単に済むと思っていたが、菩提樹院で思わぬ時間が掛かってしまった。先を急ごう。
谷津山は後ろに去り、右に日本平の丘が近づいてきた。午前中は東海道線の南側歩いたが今は北側を歩く。
今日最後の百地蔵は、この東海道線を渡り、今朝迷子になった東名高速を潜った日本平の中腹にある。
また東名のガードを潜るのかと、嫌な予感に捕らわれてが、案の定、潜った東名のガードと地図のガードが
違って迷子になってしまった。適当に見当を付けて日本平の中腹を目指して登っていたが、民家も無くなり
これ以上登ると畑や林ばかりになっていしまいそうだ。そんな時タイミングよく軽トラが登ってきた。
慌てて手を挙げ軽トラを止めて道を尋ねた。
「桃原寺なら、新しくできた、この道を真っ直ぐ行けば本堂に出ますよ」と。
付いているのか付いていないのか良く分からない。
桃原寺の百地蔵はHPによると「護国地蔵」とあったので、どんな地蔵像かと興味を持っていたが、境内には
それらしき地蔵像は見当たらなかった。本堂の柱には「駿河一国百地蔵第七十一番」の板が張ってあるので
間違いないのだが、きっと本堂の中に祀ってあるのだろう。
境内に「寛永20年(1643)徳川家康没後27年 三代将軍家光時代」と書かれた小さな案内板がついた地蔵尊が
あった。一先ずこの地蔵尊を百地蔵として良しとしておこう。


桃原寺参道 桃原寺の地蔵像
桃原寺の地図
今日の遍路は一日で30ヶ所も廻ってしまったが、矢張りこれでは多すぎる。余りに数が多すぎて前日に調査した
道も覚えきれず迷う事が多かった。マー反省はあるが残りは後30ヶ所。遍路もあと2回か3回で終わりそうだ。
先が見えてきて駅前で飲む乾杯の酒は美味しかった。
ブログの方も後15回も書けば終わりそうなので、予定通り今年中には終わる目途がついた。
歩行時間:9時間14分 休憩時間:1時間46分 延時間:11時間00分
出発時間:6時05分 到着時間:17時05分
歩 数: 48、000歩 GPS距離:35.8km
行程表
静岡駅 0:15> 41番 0:07> 42番 0:07> 43番 0:07> 44番 0:13> 45番 0:15> 46番
0:33> 47番 0:32> 48番 0:13> 49番 0:42> 50番 0:05> 51番 0:50> 52番 0:16> 53番
0:10> 54番 0:05> 55番 0:13> 56番 0:08> 57番 0:20> 58番 0:43> 59番 0:10> 60番
0:08> 61番 0:17> 62番 0:25> 63番 ~0:10>~ 69番 0:45> 70番 0:25> 草薙駅
67番目(41番) 安南寺
安南寺は新善光寺の前にあった。安南などと聞くと何となく東南アジアを連想してしまうが、安南寺には何の
説明も無かった。で、仕方なく安南を調べてみるとベトナムの中北部の地名と分かったが、それが寺の名前と
関係しているのかは分からない。案外この寺の元あった場所が安倍川の南だったのかもしれない。
山門を入った横に苔むした宝塔があったが、説明がないので謂れは分からない。鐘突き堂の前にも大きな
陶器の土瓶も置いてあり、これは若しかしてベトナムの安南焼かと思ったが、こちらにも説明が無いので
分からない。少々不親切な寺だ。


安南寺の宝塔 安南寺の大土瓶
地蔵は地蔵堂に大量生産型の六地蔵を祀ってあったが興味は湧かなかった。それより露座の子育て地蔵の
横に置かれた、四角錐に地蔵がビッシリ彫ってある地蔵塚(?)の方が興味を惹かれた。
こんな地蔵像を見るのは初めてだった。


安南寺山門 安南寺の地蔵塚
安南寺の地図
68番目(64番) 少林寺(拳法)
安南寺の隣が少林寺で、この寺も名前に興味が湧いた。少林寺と言えば、いわずと知れた少林寺拳法の
発祥の寺だ。この寺は関係あるのだろうか? この寺にも案内板は無いので自分で調べるしかない。
先ず驚いたのは少林寺拳法とは、日本発祥の武術で、しかも戦後日本人の「宋道臣」が創始者だった事だ。
私の想像していた中国発祥の拳法は「小林拳」といい、こちらの創始者は、伝説や近年の文献によると禅宗の
開祖の達磨大師ともいわれていて、明代の嵩山少林寺で武術を練習していたらしい。
となれば当然この少林寺は、拳法とは何ら関係が無いのだ。マー少林寺は臨済宗なので禅宗には違いないが。
百地蔵のHPでは、少林寺には延命地蔵があるとなっていたが、境内にあったのは新し六地蔵だけだった。


少林寺 少林寺の六地蔵
少林寺の地図
69番目(65番) 菩提樹院(国分尼寺)
寺団地最後の菩提樹院の山門前に建っている案内板を見て興味を惹かれた。
先ず驚いたのが案内板に 「旧国分尼寺」 とあった事だ。
私のホームグランドとしている大崩山塊の焼津市花沢に法華寺という寺がある。その寺の説明に
「当山は奈良時代の聖武天皇の御宇、法華罪の駿河国分尼寺として建立されたといわれる」書いてある。
これを読んだ時は、国府の駿府から離れている焼津の、しかも山の中にある寺が国分尼寺? と疑問を
感じ調べてみると、曹洞宗静岡県第一宗務所青年会 のHPに
「当山は天台宗に属し、奈良時代第45代聖武天皇の御宇、法華滅罪の駿河国分尼寺として建立された」と
あった。その時は宗教家の団体が書いてあるのだから間違いないだろうと思ったいた。
だが今回菩提樹院も国分尼寺かもしれないと分かり、再度HPと案内板を読み返してみると、その文章の
内容も構成も殆ど同じだった。これはどちらかが引用したとも思われる。
更に、案内板が立っている場所は法華寺の境内ではなく、大分離れた場所の見晴台にあるのも不自然だ。
それに比べ、菩提樹院の案内板は
「養老5年、勅命により法相宗定額寺(国分寺や尼寺に次ぐ寺格の寺)北川辺に建立。その後、盛衰を繰り
返し、徳川家康公が駿府城を築くに際し、寺町(常盤公園)に移す。その後、静岡大火や静岡大空襲により
焼失するも、昭和20年の区画整理により移転した」(概略)
焼津の住民の私としては、法華寺が国分尼寺だとしたいが、どうも分が悪そうだ。
境内に入ると、今度は「伝 駿河国分寺の塔心礎」の案内板があった。これまた変な話で駿河の国分寺は
前回の百地蔵巡りの最後に寄った国分寺のはずだ。それなのに国分寺の礎石が旧国分尼寺の菩提樹院に
あるとは納得しがたい。だが静岡市の建てた案内板には
「昭和5年、駿府城内から発見され、国分尼寺の後身の伝承を持つ菩提樹院に寄進された。」となっている。
果たして本物と判定した国分寺の塔心礎を、単なる伝承を持つだけの寺院い寄進してしまうだろうか?
更に案内板には「34cmの直径の孔を穿った鑿の痕跡は、本来は寺院の心礎として用いられたもので、中央の
孔は舎利孔であったと考えられる。この舎利孔の大きさは、甲斐や伊豆の国分寺の物とほぼ同じである。」
この石が国分寺の塔心礎と判定されたのは、孔の大きさからだったようだ。
案内板はまだ続いていて、江戸時代には「孔を広げて駿府城内にあった社の手水鉢としていた」とも書いてある。
駿河国分寺は武田信玄の駿河進攻で焼払われたが、江戸時代の安永6年(1777)には、その国分寺跡に
「日本六拾六國於國分寺立之」の石塔が建てられている。それなのに同じ時代に国分寺跡から発掘された
この石を加工して、社の手水鉢として使っただろうか? 私には理解できない。
尤も案内板には、「伝 駿河国分寺の塔心礎」 と 「伝」 が付いてはいたが。


菩提樹院山門 「伝駿河国分寺の塔心礎」
菩提樹院の地図
菩提樹院には、まだ気になる物が有った。それは由比正雪の首塚だ。寺の案内板によると
「由比正雪は駿府宮ヶ崎の紺屋に生まれ、江戸へ出て楠流軍学を学んだあと、牛込に道場を構えて軍学を
指南した。時に、徳川幕府の悪政を改革せんと、幕府転覆を計り、自ら久能山に立て籠もり、東西の同志に
号令せんとしたが、事前に露見し、駿府梅屋町の旅籠梅屋に於いて、同志9名と共に自刃した。同志と共に
安倍川畔にさらし首になるが、縁者の女人が秘かにその首を盗み、寺町の菩提樹院へ葬った。それがこの
首塚で、寺の移転と同時に首塚も移転された。」
何も案内板にケチを付けるのが趣味ではないが、この案内板の「由比正雪は駿府宮ヶ崎の紺屋に生まれ」を
覚えていてください。百地蔵の遍路できっと「由比正雪の生家」の前を通るので ------
イヤー!ここにもさらし首を盗んだ女性がいた。静岡県内では江戸時代の大盗賊の一人、日本座衛門の首を
磐田見付の鈴ヶ森処刑場から盗んで、東海道の金谷宿に埋葬した女性がいたが、由比正雪にもそんな女性が
傍にいたのですね。 しかし、とまた妄想が湧いてくる。
さっきお詣りしてきた来迎院の「宮城野・信夫」の話を覚えていますか。あの二人の女性は由比正雪の恩に
報いるため、処刑場の近くに庵を建てて、正雪の菩提を生涯弔ったとあった。どうせ庵を建てるなら正雪の首が
葬られている菩提樹の首塚の近くに建てて、冥福を祈ればよいと思ってしまうのだが ------
アッ若しかして 正雪の首を盗んだのが女性だったので、宮城野と信夫は嫉妬心を感じていたのかな。


由比正雪の首塚 由比正雪の銅像
70番目(71番) 桃原寺
寺団地の中の5寺は簡単に済むと思っていたが、菩提樹院で思わぬ時間が掛かってしまった。先を急ごう。
谷津山は後ろに去り、右に日本平の丘が近づいてきた。午前中は東海道線の南側歩いたが今は北側を歩く。
今日最後の百地蔵は、この東海道線を渡り、今朝迷子になった東名高速を潜った日本平の中腹にある。
また東名のガードを潜るのかと、嫌な予感に捕らわれてが、案の定、潜った東名のガードと地図のガードが
違って迷子になってしまった。適当に見当を付けて日本平の中腹を目指して登っていたが、民家も無くなり
これ以上登ると畑や林ばかりになっていしまいそうだ。そんな時タイミングよく軽トラが登ってきた。
慌てて手を挙げ軽トラを止めて道を尋ねた。
「桃原寺なら、新しくできた、この道を真っ直ぐ行けば本堂に出ますよ」と。
付いているのか付いていないのか良く分からない。
桃原寺の百地蔵はHPによると「護国地蔵」とあったので、どんな地蔵像かと興味を持っていたが、境内には
それらしき地蔵像は見当たらなかった。本堂の柱には「駿河一国百地蔵第七十一番」の板が張ってあるので
間違いないのだが、きっと本堂の中に祀ってあるのだろう。
境内に「寛永20年(1643)徳川家康没後27年 三代将軍家光時代」と書かれた小さな案内板がついた地蔵尊が
あった。一先ずこの地蔵尊を百地蔵として良しとしておこう。


桃原寺参道 桃原寺の地蔵像
桃原寺の地図
今日の遍路は一日で30ヶ所も廻ってしまったが、矢張りこれでは多すぎる。余りに数が多すぎて前日に調査した
道も覚えきれず迷う事が多かった。マー反省はあるが残りは後30ヶ所。遍路もあと2回か3回で終わりそうだ。
先が見えてきて駅前で飲む乾杯の酒は美味しかった。
ブログの方も後15回も書けば終わりそうなので、予定通り今年中には終わる目途がついた。












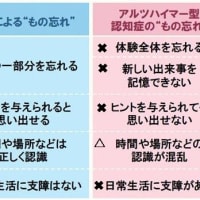




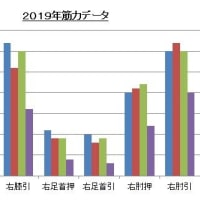
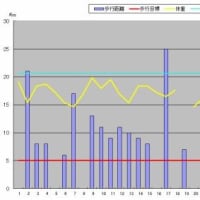
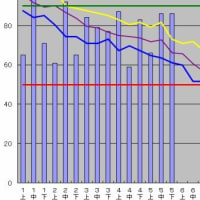
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます