《創られた賢治から愛すべき真実の賢治に》
「地上の賢治」の性向はさて、私から見れば「不羈奔放」だった「羅須地人協会時代」の賢治だが、当時の賢治の生身はもちろん地上を歩いていたわけで、それが「地上の賢治」である。つまり、「地上の賢治」とは、当時の賢治は地上をどのように歩き廻り、何を為し、何を為さなかったのかということや、どこで転びどこでまた立ち上がったのかとか、そしてそれ以前にそもそもその頃の賢治の「足元」はどうなっていたのかなどという、挫折や葛藤そして苦悩や悔恨などをも含む生身の賢治の総体のことである。そして、「天空の賢治」とは異なりこの「地上の賢治」には問題がある。
かつての私がそうだったし、世間一般にも同様の傾向があると思うのだが、賢治を聖人・君子かあるいはそれに近い人物だったと認識している人は少なくなかろう。どうも、同郷の石川啄木などとは違って神格化されている実態が賢治にはある。しかし、ここまで約10年間かけて実証的に私が考察してきた限りではどうやらそうとは言えず、それとはかけ離れていたり場合によっては真逆だあったりした場合も少なくなかった。よって、私が検証してみた限りでは、「地上の賢治」は聖人でもなければ君子でもない。
それは、このシリーズで次の「羅須地人協会時代の」における各項目
・突然の花巻農学校の辞め方にも
・高級蓄音機の購入からも
・白鳥省吾訪問ドタキャンにも?
・チェロの購入にも
・楽団の解散の仕方にも?
・「三か月間」の滞京にも(前編)
・「三か月間」の滞京にも(後編)
・農繁期の上京にも
・下根子桜からの撤退にも
をそれぞれ考察してきて見えたものが、これらを貫く棒の如き太い「不羈奔放」だったという賢治の性向であったことから導かれる帰結だった。この当時の賢治の際だったこの性向は、かつての私が抱いていた「羅須地人協会時代」の賢治、「己に対してはストイックで、貧しい農民のために献身した」賢治とは対極にあると言ってもよいものだった。・高級蓄音機の購入からも
・白鳥省吾訪問ドタキャンにも?
・チェロの購入にも
・楽団の解散の仕方にも?
・「三か月間」の滞京にも(前編)
・「三か月間」の滞京にも(後編)
・農繁期の上京にも
・下根子桜からの撤退にも
「地上の賢治」の農業実践はそれ程ではなかった
そして一方、
賢治はあまりにも聖人・君子化され過ぎてしまって、実は私はいろいろなことを知っているのだがそのようなことはおいそれとは喋られなくなってしまった。
という意味の賢治の甥である岩田純蔵氏(私の恩師)の嘆きを私は直に聞いている。そしてこの嘆きの意味は、ここまで述べてきた賢治の性向の面でも知ることができたのだが、それは「羅須地人協会時代」の農業実践の面においても同様にある。例えば、
私たちにはすぐに、一九二七年の冷温多雨の夏と一九二八年の四〇日の旱魃で、陸稲や野菜類が殆ど全滅した夏の賢治の行動がうかんでくる。当時の彼は、決して「ナミダヲナガシ」ただけではなかった。「オロオロアルキ」ばかりしてはいない。
という記述や 昭和二年は、五月に旱魃や低温が続き、六月は日照不足や大雨に祟られ未曾有の大凶作となった。この悲惨を目の当たりにした賢治は、草花のことなど忘れたかのように水田の肥料設計を指導するため農村巡りを始める。
そして、一九二七(昭和二)年は、多雨冷温の天候不順の夏だった。
というような記述に時々出会う。つまり「一九二七年の冷温多雨の夏」や「昭和二年は…六月は日照不足や大雨に祟られ未曾有の大凶作となった」などという断定表現にしばしば出会う。そしてたしかにその一部分(例えば「一九二八年の四〇日の旱魃で」)は事実である。
しかも、当時盛岡測候所長だった福井規矩三が「測候所と宮澤君」の中で、
昭和二年はまた非常な寒い氣候が續いて、ひどい凶作であつた。
<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)316p~>
と述べているから、前掲の引用文の内容は全てが歴史的事実と思われる。
そしてこれまたかつての私がそうだったし、世間一般の少なからぬ人々も同様だと思うのだが、
賢治は、この異変のなかを、文字通り東奔西走した。そして、ついに過労に倒れた。
と思い込んでいるのではなかろうか。なぜならば、上記のような書き方をした賢治関連の著作が世に横溢しているからである。ところが実は、この福井の証言は全くの事実誤認である。なぜならば、それこそ福井自身が発行している『岩手県気象年報(大正15年、昭和2年、昭和3年)』(岩手県盛岡・宮古測候所)も含めた当時の新聞報道や全ての客観的なデータがそれを全否定しているからである。したがって、前掲の引用文の内容は事実とはかなり乖離している。
どうやら、賢治の農業実践については、石井洋二郎学部長が平成27年度の卒業式の式辞で、
あやふやな情報がいったん真実の衣を着せられて世間に流布してしまうと、もはや誰も直接資料にあたって真偽のほどを確かめようとはしなくなります
と危惧していたとおりのことが「賢治関連」の場合にも起こっており、その裏付けも取らずに鵜呑みしたり、孫引きしたりして、ただ再生産しているだけだという論考等が少なくないと言わざるを得ないようだ。その結果、賢治の実践はそれ程ではないのにもかかわらず針小棒大に語られていることがしばしばあるということになりそうだ。それは何も私のみならず、吉本隆明がある座談会で、
日本の農本主義者というのは、あきらかにそれは、宮沢賢治が農民運動に手をふれかけてそしてへばって止めたという、そんなていどのものじゃなくて、もっと実践的にやったわけですし、また都会の思想的な知識人活動の面で言っても、宮沢賢治のやったことというのはいわば遊びごとみたいなものでしょう。「羅須地人協会」だって、やっては止めでおわってしまったし、彼の自給自足圏の構想というものはすぐアウトになってしまった。その点ではやはり単なる空想家の域を出ていないと言えますね。しかし、その思想圏は、どんな近代知識人よりもいいのです。
<『現代詩手帖 '63・6』(思潮社)18p >と語っているし、同じようなことを、それを間近に居て実際に見ていた羅須地人協会の隣人で会員でもあった伊藤忠一が、
協会で実際にやったことは、それほどのことでもなかったが、賢治さんのあの「構想」だけは全くたいしたもんだと思う。
<『私の賢治散歩 下巻』(菊池忠二著)35p >と言い残している。
しかも当の賢治自身も、この伊藤に宛てた書簡(258)の中で、
たびたび失礼なことも言ひましたが、殆んどあすこでははじめからおしまひまで病気(こころもからだも)みたいなもので何とも済みませんでした。
<『新校本宮澤賢治全集第十五巻書簡 本文篇』(筑摩書房)>と「羅須地人協会時代」のことを厳しく自己総括して自省し、伊藤に詫びている。
したがって、賢治を含むこの三人の「羅須地人協会」の賢治の農業実践に対しての評価はほぼ一致していると言えるのだから、この賢治の心情の吐露を私たちはもっと重く受け止めかつ素直に耳を傾け、そして冷静に評価すべきだと思う。もうそろそろ、
賢治自身は「羅須地人協会時代」に米を作ったわけでもないことから明らかなように、下根子桜に移り住んだ主たる目的は本物の百姓になろうとしたためだったというわけではないし、また、「羅須地人協会時代」に貧しい農民たちのために為した稲作指導の実践はそれ程のものでもなかった。
という事実を私たちは受け容れてもよい時機ではなかろうか。賢治は農業実践の面でも吉本等も言うとおりで、聖人などではない(すなわち聖農でもない。例えばそれは、隣の県の聖農石川理紀之助と比べてみれば直ぐわかる)のだと。 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 〝『「不羈奔放」だった地上の賢治』の目次〟へ。
〝『「不羈奔放」だった地上の賢治』の目次〟へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》
◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。
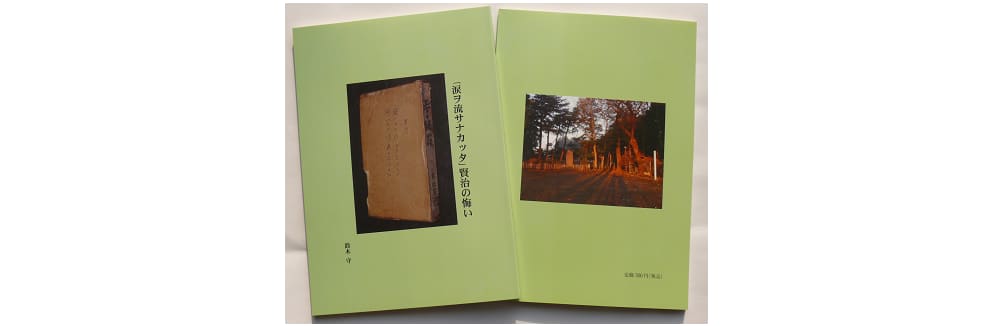
本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。
あるいは、次の方法でもご購入いただけます。
まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。
◇ 現在、拙ブログ〝検証「羅須地人協会時代」〟において、以下のように、各書の中身をそのまま公開しての連載中です。
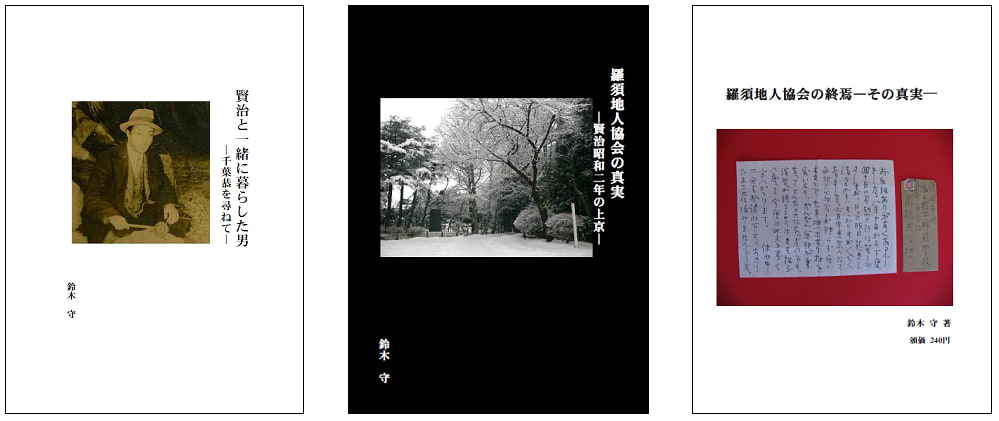
『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』 『羅須地人協会の終焉-その真実-』
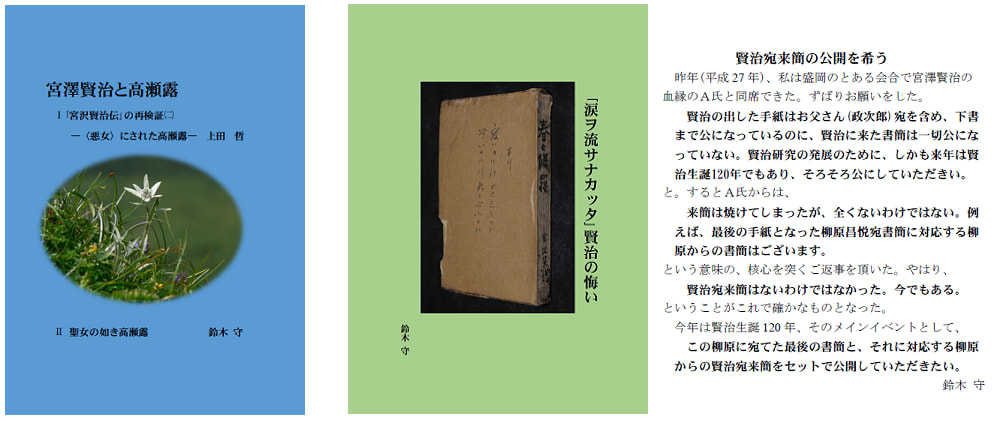
『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) 『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』


























いつもいつも失敬な物言いばかり続けてイタミイって居りまする。
先ず始めに明らめておきたいことは、小生の〈言語ゲーム(語用行為)〉は、「無礼なる非難(ブレイム)」などではなく「新しい疑問と肯定を発掘する手段・方法としての現状否定的なる言語表現行為(言語ゲーム)」としての〈批判(クリティーク)〉ののだということです。 例えば、昨年暮れ、三十年ぶりかでお会いし、例の遠野高校蔵書である国書についてだとか、カント哲学だとかウィトゲンシュタイン哲学だとかについて語りあった佐野茂樹先生がドイツ語で取り組んだE・カントの道うところの〈純粋理性批判〉やら〈実践理性批判〉という道取語用の文脈での〈批判〉です。 「批判と非難とをベイグ(ごたまぜ性あいまい)化していることを自覚できない無明」の徒輩は、『あいまいな日本の私 ― ベイグではなくアムビギュアスな』―』という〈九条の会〉発起人の道得を、〈非国民〉〈国賊〉〈売国奴〉といった忌まわしい誹謗中傷語で非難していたように観じられたのでした。 現在、朝日新聞に『おりおりのことば』というコラムを連載している鷲田清一氏もその思想の土台にしているのM・メルロー=ポンティの〈両義性の哲学〉を一大事と作し、「漱石もアムビギュアスな思索者だったと考えています。」と書いていた大江氏の「滅茶苦茶(ベイグ)ではなくアムビギュアス(両義的)な」という補足説明には目もくれず、自派の主張のみを〈真善美〉と為し、それに対立する見解を〈偽悪醜〉と決めつけ差別抑圧排除弾圧することを正義と決め込んでしまう心身態度や如何、と。 慥かに、二項対立思考あるいは二値論理思考は、〈オトナの思考〉なのですが、果たして〈タイジンの思惟思索思量〉と道えるだろうか、と。カントの〈純粋理性批判〉は〈アンチノミー(二律背反)〉という難題に遭遇し、〈人間理性の限界〉に悩んだ思量の所産だったのではないでしょうか。「ヘーゲルのディアレクティーフ」「フッサールのフェノメノン(現象)の哲学」「L・ウィトゲンシュタインの論理哲学論考と言語ゲームとの相補相依性」「メルロ・ポンティの身心知覚と両義性の哲学」などなどの視野は、漱石や稲造の眼を介して禅哲学や老荘哲学にまで遡り得るのではないかしらん、などと夢想を始めたのは白堊校校から釜南に移ったころからのことでした。そして、大志高の水源に遊び始めた時節と、例の自由主義史観やらネオリベラリズムやらリヴァタリアニズムの一斉風靡が。自由競争おおいに結構、弱肉強食は生物界の習い、差別格差の発生は自由主義の帰結なるべい、などと。 正に、「自由の両義性」、「自由競争の両義性」、「理性の両義性」、「知性の両義性」どころか「全てのノ廼ごとモノゴトの裏に両義性が蔵されているのだ」、と。 尚、〈両義性(アムビギュイティ)〉という語の広義は〈多義性〉。辞書をめくり始めて最初に戸惑わされるのは、「凡ゆる語彙が多義性をもっている。」という言語意味生成現象のという現実。「大きな辞書を調べれば調べるほどワケガワカラナクナル」という体験は、「好く知ろうとして本を読めば読むほどナニガナンダカ……」という〈あいまいさへの遭遇〉は、向学心を持っている身心なら誰でもが否応なく経験することにちd違いありません。而して、「自分で考ようとする心」が否応なく逢着するのが〈自己矛盾・自家撞着〉という病、なのではないでしょうか。「自ら考え迷う惑い悩み彷徨う道」に逸脱しないためには、「自ら考えることは放棄して強力な権威や権力を盲信し追従するという路」を突っ走れば、……。 固より、左様な路は、〈智慧の実苹果のシグナレスの声〉を聞かせてくれる経路ではないと思量いたすのですが。何しろモーレツだったですからね。〈パーソナリティディスオーダー〉、キョービ流で云えば〈メンへレ〉とか謂うんですかしらん。〈境界線上を踊るヤマイ〉というのは精神科医をさえ巻き込んでしまうリスクがあるというからタイヘンです。 おっと、ハナシが脱線してしまいました。メルロ・ポンティ流の〈アムビギュイテ(仏語)〉とは、言語意味生成や事物や人物などなどに内蔵されている〈アムビ(両極性・双面背反性)〉を認め対自し多面的に詞作思索しようとする身心態度」 のことと、ガンぢ岩大教養部時代に倫理の授業を受けた滝浦静雄氏(東北大教授)が翻訳した『眼と精神』などを読むうちに心惹かれた考えk多方でした。「考え過ぎ症候群に罹り優柔不断で決断できない心気症底シンドローム」に懊悩していた「三十而未立者「」にとってはどれほどの救いになったでしょうか。高校時代から詩人として慣らしており、明治大で仏文とフランス哲学を学んでいた城戸朱理と対等な対話が出来たのはポンティとウィトゲンシュタインだけだったことを未だに覚えています。 小生が〈自称霊魂病者稲造〉とその成立学舎英語学校での教え子〈自称神経衰弱者漱石〉に深い共感を覚えているのは、「同郷の近代日本最良のコスモポリタン」だからでもなく、「大文豪」だからというよりは、「迷い悩みノイローゼで自死も考えたこともあることを公けにしている一個人」だからですし、十九歳で、「我は脳病者なるべし」と歌った賢治 ― なにのため,ものをくふらん,そらは熱病,馬にほふられわれは脳病. 目は紅く,関節多き動物が,藻のごとく群れて脳をはねあるく ― が、二十歳に至って、「 風きたり、高鳴るものはやまならし、またはこやなぎ,さとりのねがひ.「」と詠った賢治なのでした。〈やまならし〉〈はこやなぎ〉の別名は〈白楊〉〈どろの木〉そして〈ギンドロ〉ですね。つまり、〈銀楊のメタファー〉は〈覚悟(さとり)〉。問題は、世間一般者や賢治ファンにとってではなく、「賢治自身にとっての〈さとり〉とは如何なるか?」、と。 で、この難有い問題は、賢治周辺の人々や、賢治研究の権威に如何ほどに問い質してみても謎のままであり続けざるを得ないということ。 賢治自身の「父母未生以前本来の面目」を垣間見る手立ては、〈賢治道得〉つまり〈賢治テクスト〉を読み込む試みしか、…。しかしながら、〈賢治ボキャり―ブラリ―〉や〈賢治レトリック〉は自前造語スキゾフレニ アなみにチンプンカンプン。漱石の語用もかなりの程度に難解で、初読時には語注と首っ引きになる必要が生じますが、賢治の場合はか分厚い『宮澤賢治語彙辞典』を矯めつ眇めつしても埒があかないのが而xty歳実際でしょう。賢治研究の雄、入沢翁が、「私は伝記的な問題には立ち入りません」と明言しているのも宜なるかな。
譬えば、〈流石漱送籍者漱石〉に就いて道うならば、小生は、『坊つちやん』での〈漱石の分身〉は、俗説流の〈坊っちやん〉などではなく『私の個人主義』で金之助自身が語っているように〈赤シャツ〉なのだと読んで楽しんでいます(そう読むと話がコンプレックス化して愉快至極に)し、根も『吾輩は猫である』での送籍分身は〈吾輩猫〉 に他ならない、と。では、〈珍野苦沙弥〉は誰のエージェントなるか、といえば。「妻子を養う為に嫌い(?)な教師業で金を稼ぎ、時勢とその行く末に腹を立て、神経衰弱と酷い胃潰瘍に悩まされ、癇癪発作を止められず、時には妻子にたいしてドメスティックヴァイオレンスを振るっていたか世俗生活者夏目金之助」、ということで。 シリキレですが、長くなったのでまた。
2016,3,1 15:48 文遊理道樂遊民洞のホザク
ついに、四年ぶりの二十九日が過ぎて白鳥も北帰行の弥生三月に。新書斎の窓からはキタエ北へ帰るVi字型が頻繁です。あとどれほどの有時経歴を。
お早うございます。
そうですか、昨年末佐野先生にお会いになったのですね。
佐野先生といえば、あの透徹した視線に豊かな知性とぶれない良心を私はいつも感じておりました。東日本大震災での罹災もあってご苦労なさっておられるやに承っておりますが、お元気でいらっしゃいましたか。
さて、その他のことに関しましては芋虫の眼にはやはり難しすぎますので承ってだけおきますが、
入沢翁が、「私は伝記的な問題には立ち入りません」と明言しているのも宜なるかな。
に関してだけ、私が感ずるところを今回少し述べたいと思います。
まず、私も基本的には「宜なるかな」と思います。ただし、それはあくまでも入沢先生の場合にはという限定付きですが。
といいますのは、基本的には「作品」と「作家」とは別個のものだと思いますし、「作品」ができた時点でそれはそれで独り歩きできるものだと思うからです。
ただしその際に二つの問題点があると思います。まず一つ目は、そうはいいつつも実はどうしてもその作品の理解を深めたいということになればどうしてもそれを生み出した人のことを知りたくなるということが不可避だと私には思えるからです。そして実際そうしている人は少なくないはずです。
そして二つ目は、私から言わせてもらえば、賢治のいわゆる「作品」には実は「作品でない」ものが多いということです。もう少し具体的に申しますと、賢治のいわゆる「作品」の中には、いくつかのものは生前既に公になっていたり、あるいは「定稿」 としていたものがあるからそれらは「作品」と言えると思うのですが、下書稿であったものを後に賢治以外の人たちがああでもないこうでもないと苦労しながら手を加えて賢治作品として世に送り出したものも少なからずあると思うのですが、私はそれらを賢治の作品としては純粋には受け容れ難いのです。端的に言えば「下書稿」はその作家の「作品」とは言い切れないと思っているのです。下書稿はあくまでの草稿であり、それがその作者によって完成されてこそはじめてその作者の作品になると思うのです。
それにしても、これだけ下書稿のことをああでもないこうでもないと「矯めつ眇めつ」されている作家は他にいないと思います。もちろんそれは、「賢治研究」という立場からは当然のことだと思いますが、ちょっとガラパゴス化し過ぎているのではなかろうかということも私は危惧ぐしております。また一方で、下書をあれこれ吟味することと「伝記的な問題」を追求することとはそれ程の大きな違いはないとも思っております。
ところで、さきほどの「限定付き」を外せば、「伝記的な問題」 は今まさに取り上げられなければならないと思います。それは、一年前の東大教養学部の卒業式における石井学部長の式辞がまさに指摘していることに対応する、「賢治研究」における喫緊の課題だと私は思っているからです。
この石井学部長の式辞の内容を知ってしまうと、「伝記的な問題には立ち入りません」という入沢先生の立場とは違ってしまいますが、賢治研究家の全てがそうあるべきだとは私にはどうしても思えません。逆に、少なくとも伝記的な問題に立ち入る賢治研究家の出現が今俟たれていると思います。
鈴木 守