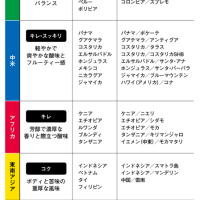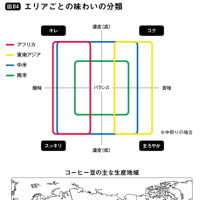芸術作品とは、仲介者なしでそれと一対一で向き合い、作者が表現しようとしたことを虚心に受け止めるべきものだと感じたのである。作者との一対一の関係に慣れるには、何よりもできる限り多くの傑作を自分の眼でじかに見ることが重要だ。
土地は持っていないが、頭脳は持っている人々が集まって作ったのが都市国家です。都市とはイコール頭脳集団、と言ってよいくらい。それまでの「ノーヴィレ」(貴族)な血筋の問題であったのが、「血がノーヴィレを決めるのではなく、精神の高貴さが決める」ように変わってくる。所有する土地の広さと何代も昔にまでたどれる血統い代わって、才能の豊かさと気力の強さが、人間の評価の基準になっていったのです。
肌で知っているだけでは、彼個人の智慧にはなっても他者もふくめての共有財産にはならない。科学的に探究しその結果を言語を通して公のものにしてはじめて、実地に経験したことのない人でも共有が可能な智慧になるのです。
原語には、他者への伝達の手段としてだけではなく、原語を使って表現していく過程で自然に生まれる、自分自身の思考を明快にするという働きもある。明晰で論理的に話掛けるようになれば、頭脳のほうも明晰に論理的になるのです。つまり、思考と表現は、同一線上にあってしかも相互に働きかける関係にもあるということ。また、流れがこのように変われば、自分の眼で見、自分の頭で考え、自分の言葉で話し書く魅力に目覚めるのも当然の帰結です。神を通して見、神の意に沿って考え、聖書の言葉で話し書いていた中世を思い起こせば、ルネサンスとは「人間の発見」であったとすルブルクハルトの考察は正しい。
人口の激減とは、やむをえずにしろ人々の関心を効率性に向けざるを得なくする。それ以前は都市に流れ込んでくる人の量を頼りに上昇していたフィレンツエ経済も、ベスト以後は、質を重視し個々の生産性の向上を期すやり方に変わっている。(中略)1348年から49年にかけてのペストの大流行は、経済大国になりつつあったイタリアの都市国家に、経済構造の再構築を強いたのではないかと思うくらいです。
宗教とは信ずることであり、哲学は疑うことです。唯一の原理の探求も、哲学では原理の樹立と破壊を繰り返し行うことによってなされるものであって、いったん打ち立てた原理を神聖不可侵なものとして堅持しつづけることでなるものではない。哲学とはギリシャ哲学につきると言ったのは、ギリシャ時代は多神教の世界だったので、神聖にして不可侵としなければ成り立たない、一神教の規制を受けないで済んだからですよ。
文化の想像とは、いかに優れた資質に恵まれていても、純粋培養ではできないのです。異分子の混入による刺激が、どうしても必要になる。
このルネサンスが現代の我々に遺した遺産を総括するとすれば、まず第一は現代人が肉体の眼でも見ることができる芸術品の数々。遺産の第二は、精神の独立に対する強烈な執着。言い換えれば、自分の眼で見、自分の頭で考え、自分の言葉ないし手で表現することによって他者に伝える生き方です。遺産の第三は、二元論ではなく一元論的な考え方。(中略)古代ギリシャやローマでは、多神教であった事情から神さえも善と悪の双方をともにもつ存在とされていました。それが人間となればなおのこと、自分の内に善と書くの双方を持っている。となると、悪を抑えて善をより多く発揮させながら生きるにはどうすればよいか、がj」最重要な課題になる。この古代を復興したルネサンスでは、当然ながら人間が中心にならざるをえない。善悪ともを撃ちにかかえる人間が中心になれば悪は他人の粉うことで自分は知ったことではない、などどは言えなくなります。悪もまた我にあり、なんです。」ただしこれは、自己コントロールを求められるおいうことですから、精神も強靭でなければならず、ルネサンスとは精神のエリートたちによる運動であったと言えるかもしれません。
戦後の日本文学には、松本清張、司馬遼太郎、藤沢周平という流れがあります。松本清張は、戦後の下層階級の孤児のような存在を描いてきた。孤児が成り上がっていくプロセスの中での犯罪というのを取り上げた。そのことによって、戦後の混乱した占領期から高度経済成長期に至る時期をうまく捉えた。日本が高度経済成長に乗った段階で、経営者、管理者、指導者がモデルとすべき存在を歴史上に求めて書いたのが司馬遼太郎。そのあと、中間管理職の悲哀を江戸時代に仮託して書いたのが藤沢周平です。
総司令官は一兵卒までが働いてくれないと絶対に戦闘で勝てないので、一兵卒の気持ちまで把握しているものです。食の心配までする。だけど、中間管理職の場合は、自分は上から任命されのあで、上にばかり目がいく。それは当然なんです。だから、下に目が届かないということを非難しても、その避難は人間の本性からして適切ではないと思います。
土地は持っていないが、頭脳は持っている人々が集まって作ったのが都市国家です。都市とはイコール頭脳集団、と言ってよいくらい。それまでの「ノーヴィレ」(貴族)な血筋の問題であったのが、「血がノーヴィレを決めるのではなく、精神の高貴さが決める」ように変わってくる。所有する土地の広さと何代も昔にまでたどれる血統い代わって、才能の豊かさと気力の強さが、人間の評価の基準になっていったのです。
肌で知っているだけでは、彼個人の智慧にはなっても他者もふくめての共有財産にはならない。科学的に探究しその結果を言語を通して公のものにしてはじめて、実地に経験したことのない人でも共有が可能な智慧になるのです。
原語には、他者への伝達の手段としてだけではなく、原語を使って表現していく過程で自然に生まれる、自分自身の思考を明快にするという働きもある。明晰で論理的に話掛けるようになれば、頭脳のほうも明晰に論理的になるのです。つまり、思考と表現は、同一線上にあってしかも相互に働きかける関係にもあるということ。また、流れがこのように変われば、自分の眼で見、自分の頭で考え、自分の言葉で話し書く魅力に目覚めるのも当然の帰結です。神を通して見、神の意に沿って考え、聖書の言葉で話し書いていた中世を思い起こせば、ルネサンスとは「人間の発見」であったとすルブルクハルトの考察は正しい。
人口の激減とは、やむをえずにしろ人々の関心を効率性に向けざるを得なくする。それ以前は都市に流れ込んでくる人の量を頼りに上昇していたフィレンツエ経済も、ベスト以後は、質を重視し個々の生産性の向上を期すやり方に変わっている。(中略)1348年から49年にかけてのペストの大流行は、経済大国になりつつあったイタリアの都市国家に、経済構造の再構築を強いたのではないかと思うくらいです。
宗教とは信ずることであり、哲学は疑うことです。唯一の原理の探求も、哲学では原理の樹立と破壊を繰り返し行うことによってなされるものであって、いったん打ち立てた原理を神聖不可侵なものとして堅持しつづけることでなるものではない。哲学とはギリシャ哲学につきると言ったのは、ギリシャ時代は多神教の世界だったので、神聖にして不可侵としなければ成り立たない、一神教の規制を受けないで済んだからですよ。
文化の想像とは、いかに優れた資質に恵まれていても、純粋培養ではできないのです。異分子の混入による刺激が、どうしても必要になる。
このルネサンスが現代の我々に遺した遺産を総括するとすれば、まず第一は現代人が肉体の眼でも見ることができる芸術品の数々。遺産の第二は、精神の独立に対する強烈な執着。言い換えれば、自分の眼で見、自分の頭で考え、自分の言葉ないし手で表現することによって他者に伝える生き方です。遺産の第三は、二元論ではなく一元論的な考え方。(中略)古代ギリシャやローマでは、多神教であった事情から神さえも善と悪の双方をともにもつ存在とされていました。それが人間となればなおのこと、自分の内に善と書くの双方を持っている。となると、悪を抑えて善をより多く発揮させながら生きるにはどうすればよいか、がj」最重要な課題になる。この古代を復興したルネサンスでは、当然ながら人間が中心にならざるをえない。善悪ともを撃ちにかかえる人間が中心になれば悪は他人の粉うことで自分は知ったことではない、などどは言えなくなります。悪もまた我にあり、なんです。」ただしこれは、自己コントロールを求められるおいうことですから、精神も強靭でなければならず、ルネサンスとは精神のエリートたちによる運動であったと言えるかもしれません。
戦後の日本文学には、松本清張、司馬遼太郎、藤沢周平という流れがあります。松本清張は、戦後の下層階級の孤児のような存在を描いてきた。孤児が成り上がっていくプロセスの中での犯罪というのを取り上げた。そのことによって、戦後の混乱した占領期から高度経済成長期に至る時期をうまく捉えた。日本が高度経済成長に乗った段階で、経営者、管理者、指導者がモデルとすべき存在を歴史上に求めて書いたのが司馬遼太郎。そのあと、中間管理職の悲哀を江戸時代に仮託して書いたのが藤沢周平です。
総司令官は一兵卒までが働いてくれないと絶対に戦闘で勝てないので、一兵卒の気持ちまで把握しているものです。食の心配までする。だけど、中間管理職の場合は、自分は上から任命されのあで、上にばかり目がいく。それは当然なんです。だから、下に目が届かないということを非難しても、その避難は人間の本性からして適切ではないと思います。