みなさま、おはようございます。海風おねいさんです。
昨夜はなんとかお天気が持ってよかったですね。
盆踊り最終日、楽しまれましたか?
このところ、観光で島へいらっしゃる方々とお話しする機会の多いおねいさんです。
よく言われるのが、 「島料理をもっと載せてほしい
「島料理をもっと載せてほしい
 」
」
了解いたしました。今日はリクエストにお答えいたします。

島料理の新カテゴリも作りました。
リクエストがあれば、どんどんブログに反映していきたいと思います。

「ぶどの蟹寄せ」
これは贅沢なお料理です。
タラバ蟹を焼いた身をほぐして、島の特産品、「ぶど」で寄せています。
「ぶど」は、八丈島独特の海草です。
赤っぽい海草を煮ると緑に変色し、煮溶かして固めると寒天のようになります。
色と香りの強い寒天=天草に似たものと思っていただけるとわかりやすいですね。
以前に三宅島の方とお話したときに、「ぶど」を初めて見た、とおっしゃった。
三宅島には「ぶど」はないのでしょうか?また他の伊豆諸島ではどうでしょう?
ご存知の方がいたら、教えてくださいね。
九州に「おきうと」という似たような海草のお料理があります。
わたしは以前に「ぶど」の語源を知りたくて、少し調べたのですが、
九州のおきうとには、「沖人(おきうど)」=海から来た人が伝えたという説があり、
ひょっとしたら「おきうど」が変形して訛り、「ぶど」になったのかもと思いました。
「ぶど」の語源も知ってらっしゃる方がいらしたら、ぜひ教えてくださいませ。
作り方は、基本的には「ところてん」と同じです。
違うのは、少々具材を入れて味をつけるところでしょうか。
味付けは、八丈島内でも地区や家庭によってそれぞれ違うのです。
塩や醤油だけで味をつける方もいれば、味噌や化学調味料を入れる方もいます。
具材は、島の貝や飛魚の身をほぐして入れるのが一般的でしたが、
今は、ツナ缶やサバの水煮缶などで代用することも多い。
今日は、お客様用に、蟹をフンパツいたしました。

ぶど断面(溶き玉子入り)
これは、溶き卵を流した「ぶど」の断面です。
黄色のマーブルになって、きれいですよね。
以前に島の奥様に教えていただきました。

法事の持ち膳の「ぶど」
島では、法事の持ち膳などにもこの「ぶど」が入ってます。
いかにも精進ぽいお料理ですし、島の人はみんな「ぶど」が大好きなんですよ。

「ぶど」を冷やし固めているところです。
バットなどに流し、氷で荒熱をとったら、冷蔵庫で冷やし固めます。

海草を煮溶かして味をつけ、具財を混ぜ込んで冷やし固めるだけですから、
教えれば子どもでも作れる簡単なお料理です。
これは以前に小学校の授業で作った「ぶど」です。

これは、「ぶど」の海草を洗い、ゴミなどを取り除き、
さっと煮て途中で冷やし固めておいたものです。
ここまで下ごしらえして冷凍しておくと、いざ使うときに、とても便利です。
これに水を足して火にかけ、煮溶かしていくわけです。
煮る時間は、20分ほどでしょうか。
島の「ぶど」をご紹介しました。
昨夜はなんとかお天気が持ってよかったですね。

盆踊り最終日、楽しまれましたか?

このところ、観光で島へいらっしゃる方々とお話しする機会の多いおねいさんです。
よく言われるのが、
 「島料理をもっと載せてほしい
「島料理をもっと載せてほしい
 」
」了解いたしました。今日はリクエストにお答えいたします。


島料理の新カテゴリも作りました。

リクエストがあれば、どんどんブログに反映していきたいと思います。

「ぶどの蟹寄せ」
これは贅沢なお料理です。
タラバ蟹を焼いた身をほぐして、島の特産品、「ぶど」で寄せています。
「ぶど」は、八丈島独特の海草です。
赤っぽい海草を煮ると緑に変色し、煮溶かして固めると寒天のようになります。
色と香りの強い寒天=天草に似たものと思っていただけるとわかりやすいですね。
以前に三宅島の方とお話したときに、「ぶど」を初めて見た、とおっしゃった。
三宅島には「ぶど」はないのでしょうか?また他の伊豆諸島ではどうでしょう?
ご存知の方がいたら、教えてくださいね。
九州に「おきうと」という似たような海草のお料理があります。
わたしは以前に「ぶど」の語源を知りたくて、少し調べたのですが、
九州のおきうとには、「沖人(おきうど)」=海から来た人が伝えたという説があり、
ひょっとしたら「おきうど」が変形して訛り、「ぶど」になったのかもと思いました。
「ぶど」の語源も知ってらっしゃる方がいらしたら、ぜひ教えてくださいませ。

作り方は、基本的には「ところてん」と同じです。
違うのは、少々具材を入れて味をつけるところでしょうか。
味付けは、八丈島内でも地区や家庭によってそれぞれ違うのです。
塩や醤油だけで味をつける方もいれば、味噌や化学調味料を入れる方もいます。
具材は、島の貝や飛魚の身をほぐして入れるのが一般的でしたが、
今は、ツナ缶やサバの水煮缶などで代用することも多い。
今日は、お客様用に、蟹をフンパツいたしました。


ぶど断面(溶き玉子入り)
これは、溶き卵を流した「ぶど」の断面です。
黄色のマーブルになって、きれいですよね。
以前に島の奥様に教えていただきました。

法事の持ち膳の「ぶど」
島では、法事の持ち膳などにもこの「ぶど」が入ってます。
いかにも精進ぽいお料理ですし、島の人はみんな「ぶど」が大好きなんですよ。

「ぶど」を冷やし固めているところです。
バットなどに流し、氷で荒熱をとったら、冷蔵庫で冷やし固めます。

海草を煮溶かして味をつけ、具財を混ぜ込んで冷やし固めるだけですから、
教えれば子どもでも作れる簡単なお料理です。
これは以前に小学校の授業で作った「ぶど」です。

これは、「ぶど」の海草を洗い、ゴミなどを取り除き、
さっと煮て途中で冷やし固めておいたものです。
ここまで下ごしらえして冷凍しておくと、いざ使うときに、とても便利です。
これに水を足して火にかけ、煮溶かしていくわけです。
煮る時間は、20分ほどでしょうか。
島の「ぶど」をご紹介しました。





















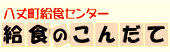





わたしは地方料理に非常に興味があるので、
東京在住の頃には、博多料理のお店にもよく行きました。
おきうとは、つるりとした、蒟蒻に近い食感ですが、
ぶどは、もっとざらりとして、海草くさいです。
海草に直接調味するので、なにも付けずに、そのままいただきます。
これは調理法の違いで、ぶどももっとよく煮てから漉したら、
おきうとに近いかんじになるかもしれません。
おきうとの原材料をぜひ見てみたいです。
博多だけでなく、新潟にも「えご」「えご海苔」と呼ばれる
似たような海草のにこごり料理があるそうですよ。
以前に新潟の方から教えていただきました。
話を聞くと、こちらの方が「ぶど」に近そうですが、
「おきうと」の方が一般的に有名なので、
ここでは「おきうと」と比較して取り上げました。
八丈島はその昔、長く流人の島であったので、
各地のいろんな文化が入り込んでいますが、
特に九州地方からは、さつま芋や焼酎の製法など、
伝わっているものが多いのです。
そんなこともあって、「おきうど」→「うど」→「ぶど」と変化したのかしら?
などと考えてみました。
ダイナミックに八丈島料理の紹介ですね!!
スーパーあさぬま発信でお役立ちですね!!
転勤してきた方の奥様方にも
相当の情報になると思います。
「ぶど」を食べたことも見たこともない方が結構いらっしゃる。
少しめずらしいところで…と思い、ご紹介してみました。
「ぶど」は各家庭の味がいろいろあるのが楽しいところ。
島内の方々にも多少でも参考になれば嬉しいです。
これ作ってみたい。。
教えてくれてありがとう。
本当に、すばらしい!
島のよさがガンガン、伝わってきます。
これからも張りきって、島の素晴らしい郷土料理を紹介していくわね。
刻々とそちらでの滞在時間が短くなりますね。
ホームシックもあるでしょうけど、
みきちゃんはオランダ料理をいっぱい覚えて、
帰ってきたら、わたしに教えてね。
そちらも期待してますので、忘れないでね。
一度でいいから食べたいデス!!!!!
どんな味がするのか楽しみです!
ブドは海藻の香りの強いとてもヘルシーなお味のお料理です。
ブドを食べに八丈島へ遊びに来てくださいね。
ぶどではアリマシェンカ!
一度食べたかったんですよ!
今度作ってみます!
味付けは各家庭で違うので、ここには載せていませんが、
ぜひオリジナルなブド作りに挑戦なさってみてくださいね。