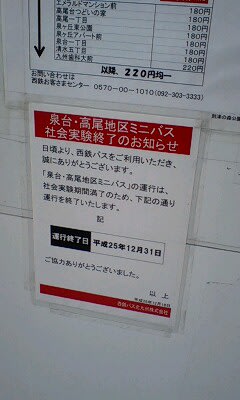(つづき)
「営団入口」。
北九州地区の“KITAKYUSHU CULTURE AND SCIENCE MUSEUM FOR YOUTH”、“INTERNATIONAL VILLAGE CENTER”、“YAHATA EAST FIRE STATION”、“YAHATA SEITETSUSHO SYNTHESIS CENTER”、“THREE-WAY INTERSECTION”…のような表記を見てきているので、“CORPORATION ENTRANCE”のような表記も期待してしまうのだが、ここは“EIDAN ENTRANCE”。
なお、ここでいう「営団」という組織自体は70年以上前になくなっている。
当然、なくなったときのことはリアルタイムでは知らないのですが。
(つづく)
(つづき)
「桜丘第一」。
英字表記は“SAKURAGAOKA DAIICHI”で、「一」も“ICHI”となっていて、完全な読み重視のパターン。
ちなみにこちらは、戸畑に行くといつも目に飛び込んでくる“Aso 1-go Park”。
誰のための英字表記なのかがいまいちよくわからないパターン。
ワン・ゴー・パーク、犬が飛び回っているドッグラン的な公園が思い浮かぶ。
「桜ケ丘」から「桜丘」表記に変わったのは2011年春。
町名の表記が変わった訳ではなく、もとから一致していなかった表記を合わせただけ。
桜丘地区の中では、第一~第五は、標高の低さの順番でもあります。
なお、北九州地区だと、地名の後ではなく、地名の前に「第○」が付くケースも多い。

現在の本数と経路(都心方面)。
1993年、1995年、1996年当時の本数や、ここから南福岡駅に向かう路線については過去の記事を参照。
「外環3番」用の「桜丘第一」は、現在のバス道路と交差する広い道路上への設置を想定しておりました(笑)。
(つづく)
(つづき)
「四箇田団地」の下に“Shikata housing estate”。

こっちには“Murozumi housing estate”も。
ここは「藤崎バス乗継ターミナル」。
以前から、ここでは「団地」を“housing estate”と表現している。
「住宅団地」「工場団地」「流通施設団地」「産業団地」…など、本来は団地にもいろいろあるのだが、その中の「住宅団地」のことを主に「団地」と呼ぶことが定着しているし、四箇田団地も室住団地も、工場や流通施設ではなく住宅なので、ハウジングエステートでよいのだろうけど、なんか仰々しい感じも。

他も、全体的に「意味重視」で書かれているが、「営業所」は“Eigyosho”だったりする。

こちらは「天神三丁目」での表示。
天神地区のバステラス(←新型のバスシェルターのこと。「バステラス」は、公募で決まった愛称なのですが、そう呼んでいる人はあまり多くないかも)では、表現方法がちゃんとしているということを以前書いたのだが、ここは、「四箇田」「室住」とだけ書くことで、「団地」を訳すことを回避しているようにも見える。
(つづく)
「四箇田団地」の下に“Shikata housing estate”。

こっちには“Murozumi housing estate”も。
ここは「藤崎バス乗継ターミナル」。
以前から、ここでは「団地」を“housing estate”と表現している。
「住宅団地」「工場団地」「流通施設団地」「産業団地」…など、本来は団地にもいろいろあるのだが、その中の「住宅団地」のことを主に「団地」と呼ぶことが定着しているし、四箇田団地も室住団地も、工場や流通施設ではなく住宅なので、ハウジングエステートでよいのだろうけど、なんか仰々しい感じも。

他も、全体的に「意味重視」で書かれているが、「営業所」は“Eigyosho”だったりする。

こちらは「天神三丁目」での表示。
天神地区のバステラス(←新型のバスシェルターのこと。「バステラス」は、公募で決まった愛称なのですが、そう呼んでいる人はあまり多くないかも)では、表現方法がちゃんとしているということを以前書いたのだが、ここは、「四箇田」「室住」とだけ書くことで、「団地」を訳すことを回避しているようにも見える。
(つづく)
(つづき)
上部の「○○方面」のところは、“Fukuoka Tower”“Noko Ferry Port”“Hakata Pier”と、「意味重視」で、
その下の「次は」のところは、“SHIMIN KAKIKAN-MAE”“RYOJIKAN-MAE”と「読み重視」。
「意味」と「読み」が混在していることを批判したいわけではなく、個人的には、むしろ理に適っていると思います。
“施設名の入ったバス停は、「その施設に行く人がいるから」施設名が入っている場合と、「ただそこに施設があるから」施設名が入っている場合の二つに分けることができそうであり、「長尾変電所前」はおそらく後者に属するのだと思う”
と、8年半前の「長尾変電所前」の記事で書いたのだが、これに当てはめると、「○○方面」では、「その施設に行く人がいるから」という観点を重視すべき、という考えが成り立つと言えそう。
それにしてもここは、ボートレースから警察署、領事館まで、多様な“Next stop”を持つバス停であり、「DWK」もそこそこ高い。
(つづく)
上部の「○○方面」のところは、“Fukuoka Tower”“Noko Ferry Port”“Hakata Pier”と、「意味重視」で、
その下の「次は」のところは、“SHIMIN KAKIKAN-MAE”“RYOJIKAN-MAE”と「読み重視」。
「意味」と「読み」が混在していることを批判したいわけではなく、個人的には、むしろ理に適っていると思います。
“施設名の入ったバス停は、「その施設に行く人がいるから」施設名が入っている場合と、「ただそこに施設があるから」施設名が入っている場合の二つに分けることができそうであり、「長尾変電所前」はおそらく後者に属するのだと思う”
と、8年半前の「長尾変電所前」の記事で書いたのだが、これに当てはめると、「○○方面」では、「その施設に行く人がいるから」という観点を重視すべき、という考えが成り立つと言えそう。
それにしてもここは、ボートレースから警察署、領事館まで、多様な“Next stop”を持つバス停であり、「DWK」もそこそこ高い。
(つづく)
(つづき)
「那珂小学校前」は “NAKA JUNIOR SCHOOL MAE”、「八田小学校前」は “HATTA ELEMENTARY SCHOOL”だったが、こちらの英字表記は“YANAGANISISHO IRIGUCHI”。

「弥永西小入口」。



以前の記事でも取り上げた、バス停と大きな木。

現在は「62番」から「62-1番」に変更となり、また、県庁、吉塚営業所にも行かなくなっている。

ただし、老司で「62-1番」から「62番」に変わり、

さらに西鉄大橋駅で「62番」から3パターンに変身。

全体の道のり。

「特快162番」も、番号の付け方の意味を踏まえれば(もともとは全て「62番」だったものを、片縄方面が「62番」で、警弥郷方面が「62-1番」として分割した)、「162-1番」でないといけないのだが、「3桁の行先番号には枝番が付かない」という“原則”もあって、矛盾を抱えつつも仕方なく(?)この番号を背負っている。
また、「都市高62」という表現の違和感については、この記事やこの記事でも触れたところである。

土日祝日は、そんな矛盾や違和感とは無縁で、全てが西鉄大橋駅止まり。

ちなみに、「弥永西小入口」の大橋駅方面の乗り場は、一方通行路上にある。
左が大橋駅方面の乗り場がある道路で、





博多南駅方面の乗り場は右の一方通行ではない道路上に。
(つづく)
「那珂小学校前」は “NAKA JUNIOR SCHOOL MAE”、「八田小学校前」は “HATTA ELEMENTARY SCHOOL”だったが、こちらの英字表記は“YANAGANISISHO IRIGUCHI”。

「弥永西小入口」。



以前の記事でも取り上げた、バス停と大きな木。

現在は「62番」から「62-1番」に変更となり、また、県庁、吉塚営業所にも行かなくなっている。

ただし、老司で「62-1番」から「62番」に変わり、

さらに西鉄大橋駅で「62番」から3パターンに変身。

全体の道のり。

「特快162番」も、番号の付け方の意味を踏まえれば(もともとは全て「62番」だったものを、片縄方面が「62番」で、警弥郷方面が「62-1番」として分割した)、「162-1番」でないといけないのだが、「3桁の行先番号には枝番が付かない」という“原則”もあって、矛盾を抱えつつも仕方なく(?)この番号を背負っている。
また、「都市高62」という表現の違和感については、この記事やこの記事でも触れたところである。

土日祝日は、そんな矛盾や違和感とは無縁で、全てが西鉄大橋駅止まり。

ちなみに、「弥永西小入口」の大橋駅方面の乗り場は、一方通行路上にある。
左が大橋駅方面の乗り場がある道路で、





博多南駅方面の乗り場は右の一方通行ではない道路上に。
(つづく)
(つづき)
「那珂小学校前」。
英字表記は“NAKA JUNIOR SCHOOL MAE”で、意味重視なのか読み重視なのか、はたまた訳がそもそも合っているのか、など、いろんな論点を投げかけてくれている。





郊外行き(板付七丁目、井尻駅、雑餉隈営業所方面)乗り場。
正面は「那珂小学校」となっていて、側面とは異なり“前”がない。




都心行き(博多駅方面)乗り場。
こちらも側面と前面とで名称が異なる。
行先案内にある「藤崎」には今年の春以降行かなくなっており、代わりに(ではないですが)、2011年2月から県庁、名島、アイランドシティ方面に行けるようになっている。

二つの乗り場の間にある「那珂小学校」交差点。

筑紫通りから北西に分岐するこの道路は、かつてのバス通りだが、ここをバスで通った記憶がないのが悔やまれる。

まっすぐ行くと「東光寺」。

青が旧バス通り。
道路のつながり方をみると、これと並行する赤の部分に新しい道路を造りたかったのでは?という意図が感じられる。

ただし、現在の都市計画図にはそのような計画線はなし(赤い線は用途地域の境界、紫やピンクの色は用途地域であり、都市計画道路とは関係なし)。
間に古墳や工場があって難しそうだったから早々に諦めたのでは?などとも考えるのだが、その計画の有無を含め、全て想像です。
(つづく)
「那珂小学校前」。
英字表記は“NAKA JUNIOR SCHOOL MAE”で、意味重視なのか読み重視なのか、はたまた訳がそもそも合っているのか、など、いろんな論点を投げかけてくれている。





郊外行き(板付七丁目、井尻駅、雑餉隈営業所方面)乗り場。
正面は「那珂小学校」となっていて、側面とは異なり“前”がない。




都心行き(博多駅方面)乗り場。
こちらも側面と前面とで名称が異なる。
行先案内にある「藤崎」には今年の春以降行かなくなっており、代わりに(ではないですが)、2011年2月から県庁、名島、アイランドシティ方面に行けるようになっている。

二つの乗り場の間にある「那珂小学校」交差点。

筑紫通りから北西に分岐するこの道路は、かつてのバス通りだが、ここをバスで通った記憶がないのが悔やまれる。

まっすぐ行くと「東光寺」。

青が旧バス通り。
道路のつながり方をみると、これと並行する赤の部分に新しい道路を造りたかったのでは?という意図が感じられる。

ただし、現在の都市計画図にはそのような計画線はなし(赤い線は用途地域の境界、紫やピンクの色は用途地域であり、都市計画道路とは関係なし)。
間に古墳や工場があって難しそうだったから早々に諦めたのでは?などとも考えるのだが、その計画の有無を含め、全て想像です。
(つづく)
(つづき)
「天神高速バスターミナル前」
英字表記は“TENJIN EXPRESSWAY BUS TERMINAL-MAE”

意味重視だが最後の“MAE”は読み。
福岡地区は「読み重視」が基本だったのだが、それを前提とすればここは例外。
読みよりも意味を伝えるほうが重要という判断なのか、それとも、西鉄の施設だし英訳も定まっているので使い易かったのか。
最後の“MAE”は余計な気もするが、

“MAE”を外してしまうとバスターミナル「そのもの」との混同が起きてしまうので外せなかった…という感じだろうか。

今年の7月から、ここから北九州空港にも行けるようになっているが、午前3時20分の発車であり、かなりハードルが高い。
利用状況はどんな具合なのでしょうか。

「100円循環バス」にとってのバス停ナンバーは8。
でも、来年6月、連接バスが運行を開始したら、「100円循環バス」は渡辺通り経由から福岡市役所・天神中央公園前経由に変更になるかも(何の根拠もない想像です)。
今年春の天神地区の乗り物変更も、連接バス導入の布石の一つだったように思える。

こちらは連接バスのプレスリリースからの引用。
これを眺めていると、今こそ「西鉄貝塚線を中洲川端駅まで延長する」ことを検討してもよいのでは?という思いを強くする(参考記事1、参考記事2、参考記事3、参考記事4)。
(つづく)
「天神高速バスターミナル前」
英字表記は“TENJIN EXPRESSWAY BUS TERMINAL-MAE”

意味重視だが最後の“MAE”は読み。
福岡地区は「読み重視」が基本だったのだが、それを前提とすればここは例外。
読みよりも意味を伝えるほうが重要という判断なのか、それとも、西鉄の施設だし英訳も定まっているので使い易かったのか。
最後の“MAE”は余計な気もするが、

“MAE”を外してしまうとバスターミナル「そのもの」との混同が起きてしまうので外せなかった…という感じだろうか。

今年の7月から、ここから北九州空港にも行けるようになっているが、午前3時20分の発車であり、かなりハードルが高い。
利用状況はどんな具合なのでしょうか。

「100円循環バス」にとってのバス停ナンバーは8。
でも、来年6月、連接バスが運行を開始したら、「100円循環バス」は渡辺通り経由から福岡市役所・天神中央公園前経由に変更になるかも(何の根拠もない想像です)。
今年春の天神地区の乗り物変更も、連接バス導入の布石の一つだったように思える。

こちらは連接バスのプレスリリースからの引用。
これを眺めていると、今こそ「西鉄貝塚線を中洲川端駅まで延長する」ことを検討してもよいのでは?という思いを強くする(参考記事1、参考記事2、参考記事3、参考記事4)。
(つづく)
(つづき)
福岡市中央区の「薬院駅前」バス停。
英字表記は“YAKUIN STATION MAE”ではなく“YAKUINEKIMAE”であり読み重視。
“YAKUIN”と“EKIMAE”の間にスペースがないので、そのまま読むと、“ヤクイネキマエ”となるが、“ヤクイネキマエ”のほうがかっこよく聞こえるかも(?)。

「快速」とはいうものの、「柳橋」に停まらないだけ。

反対側。


「9番」「10番」「15番」「20番」は、この春から「六本松三丁目」に停車しなくなったが、ここには「快速」という概念は出てきていません。
(つづく)
福岡市中央区の「薬院駅前」バス停。
英字表記は“YAKUIN STATION MAE”ではなく“YAKUINEKIMAE”であり読み重視。
“YAKUIN”と“EKIMAE”の間にスペースがないので、そのまま読むと、“ヤクイネキマエ”となるが、“ヤクイネキマエ”のほうがかっこよく聞こえるかも(?)。

「快速」とはいうものの、「柳橋」に停まらないだけ。

反対側。


「9番」「10番」「15番」「20番」は、この春から「六本松三丁目」に停車しなくなったが、ここには「快速」という概念は出てきていません。
(つづく)
(つづき)
福岡市東区の「オークタウン入口」バス停。
英字表記は“OHKU TOWN IRIGUCHI”で、読み重視と意味重視が混在しているが、「オー」を“OH”とするのはローマ字としては減点対象かも。
「よう」を“YHO”と表記するよりは減点は小さそうですが。





下原からやってくる路線が停車。

信号のほうは“Oak Town Entrance”と、一応、意味重視。


反対方向の乗り場には、和白(営)、青柳四角、こもの、古賀駅前の表記も残るが、


実際は、3つ先の下原行きと、一日一本だけの新宮緑ケ浜行きのみ。

交差点から南東方向、こっちがオークタウン方面。
ここが春日市であれば、確実にバスが通っていたと思われるが、あいにく(?)ここは福岡市であり、オークタウンに乗り入れるバス路線はない。
この道路を上まで登りきって、突き当たりを左に行けば久山町、右に行けば香椎宮方面への抜け道。



上部に建設中の高架橋は、

「博多バイパスをつくっています」

ここからもバイパスに入れるようになるもよう。

勅使道、松崎方面と、

国道3号方面。
私が小学一年生の時に初めて買った福岡市の地図に、この道路の計画線が既に入っていたが、それから30年以上の歳月が流れ、完成形がようやく見えてきた。

バイパスの起点。
毎朝バスの車窓から目にする国道3号(東部青果市場前~九州産業大学南口間)からの眺め。

こちらは香椎二丁目(香椎芹田公園付近)から松崎方向、

同じ場所から反対方向。
(つづく)
福岡市東区の「オークタウン入口」バス停。
英字表記は“OHKU TOWN IRIGUCHI”で、読み重視と意味重視が混在しているが、「オー」を“OH”とするのはローマ字としては減点対象かも。
「よう」を“YHO”と表記するよりは減点は小さそうですが。





下原からやってくる路線が停車。

信号のほうは“Oak Town Entrance”と、一応、意味重視。


反対方向の乗り場には、和白(営)、青柳四角、こもの、古賀駅前の表記も残るが、


実際は、3つ先の下原行きと、一日一本だけの新宮緑ケ浜行きのみ。

交差点から南東方向、こっちがオークタウン方面。
ここが春日市であれば、確実にバスが通っていたと思われるが、あいにく(?)ここは福岡市であり、オークタウンに乗り入れるバス路線はない。
この道路を上まで登りきって、突き当たりを左に行けば久山町、右に行けば香椎宮方面への抜け道。



上部に建設中の高架橋は、

「博多バイパスをつくっています」

ここからもバイパスに入れるようになるもよう。

勅使道、松崎方面と、

国道3号方面。
私が小学一年生の時に初めて買った福岡市の地図に、この道路の計画線が既に入っていたが、それから30年以上の歳月が流れ、完成形がようやく見えてきた。

バイパスの起点。
毎朝バスの車窓から目にする国道3号(東部青果市場前~九州産業大学南口間)からの眺め。

こちらは香椎二丁目(香椎芹田公園付近)から松崎方向、

同じ場所から反対方向。
(つづく)
(つづき)
福岡市城南区の「福大病院」バス停。
英字表記は“FUKUDAI BYOIN”であり、読み重視。

病院の建物のまん前なので、敢えて意味を伝える必要もなさそう(そういう意図で、読み重視になっている訳ではないと思いますが)。

両隣りのバス停は、「福大第二記念会堂前」「福大正門前」と「福大薬学部前」と、「福大」が全て入っている。
かつては周囲に、福大東口、長野町、倉瀬戸、福大病院東口、福大病院南口、梅林、市牟田池、西南分校前…などの名のバス停があったが、いずれも改称されており(ただし、福大病院東口のみ廃止)、改称率(?)が高いエリアでもある。


「福大病院」が終点のバスは、何番であっても「番号なし」でやってくる。
南福岡駅付近における「雑餉隈営業所行き」と同じような扱い。


都心方面と、


郊外方面が

並んで立つ。
バス停の下には地下鉄七隈線「福大前」駅がある。
「14番」を親とする茶山線シリーズ(「14番」のほかに「114番」「140番」)の本数は全盛期と比較すると見る影もないが、地下鉄で天神まで行けるようになっても、まだこれだけのバスが走っていることは特筆すべきなのかもしれない。
ただ、地下鉄の天神南から博多までの延伸工事も始まっており、開通すれば、現時点で茶山線シリーズの中で最も本数が多い「114番」が一番大きな影響を受けそう。
まあ、そうなる前に、大きな再編が行われそうでもありますが。

かつての「福大病院」のバス乗り場は、ここから少し西側にロータリーがありました。
また、地下鉄が開業してしばらくの間、ここから曲渕や椎原に行けた時期もありました。
(つづく)
福岡市城南区の「福大病院」バス停。
英字表記は“FUKUDAI BYOIN”であり、読み重視。

病院の建物のまん前なので、敢えて意味を伝える必要もなさそう(そういう意図で、読み重視になっている訳ではないと思いますが)。

両隣りのバス停は、「福大第二記念会堂前」「福大正門前」と「福大薬学部前」と、「福大」が全て入っている。
かつては周囲に、福大東口、長野町、倉瀬戸、福大病院東口、福大病院南口、梅林、市牟田池、西南分校前…などの名のバス停があったが、いずれも改称されており(ただし、福大病院東口のみ廃止)、改称率(?)が高いエリアでもある。


「福大病院」が終点のバスは、何番であっても「番号なし」でやってくる。
南福岡駅付近における「雑餉隈営業所行き」と同じような扱い。


都心方面と、


郊外方面が

並んで立つ。
バス停の下には地下鉄七隈線「福大前」駅がある。
「14番」を親とする茶山線シリーズ(「14番」のほかに「114番」「140番」)の本数は全盛期と比較すると見る影もないが、地下鉄で天神まで行けるようになっても、まだこれだけのバスが走っていることは特筆すべきなのかもしれない。
ただ、地下鉄の天神南から博多までの延伸工事も始まっており、開通すれば、現時点で茶山線シリーズの中で最も本数が多い「114番」が一番大きな影響を受けそう。
まあ、そうなる前に、大きな再編が行われそうでもありますが。

かつての「福大病院」のバス乗り場は、ここから少し西側にロータリーがありました。
また、地下鉄が開業してしばらくの間、ここから曲渕や椎原に行けた時期もありました。
(つづく)
(つづき)
福岡市東区の「八田小学校前」バス停。
「八田遊園地」の英字表記は、“HATTA AMUSEMENT PARK”ではなく、“HATTA YUENCHI”だったが、ここ「八田小学校前」は、“HATTA SHOGAKKO MAE”ではなく、“HATTA ELEMENTARY SCHOOL”。





土井団地、みどりが丘団地(入口)方面行き乗り場と、




流通センター、松島一丁目、博多駅方面行き乗り場。
こちらは「八田小学校前」ではなく「八田小学校」という名称になっており「前」の有無の違いがあるのだが、「産業団地」と「産業団地前」のような別のバス停ではない。

このまままっすぐ行くと千早駅なのだが、千早駅に行く路線はない。
少し先の「舞松原」の交差点で合流してくる路線に関しても、直進して千早駅に行く「4番」よりも、「若宮田」で左折して都市高速経由で天神に向かう「24C」のほうに重点が置かれている。
なお、「八田小学校」とか「八田小学校前」といいながら、小学校まではやや距離があり、隣りの「八田」のほうが近いかもしれない。
かつては「71番」(現在の「大濠公園~天神~県庁~巴町~月見町」ではなく、その一世代前の路線)の八田小経由などもここを走っていたが、この二十年以上はずっと「73番」のみであり、「レークヒルズ野多目」や「片江小学校前」などと同様、“なぜか天神行きのバスに恵まれない”という状態が続いている。
もともとは「73番」も、当時の「72番」などと同様、県道福岡直方線を通って土井営業所まで行ってそこから土井団地に向かっていた(郊外行きでみた場合)が、おそらく30年少し前に「多々良」(当時は「国鉄多々良」)の先で「若宮一丁目」のほうに分岐して、坂を上って下りた後の交差点(八田交番がある若宮一丁目交差点)で「八田小学校経由土井団地行き」と「八田団地経由土井営業所行き」に分かれるという2系統体制になった。

これが「八田小学校」バス停からすぐ近くの「若宮一丁目」交差点で、この先が、県道福岡直方線方面。
当時は「八田小学校経由土井団地行き」と「八田団地経由土井営業所行き」が“同格”という感じだったが、現在は(といっても、もうかなり前からですが)、「八田団地経由土井営業所行き」のほうは一日一本のみになっている。
県道福岡直方線から早めに離れるようなルート設定は、同じく博多駅と土井方面を結ぶJR九州バス(当時は国鉄バス)との差別化を図る意味があったから…なのかはわからないが、現在では、JR九州バスと「73番」の間には、あまり代替性はない感じがする。
「73番」の「八田小学校経由土井団地行き」と「八田団地経由土井営業所行き」は、八田の交差点で垂直に交わるという、なかなか目を惹く動きをする。
これは、「八田」の交差点を北からやってきて東のほうに曲がるのが難しいからなのだろう…と、当時はそう理解していたのだが、実際のところはどうなのでしょうか。
(つづく)
福岡市東区の「八田小学校前」バス停。
「八田遊園地」の英字表記は、“HATTA AMUSEMENT PARK”ではなく、“HATTA YUENCHI”だったが、ここ「八田小学校前」は、“HATTA SHOGAKKO MAE”ではなく、“HATTA ELEMENTARY SCHOOL”。





土井団地、みどりが丘団地(入口)方面行き乗り場と、




流通センター、松島一丁目、博多駅方面行き乗り場。
こちらは「八田小学校前」ではなく「八田小学校」という名称になっており「前」の有無の違いがあるのだが、「産業団地」と「産業団地前」のような別のバス停ではない。

このまままっすぐ行くと千早駅なのだが、千早駅に行く路線はない。
少し先の「舞松原」の交差点で合流してくる路線に関しても、直進して千早駅に行く「4番」よりも、「若宮田」で左折して都市高速経由で天神に向かう「24C」のほうに重点が置かれている。
なお、「八田小学校」とか「八田小学校前」といいながら、小学校まではやや距離があり、隣りの「八田」のほうが近いかもしれない。
かつては「71番」(現在の「大濠公園~天神~県庁~巴町~月見町」ではなく、その一世代前の路線)の八田小経由などもここを走っていたが、この二十年以上はずっと「73番」のみであり、「レークヒルズ野多目」や「片江小学校前」などと同様、“なぜか天神行きのバスに恵まれない”という状態が続いている。
もともとは「73番」も、当時の「72番」などと同様、県道福岡直方線を通って土井営業所まで行ってそこから土井団地に向かっていた(郊外行きでみた場合)が、おそらく30年少し前に「多々良」(当時は「国鉄多々良」)の先で「若宮一丁目」のほうに分岐して、坂を上って下りた後の交差点(八田交番がある若宮一丁目交差点)で「八田小学校経由土井団地行き」と「八田団地経由土井営業所行き」に分かれるという2系統体制になった。

これが「八田小学校」バス停からすぐ近くの「若宮一丁目」交差点で、この先が、県道福岡直方線方面。
当時は「八田小学校経由土井団地行き」と「八田団地経由土井営業所行き」が“同格”という感じだったが、現在は(といっても、もうかなり前からですが)、「八田団地経由土井営業所行き」のほうは一日一本のみになっている。
県道福岡直方線から早めに離れるようなルート設定は、同じく博多駅と土井方面を結ぶJR九州バス(当時は国鉄バス)との差別化を図る意味があったから…なのかはわからないが、現在では、JR九州バスと「73番」の間には、あまり代替性はない感じがする。
「73番」の「八田小学校経由土井団地行き」と「八田団地経由土井営業所行き」は、八田の交差点で垂直に交わるという、なかなか目を惹く動きをする。
これは、「八田」の交差点を北からやってきて東のほうに曲がるのが難しいからなのだろう…と、当時はそう理解していたのだが、実際のところはどうなのでしょうか。
(つづく)
(つづき)
福岡市東区の「土井営業所」バス停。
営業所最寄りのバス停に「営業所」が入っており、「新宮緑ケ浜」「桜丘第四」「野方」「四箇田団地」「早良高校前」などとは違うパターン。
英字表記は、「DOI EIGYOSHO」で、宇美営業所や雑餉隈営業所と同じ感じ。
土井営業所の所在地は「多々良」、土井団地は「青葉」であり、いずれも「土井」にはないが、JR九州バスの「筑前土井」バス停は「土井」にある。

営業所の脇に乗り場。

路線のバリエーションはそこそこ多いが、



一日一本だけとか二本だけという系統も多く、

「24C」を除くと、かなりスカスカになってしまいそう。
毎週日曜日の昼間に一本だけ「無番」の上脇田行きがここから出ていた時代もありました。

「4番」の前身は「24番」。
このブログを始めてまもなく9年になるが、この10年足らずの間にも、記憶をたどれないほどいろんな変化があった路線。
「240番」「24N」など、派生路線もいろいろとできたが、ちゃんと生き残っているのは「24C」のみ。
「土井営業所~千早駅」の区間便も「4番」で、「千早駅~天神・タワー」も「4番」。
今後もし、「タワー~昭和通り~天神」という区間便ができてそれも「4番」になれば、かつて「1番」に「野方~姪浜駅」と「博多駅~板付七丁目」が併存していたのと同じような状況になる。

ひとつ隣りのバス停も「土井営業所」となっているのは誤りではなく、


この先の、「土井(桃田)」の交差点の先に、「土井営業所(千鳥すし前)」というもう一つの乗り場があるため。
建物や県道を隔てるため、「土井営業所(千鳥すし前)」からは営業所の存在になかなか気付きづらい。


対面側の乗り場。



都心行きが夕方以降にしか停車せず、通学や都心への通勤に全く使えない理由は「西鉄多々良」と同じ。
(つづく)
福岡市東区の「土井営業所」バス停。
営業所最寄りのバス停に「営業所」が入っており、「新宮緑ケ浜」「桜丘第四」「野方」「四箇田団地」「早良高校前」などとは違うパターン。
英字表記は、「DOI EIGYOSHO」で、宇美営業所や雑餉隈営業所と同じ感じ。
土井営業所の所在地は「多々良」、土井団地は「青葉」であり、いずれも「土井」にはないが、JR九州バスの「筑前土井」バス停は「土井」にある。

営業所の脇に乗り場。

路線のバリエーションはそこそこ多いが、



一日一本だけとか二本だけという系統も多く、

「24C」を除くと、かなりスカスカになってしまいそう。
毎週日曜日の昼間に一本だけ「無番」の上脇田行きがここから出ていた時代もありました。

「4番」の前身は「24番」。
このブログを始めてまもなく9年になるが、この10年足らずの間にも、記憶をたどれないほどいろんな変化があった路線。
「240番」「24N」など、派生路線もいろいろとできたが、ちゃんと生き残っているのは「24C」のみ。
「土井営業所~千早駅」の区間便も「4番」で、「千早駅~天神・タワー」も「4番」。
今後もし、「タワー~昭和通り~天神」という区間便ができてそれも「4番」になれば、かつて「1番」に「野方~姪浜駅」と「博多駅~板付七丁目」が併存していたのと同じような状況になる。

ひとつ隣りのバス停も「土井営業所」となっているのは誤りではなく、


この先の、「土井(桃田)」の交差点の先に、「土井営業所(千鳥すし前)」というもう一つの乗り場があるため。
建物や県道を隔てるため、「土井営業所(千鳥すし前)」からは営業所の存在になかなか気付きづらい。


対面側の乗り場。



都心行きが夕方以降にしか停車せず、通学や都心への通勤に全く使えない理由は「西鉄多々良」と同じ。
(つづく)
(つづき)
福岡市博多区の「福高前」バス停。
結局、4月1日に「福岡高校前」に改称されることはなく、現在も「福高前」のまま。

英字表記は「FUKKO」であり、なかなか潔い(?)。
北九州だったらどんな表記になっていただろうか。


博多駅とゆめタウン博多を結ぶ「15番」が停車。
「福高前」は、かつての市内電車「循環線」のルートであり、市電廃止後も代替路線の「85番」福博循環線が大量に走っていたが、

現在は、これくらいのボリューム。
それでも「15番」は、この10年あまり、ルート変更や大きな減便もなく日々淡々と運行している感があり、低いレベルで安定している印象。

「千鳥橋“72”行き」も健在。



堅粕一丁目~緑橋~祇園町~駅前一丁目~博多駅方面行き乗り場。

この先は、国道3号。


千代町~千鳥橋~千代五丁目~馬出三丁目~浜松町~東浜~ゆめタウン博多方面行き乗り場。

「85番」の末期は、千鳥橋を起点とする一周の循環運行でした。


電車が向こうから走ってきそうなカーブ。
この先もまた、国道3号。
天神、博多駅という現在の商業中心の位置、そして、都心に対する道路の角度などの面から考えると、今後、このバス停を通るバスが再び増加することはあまり見込めないのかも。
(つづく)
福岡市博多区の「福高前」バス停。
結局、4月1日に「福岡高校前」に改称されることはなく、現在も「福高前」のまま。

英字表記は「FUKKO」であり、なかなか潔い(?)。
北九州だったらどんな表記になっていただろうか。


博多駅とゆめタウン博多を結ぶ「15番」が停車。
「福高前」は、かつての市内電車「循環線」のルートであり、市電廃止後も代替路線の「85番」福博循環線が大量に走っていたが、

現在は、これくらいのボリューム。
それでも「15番」は、この10年あまり、ルート変更や大きな減便もなく日々淡々と運行している感があり、低いレベルで安定している印象。

「千鳥橋“72”行き」も健在。



堅粕一丁目~緑橋~祇園町~駅前一丁目~博多駅方面行き乗り場。

この先は、国道3号。


千代町~千鳥橋~千代五丁目~馬出三丁目~浜松町~東浜~ゆめタウン博多方面行き乗り場。

「85番」の末期は、千鳥橋を起点とする一周の循環運行でした。


電車が向こうから走ってきそうなカーブ。
この先もまた、国道3号。
天神、博多駅という現在の商業中心の位置、そして、都心に対する道路の角度などの面から考えると、今後、このバス停を通るバスが再び増加することはあまり見込めないのかも。
(つづく)
(つづき)
福岡市早良区の「入部幼稚園前」バス停。
かつての「入部派出所前」である。
英字表記は“IRIBEYHOCHIENMAE”であり、ここから正しい「読み」にたどり着くのはなかなか難しい。
地名も、「いりべ」ではなく「いるべ」が正式。

周囲はこんなにのどか。
向こうに見える山のふもと、室見川に沿って昭和バスが走っていた時代も遠くなりつつある。


郊外行き乗り場。


行先のバリエーションがここまで減ってしまいました…。



都心方面行き乗り場。



それでもまだ、通勤時間帯に都心行きの路線のバリエーションがこれだけあるというのは、かなり恵まれているほうではないかと思われる。
(つづく)
福岡市早良区の「入部幼稚園前」バス停。
かつての「入部派出所前」である。
英字表記は“IRIBEYHOCHIENMAE”であり、ここから正しい「読み」にたどり着くのはなかなか難しい。
地名も、「いりべ」ではなく「いるべ」が正式。

周囲はこんなにのどか。
向こうに見える山のふもと、室見川に沿って昭和バスが走っていた時代も遠くなりつつある。


郊外行き乗り場。


行先のバリエーションがここまで減ってしまいました…。



都心方面行き乗り場。



それでもまだ、通勤時間帯に都心行きの路線のバリエーションがこれだけあるというのは、かなり恵まれているほうではないかと思われる。
(つづく)