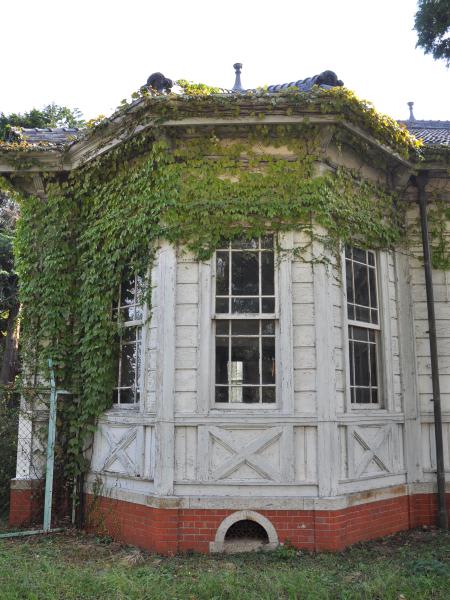JR東海道線か名鉄本線に乗り、金山~熱田(神宮前)間を通ると、線路のすぐ脇(東側)の赤煉瓦の倉庫が目につきます。
倉庫は東西に長く北側が道路に面しているため、縦長の窓が並んだ美しいイギリス積みの壁面を見ることができます。
当初は熱田砲兵工廠として造られ、囚人を集め兵器を製造していたそうです。
煉瓦倉庫が当初のまま完全に保存されているのは北側の一棟だけですが、敷地内には一部煉瓦造の倉庫が見られます。
◆中京倉庫(株)/愛知県名古屋市熱田区六野町2
竣工:明治37~40年(1904~1907)
施工:一部有馬組
構造:煉瓦造平屋建
撮影:2010/02/11

北側道路から望む

倉庫南側

北側壁面~窓はコンクリートで埋められています

西妻側の丸窓

敷地内のほとんどの倉庫は煉瓦の上からコンクリートが塗られ、一部だけが煉瓦のまま残っています










































 吉田城と手筒花火
吉田城と手筒花火