
最近よく私がセミナーでするお話をひとつ。
「カイゼン」や「内部統制の文書化」などがクローズアップされる機会が増えた昨今、「見える化」という言葉が随分ひんぱんにキーワード的に使われるようになりました。当ブログでも以前「見える化」を取り上げたことがありますが、今日は「見える化」をキーワードにした社内改革におけるふたつのポイントについてお話します。
「見える化」を一般社員向けに説明するとき私は、同じ広告チラシをひとつは事務封筒にもうひとつは透明なクリアファイルに入れます。そのふたつを比較して、同じチラシが入っていても片方は何を訴えたいのか外から全く分からない状態、もう片方は表も裏も全部読めて何を訴えたいのかすべて分かる状態であることを示します。
そしてこう話します。「中身が見えなければ何も考えようがないけど、中身が見えれば様々な考えや行動がうまれますね」。「「見える化」とは、「様々な経営資源を有効・有益に活用するために、どこに何があるか、誰が何をしているか、何を思っているかを、中身が見えない封筒に入った状態から透明なクリアファイルに移す作業なのです」。その上で、「封筒の中身は“モノ”である場合と、“ヒト”である場合があります」と続けます。すなわち、「見える化」の大きなふたつのポイントとして、「モノの見える化」と「ヒトの見える化」をあげる訳です。
「モノの見える化」とは…。「何がどこにあるのか」、「経営資源たる「モノ」はどのように扱うのか」、「「モノ」に関して何をしてよく何をしてはいけないのか」、等々について全社員から「見える」状態にすることです。すなわち、「ルール化」や「制度化」「マニュアル化」「プロセスの標準化」と言われる改善策はすべてこの「モノの見える化」に他ならないのです。
しかしながら、今あげた「ルール化」や「制度化」や「マニュアル化」や「プロセスの標準化」を、高いコストをかけてプロのコンサルタントを雇って一生懸命やってもうまく機能しないことが間々あります。これはなぜか?これは、もうひとつの重要な「見える化」である「ヒトの見える化」が抜け落ちている場合がほとんどであると言っていいでしょう。
では、「ヒトの見える化」とは…?「ヒトの見える化」とは、「誰が何を考えているのか」、「誰が何のために何をしているのか」、「誰がどこに向かって動いているのか」、等々について「見える化」することです。すなわち、「ヒトの見える化」は「コミュニケーションの活性化」に他ならないのです。
「コミュニケーションの活性化」を、もっと具体的施策に落とし込むとどうなるでしょう。“ホウ・レン・ソウ”の徹底目的での「日報制度」の見直し、「会議の改廃・運営の見直し」、「提案制度の制定」、「評価制度の見直しと明確化」、「管理者教育による部下とのコミュニケーション能力の向上」、あるいは「社長に対するパーソナル・コーチングの実施」などがそれにあたります。
すなわち、ふたつの「見える化」になぞらえてお話することは、「社内標準化」と「コミュニケーション活性化」の重要性を言っている訳です。このふたつはどちらが欠けても、改善はうまく進みません。先に話したように、「社内標準化」だけでは形が整っても魂が入らないままでしょうし、「コミュニケーションの活性化」だけが進んだのでは、整備が進まない社内状況に対して言いたい放題の不平不満ばかりが噴出して、社内秩序や組織運営を危うくするでしょう。
手前味噌的に聞こえてしまうかもしれませんが、このふたつの「見える化」をバランスよくリードし具体的にどのような施策をどのような手順で進めるのがよいかを、オーダーメイドでコーディネートするのが、組織経験豊富なコンサルタントということになる訳です。
ちなみに、このふたつの「見える化」は、社内改革だけでなく、対顧客戦略においても有効なソリューションです。もっと言えば、家庭内の問題改善にも応用可能な“万能薬”であります。その辺はセミナーではお話してます。ブログでは、またの機会にでもお話いたします。
「カイゼン」や「内部統制の文書化」などがクローズアップされる機会が増えた昨今、「見える化」という言葉が随分ひんぱんにキーワード的に使われるようになりました。当ブログでも以前「見える化」を取り上げたことがありますが、今日は「見える化」をキーワードにした社内改革におけるふたつのポイントについてお話します。
「見える化」を一般社員向けに説明するとき私は、同じ広告チラシをひとつは事務封筒にもうひとつは透明なクリアファイルに入れます。そのふたつを比較して、同じチラシが入っていても片方は何を訴えたいのか外から全く分からない状態、もう片方は表も裏も全部読めて何を訴えたいのかすべて分かる状態であることを示します。
そしてこう話します。「中身が見えなければ何も考えようがないけど、中身が見えれば様々な考えや行動がうまれますね」。「「見える化」とは、「様々な経営資源を有効・有益に活用するために、どこに何があるか、誰が何をしているか、何を思っているかを、中身が見えない封筒に入った状態から透明なクリアファイルに移す作業なのです」。その上で、「封筒の中身は“モノ”である場合と、“ヒト”である場合があります」と続けます。すなわち、「見える化」の大きなふたつのポイントとして、「モノの見える化」と「ヒトの見える化」をあげる訳です。
「モノの見える化」とは…。「何がどこにあるのか」、「経営資源たる「モノ」はどのように扱うのか」、「「モノ」に関して何をしてよく何をしてはいけないのか」、等々について全社員から「見える」状態にすることです。すなわち、「ルール化」や「制度化」「マニュアル化」「プロセスの標準化」と言われる改善策はすべてこの「モノの見える化」に他ならないのです。
しかしながら、今あげた「ルール化」や「制度化」や「マニュアル化」や「プロセスの標準化」を、高いコストをかけてプロのコンサルタントを雇って一生懸命やってもうまく機能しないことが間々あります。これはなぜか?これは、もうひとつの重要な「見える化」である「ヒトの見える化」が抜け落ちている場合がほとんどであると言っていいでしょう。
では、「ヒトの見える化」とは…?「ヒトの見える化」とは、「誰が何を考えているのか」、「誰が何のために何をしているのか」、「誰がどこに向かって動いているのか」、等々について「見える化」することです。すなわち、「ヒトの見える化」は「コミュニケーションの活性化」に他ならないのです。
「コミュニケーションの活性化」を、もっと具体的施策に落とし込むとどうなるでしょう。“ホウ・レン・ソウ”の徹底目的での「日報制度」の見直し、「会議の改廃・運営の見直し」、「提案制度の制定」、「評価制度の見直しと明確化」、「管理者教育による部下とのコミュニケーション能力の向上」、あるいは「社長に対するパーソナル・コーチングの実施」などがそれにあたります。
すなわち、ふたつの「見える化」になぞらえてお話することは、「社内標準化」と「コミュニケーション活性化」の重要性を言っている訳です。このふたつはどちらが欠けても、改善はうまく進みません。先に話したように、「社内標準化」だけでは形が整っても魂が入らないままでしょうし、「コミュニケーションの活性化」だけが進んだのでは、整備が進まない社内状況に対して言いたい放題の不平不満ばかりが噴出して、社内秩序や組織運営を危うくするでしょう。
手前味噌的に聞こえてしまうかもしれませんが、このふたつの「見える化」をバランスよくリードし具体的にどのような施策をどのような手順で進めるのがよいかを、オーダーメイドでコーディネートするのが、組織経験豊富なコンサルタントということになる訳です。
ちなみに、このふたつの「見える化」は、社内改革だけでなく、対顧客戦略においても有効なソリューションです。もっと言えば、家庭内の問題改善にも応用可能な“万能薬”であります。その辺はセミナーではお話してます。ブログでは、またの機会にでもお話いたします。











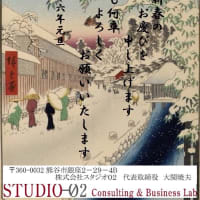
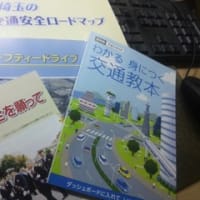
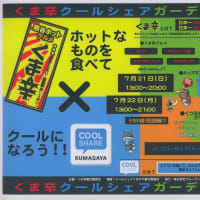
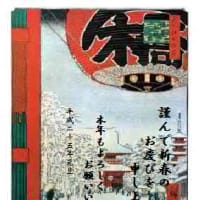


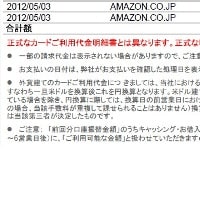

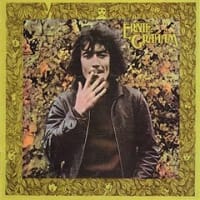
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます