本書は、死、極楽・地獄をテーマにえがいた絵本である。子ども向きではない、全年齢層向き。
昭和30年代、貧しい農家の高齢者が自宅で死を迎えた。そのうちのホンの数人ではあるが、その様子を医師の祖父に連れられて垣間見た。
当時の死はすべて自然死、静かな死であった。家族や親戚、隣近所の人たちがその時を待ちながら,患者や自分の死の時のことをしんみりと考えていたのだ。
高齢者の自然死を通じて、死は決して恐れるものではない・・私は何も分からなかったが、印象としてはそんな感じだった。人生の終末に迎える静かな死、いいものだと思った。
私の医療観はこのときにつくられた。だから、私は必要充分な診断・治療は行ったが、それでもいずれ患者に死期は来る。その判断のもとでは如何にスムーズに人生の最終コースに乗せるか、死戦期をいかに苦しくない状況にしてあげられるか、を最大の念頭に置いて来た。
例えていえば、秋田空港を力強く離陸した旅客機が無事飛行したあと目的地の羽田空港滑走路にスムーズに着陸する様に、である。着陸しないですむ旅客機はない。私が先輩後輩の医療を通じて見た患者の死の姿は決してスムーズでなく、不時着、墜落、オーバーラン、空中爆発・・であった。
当時の医療界全体が患者の死は医療の敗北で、いろんな手を用いて少しでも長く生かすべきといった考えがあって、心拍が停止するまで、時にはそのあとですら心臓に注射をうち、電気ショックをかけた。
結局は自分の医療観にそった医療を求めて現在の病院に移ったが、臨死状態の患者の治療は似たようなものであった。さいわい、私は自身の人間性の問題があったためであろう、同僚から仲間としては受け入れられたとは言えなかったが、それだけ自分の医療観に沿った診療が出来た。臨死期になると対症療法しかしない私に対して同僚から「手抜き医療」と激しく非難された事もあった。
人はいずれ死ぬ。結果が見えているのに患者を最後まで病気と闘わせる。そんな医療は正しいと思わない。患者は死の直前、30分ほどの安息期に入る。患者の呼吸・循環は一時的に安定し、表情も良くなり周囲の家族達と言葉を交わすこともある。この時期こそ死に向かって「患者が病気を受け入れ、戦うのをやめた」貴重な時間である。自然死に近い状態はこの時間が長い。この時間すら奪ってしまう医師が少なくない。
当時は、一生懸命治療してくれた医師が喜ばれた。
私の感覚から見ると家族と医師とで患者を生きながら地獄を味あわせていた、と思う。
そんな感覚で患者の終末期を見てきた私にとって、私が自身の医療に納得するためにもこの本は素晴らしいと思う。

(「このあと どうしちゃおう」の神様との面談の絵 この一枚からも癒やされる)
もうひとつ、この本はおじいさんの死を通じて、孫が「生きている間にやりたいことがいっぱいある」ことに気づかされる、というくだりである。そう、いい死を迎えるという事はいい生き方をすることなのだ。死ぬ瞬間であわてて時間を伸ばしてももう遅いのだ。
昭和30年代、貧しい農家の高齢者が自宅で死を迎えた。そのうちのホンの数人ではあるが、その様子を医師の祖父に連れられて垣間見た。
当時の死はすべて自然死、静かな死であった。家族や親戚、隣近所の人たちがその時を待ちながら,患者や自分の死の時のことをしんみりと考えていたのだ。
高齢者の自然死を通じて、死は決して恐れるものではない・・私は何も分からなかったが、印象としてはそんな感じだった。人生の終末に迎える静かな死、いいものだと思った。
私の医療観はこのときにつくられた。だから、私は必要充分な診断・治療は行ったが、それでもいずれ患者に死期は来る。その判断のもとでは如何にスムーズに人生の最終コースに乗せるか、死戦期をいかに苦しくない状況にしてあげられるか、を最大の念頭に置いて来た。
例えていえば、秋田空港を力強く離陸した旅客機が無事飛行したあと目的地の羽田空港滑走路にスムーズに着陸する様に、である。着陸しないですむ旅客機はない。私が先輩後輩の医療を通じて見た患者の死の姿は決してスムーズでなく、不時着、墜落、オーバーラン、空中爆発・・であった。
当時の医療界全体が患者の死は医療の敗北で、いろんな手を用いて少しでも長く生かすべきといった考えがあって、心拍が停止するまで、時にはそのあとですら心臓に注射をうち、電気ショックをかけた。
結局は自分の医療観にそった医療を求めて現在の病院に移ったが、臨死状態の患者の治療は似たようなものであった。さいわい、私は自身の人間性の問題があったためであろう、同僚から仲間としては受け入れられたとは言えなかったが、それだけ自分の医療観に沿った診療が出来た。臨死期になると対症療法しかしない私に対して同僚から「手抜き医療」と激しく非難された事もあった。
人はいずれ死ぬ。結果が見えているのに患者を最後まで病気と闘わせる。そんな医療は正しいと思わない。患者は死の直前、30分ほどの安息期に入る。患者の呼吸・循環は一時的に安定し、表情も良くなり周囲の家族達と言葉を交わすこともある。この時期こそ死に向かって「患者が病気を受け入れ、戦うのをやめた」貴重な時間である。自然死に近い状態はこの時間が長い。この時間すら奪ってしまう医師が少なくない。
当時は、一生懸命治療してくれた医師が喜ばれた。
私の感覚から見ると家族と医師とで患者を生きながら地獄を味あわせていた、と思う。
そんな感覚で患者の終末期を見てきた私にとって、私が自身の医療に納得するためにもこの本は素晴らしいと思う。

(「このあと どうしちゃおう」の神様との面談の絵 この一枚からも癒やされる)
もうひとつ、この本はおじいさんの死を通じて、孫が「生きている間にやりたいことがいっぱいある」ことに気づかされる、というくだりである。そう、いい死を迎えるという事はいい生き方をすることなのだ。死ぬ瞬間であわてて時間を伸ばしてももう遅いのだ。

















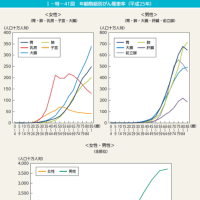


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます