SIGHTSEEING 


2005年 ラッタウット・ラープチャルーンサップ
物語の内容から言うとすごく気が重い一冊でした。
でも文章を追っていくのは楽しかったし、本当に読んで良かった一冊だと思っています。
作者はアメリカ生まれのタイ育ちの方だそうです。
生まれ育った場所への思いを、良いことも悪いこともひっくるめて
世界に向けて表現できるというのは素晴らしいことですね。
舞台は全てタイです。
私はタイに行ったことがないので、観光地として紹介されるイメージしか浮かびませんが
その町の隅々でこういうことがおこっているとは…と、暗澹たる気持ちで読んでいて
はたと「でもどの国でも同じことがおこっているのでは?」という気になりました。
もちろん観光地独特の出来事もあるし、日本では考えられない状況の物語もあります。
でも個々の人々にふりかかる不幸は、日本ではありえないというものではありません。
『徴兵の日(Draft Day )』
友人のウィチェと一緒に徴兵の抽選会場に向かいます。
ぼくは両親の贈り物のおかげで自分が徴兵されないことがわかっていました。
ウィチェのお母さんが二人分のお弁当を持って来てくれました。
ぼくは本当のことが言い出せずにいます。
日本では徴兵制が無いので、この不安や緊張感は到底わかりませんが
持てる者と持たざる者の区別をはっきりと晒してしまうシステムに驚きました。
徴兵に行かない人の罪悪感は、行く人の悲しみより早く消えてしまいそうですけど…
『観光(Sightseeing)』
北の大学へ行く準備に追われていたころ、母の様子がおかしくなっていき
ある日目が見えなくなっていることに気がつきました。
目が見えるうちにと、ふたりで20時間かけてルクマクへ観光に行くことにしました。
優しい言葉をかけるだけではどうにもならない落とし穴のような時間が
親子、夫婦、恋人の間に屡々存在しているような気がします。
お互いの不憫さを思いやりながらも、お互いの態度にいらついてしまうという状況は
特に両親が老いてくるとものすごくよくわかります。
『こんなところで死にたくない(Don't Let Me Die in This Place)』
ペリー老人はからだが不自由になったので、息子ジャックの世話になるために
アメリカからタイに来ました。
ジャックのタイ人の妻と2人の子供たちはカタコトの英語を話します。
子供は生意気ですが一緒にいると少しは楽しい気分になれます。
フラナリー・オコナーの『ゼラニウム』という短篇を思い出しました。
アメリカ版 “ ザ・頑固おやじ ” みたいな老人が、見知らぬ土地で最後を待つ気持ちを思うと
切ないものがありますね。
でもお世話する人も大変だと思う…少しは我慢しなくてはね。
最近、以前に較べて欧米で暮らすアジアの作家の本を読んでいる気がします。
作家がずっと故国にいたら同じテーマでも違った物語になるのか、変わらないのか、
それはよくわかりません。
でも読者としては、万国共通の悲喜こもごもに異国情緒が加わることで
物語の側面が増えて、いくつかの面白さを味わえるのが嬉しいような気がしています。



2005年 ラッタウット・ラープチャルーンサップ
物語の内容から言うとすごく気が重い一冊でした。
でも文章を追っていくのは楽しかったし、本当に読んで良かった一冊だと思っています。
作者はアメリカ生まれのタイ育ちの方だそうです。
生まれ育った場所への思いを、良いことも悪いこともひっくるめて
世界に向けて表現できるというのは素晴らしいことですね。
舞台は全てタイです。
私はタイに行ったことがないので、観光地として紹介されるイメージしか浮かびませんが
その町の隅々でこういうことがおこっているとは…と、暗澹たる気持ちで読んでいて
はたと「でもどの国でも同じことがおこっているのでは?」という気になりました。
もちろん観光地独特の出来事もあるし、日本では考えられない状況の物語もあります。
でも個々の人々にふりかかる不幸は、日本ではありえないというものではありません。
『徴兵の日(Draft Day )』

友人のウィチェと一緒に徴兵の抽選会場に向かいます。
ぼくは両親の贈り物のおかげで自分が徴兵されないことがわかっていました。
ウィチェのお母さんが二人分のお弁当を持って来てくれました。
ぼくは本当のことが言い出せずにいます。
日本では徴兵制が無いので、この不安や緊張感は到底わかりませんが
持てる者と持たざる者の区別をはっきりと晒してしまうシステムに驚きました。
徴兵に行かない人の罪悪感は、行く人の悲しみより早く消えてしまいそうですけど…
『観光(Sightseeing)』

北の大学へ行く準備に追われていたころ、母の様子がおかしくなっていき
ある日目が見えなくなっていることに気がつきました。
目が見えるうちにと、ふたりで20時間かけてルクマクへ観光に行くことにしました。
優しい言葉をかけるだけではどうにもならない落とし穴のような時間が
親子、夫婦、恋人の間に屡々存在しているような気がします。
お互いの不憫さを思いやりながらも、お互いの態度にいらついてしまうという状況は
特に両親が老いてくるとものすごくよくわかります。
『こんなところで死にたくない(Don't Let Me Die in This Place)』

ペリー老人はからだが不自由になったので、息子ジャックの世話になるために
アメリカからタイに来ました。
ジャックのタイ人の妻と2人の子供たちはカタコトの英語を話します。
子供は生意気ですが一緒にいると少しは楽しい気分になれます。
フラナリー・オコナーの『ゼラニウム』という短篇を思い出しました。
アメリカ版 “ ザ・頑固おやじ ” みたいな老人が、見知らぬ土地で最後を待つ気持ちを思うと
切ないものがありますね。
でもお世話する人も大変だと思う…少しは我慢しなくてはね。
最近、以前に較べて欧米で暮らすアジアの作家の本を読んでいる気がします。
作家がずっと故国にいたら同じテーマでも違った物語になるのか、変わらないのか、
それはよくわかりません。
でも読者としては、万国共通の悲喜こもごもに異国情緒が加わることで
物語の側面が増えて、いくつかの面白さを味わえるのが嬉しいような気がしています。










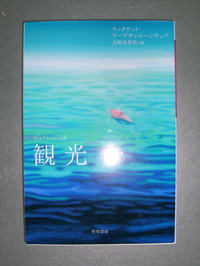







 一緒に収められている『バレンシア物語』という短篇選がとても好きでした。
一緒に収められている『バレンシア物語』という短篇選がとても好きでした。
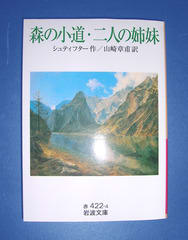

 」は
」は

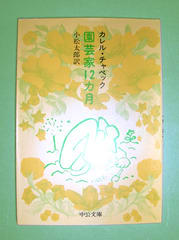

 などと夢見ています。
などと夢見ています。




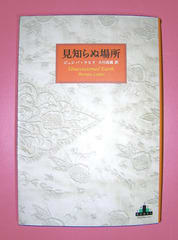




 」で始まるアニメ『アルプスの少女ハイジ』で
」で始まるアニメ『アルプスの少女ハイジ』で ヨーゼフがいませんよ
ヨーゼフがいませんよ 




