ERZAHLUNGEN UND KURZE PROSA 

フランツ・カフカ
アヴァンギャルドなものや抽象的な絵画は苦手です。
むかーし、テートギャラリーに美大卒の友人と行った時、真っ白なキャンバスに
釘が刺してある絵があって「これのどこがいいわけ?」とたずねたら
「これが芸術だと言いきれるところまでもってきたのがすごい」と言われました。
なるほどって思いますか? 私は思わないのですがうっすらと理解はできます。
正統な基礎が認知されているからこそ、なんのこっちゃ? なものも
豊かな想像力による芸術だと認められる、ってことかしらね?
カフカは私にとってそんな感じです。
物語の始まりは面白く、一語一句も魅力的なのですが、話しが一般常識の粋を超えて
展開していくと理解できなくなってしまうのです。
まったく読み手である私の落ち度であって、カフカに責められる点はありませんが
万人受けするとは思えないなぁ…『変身』はかなり分かりやすい話しですけどね。
そんな中でも、私が比較的理解できたものをご紹介します。
『火夫(Der Heizer)/1912年』
女中を妊娠させてアメリカにやられることになった16歳のポールは
船の中で、虐げられていると嘆くドイツ人の火夫に出会います。
彼を助けようと船長室で熱弁をふるうポールに、ひとりの紳士が叔父だと名乗ります。
『アメリカ』という長篇の第1章にあたる物語です。
これは普通ですが読み進むと意外な展開になっていくのでしょうか?
『アメリカ』は持っているので今度チャレンジしようと思います。
『中年のひとり者ブルームフェルト(Blumfeld,ein alterer Junggeslle)/1915年』
寂しいので犬でも飼おうかと思案しながら帰宅したブルームフェルトは
部屋の中で楽し気に跳ね回るふたつのボールに辟易させれます。
翌朝ボールを振り切って会社に行くと、使えないふたりの部下がさぼりたい放題です。
ボールの部分と会社の部分がまるで別物のようなのですが…
ボールはボールで解決してほしかった、けっこうコミカルだったんですよ。
それなのに会社の部分でどんより暗い話しになってしまって…
『万里の長城(Von den Gleichnissen)/1920年』
万里の長城はなぜ区間分割工法がとられたのか?
君主制や中国の国民性、都会と田舎における皇帝への忠誠の温度差などをとりあげて
論究を試みています。
普通に読むと真面目な論文にみえますし、納得の部分も多いのですが
この1冊に収められていると、もしかして全部つくりごと? と思われてなりません。
歴史家が読んだら抱腹絶倒ものなのでしょうか?
気がついたらカフカも何冊か持っていた私… 『城』とか『流刑地にて』とかね。
短編でこんなことじゃ先が思いやられます
いつか読むつもりですけど、いつだか分かりません。


フランツ・カフカ
アヴァンギャルドなものや抽象的な絵画は苦手です。
むかーし、テートギャラリーに美大卒の友人と行った時、真っ白なキャンバスに
釘が刺してある絵があって「これのどこがいいわけ?」とたずねたら
「これが芸術だと言いきれるところまでもってきたのがすごい」と言われました。
なるほどって思いますか? 私は思わないのですがうっすらと理解はできます。
正統な基礎が認知されているからこそ、なんのこっちゃ? なものも
豊かな想像力による芸術だと認められる、ってことかしらね?
カフカは私にとってそんな感じです。
物語の始まりは面白く、一語一句も魅力的なのですが、話しが一般常識の粋を超えて
展開していくと理解できなくなってしまうのです。
まったく読み手である私の落ち度であって、カフカに責められる点はありませんが
万人受けするとは思えないなぁ…『変身』はかなり分かりやすい話しですけどね。
そんな中でも、私が比較的理解できたものをご紹介します。
『火夫(Der Heizer)/1912年』

女中を妊娠させてアメリカにやられることになった16歳のポールは
船の中で、虐げられていると嘆くドイツ人の火夫に出会います。
彼を助けようと船長室で熱弁をふるうポールに、ひとりの紳士が叔父だと名乗ります。
『アメリカ』という長篇の第1章にあたる物語です。
これは普通ですが読み進むと意外な展開になっていくのでしょうか?
『アメリカ』は持っているので今度チャレンジしようと思います。
『中年のひとり者ブルームフェルト(Blumfeld,ein alterer Junggeslle)/1915年』

寂しいので犬でも飼おうかと思案しながら帰宅したブルームフェルトは
部屋の中で楽し気に跳ね回るふたつのボールに辟易させれます。
翌朝ボールを振り切って会社に行くと、使えないふたりの部下がさぼりたい放題です。
ボールの部分と会社の部分がまるで別物のようなのですが…
ボールはボールで解決してほしかった、けっこうコミカルだったんですよ。
それなのに会社の部分でどんより暗い話しになってしまって…
『万里の長城(Von den Gleichnissen)/1920年』

万里の長城はなぜ区間分割工法がとられたのか?
君主制や中国の国民性、都会と田舎における皇帝への忠誠の温度差などをとりあげて
論究を試みています。
普通に読むと真面目な論文にみえますし、納得の部分も多いのですが
この1冊に収められていると、もしかして全部つくりごと? と思われてなりません。
歴史家が読んだら抱腹絶倒ものなのでしょうか?
気がついたらカフカも何冊か持っていた私… 『城』とか『流刑地にて』とかね。
短編でこんなことじゃ先が思いやられます

いつか読むつもりですけど、いつだか分かりません。











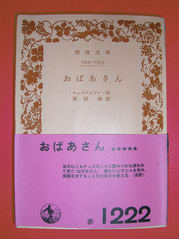


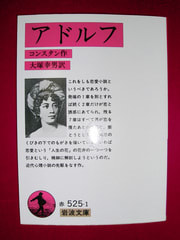


 っていうことで
っていうことで










