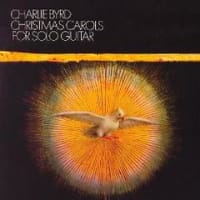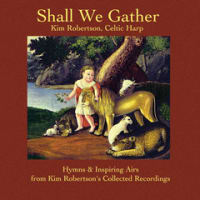”演歌の星・藤圭子のすべて”by 藤圭子
輪島祐介氏の著作、「創られた”日本の心”神話」(光文社新書)は、”演歌は日本人の心の歌である”などという、いつのまにか当たり前のように言われるようになった言葉が本当に実のあるものなのかを疑ってかかり、そもそも演歌は言われるような音楽なのかを検証し直した、大変意義深い本だった。
いかに作り上げられた神話が定説として流通してしまっているかを見事に指摘して見せてくれたこの本で、一九六〇年代から七〇年代への変わり目に、擬制としての演歌の定義が確立される時代を象徴する歌手として登場した藤圭子。彼女のデビュー・アルバム、”★演歌の星・藤圭子のすべて”を、ここで改めて聞いてみた。
そもそも藤圭子なる歌手、今となっては振り返られる事もなくなった。話題になるとすれば、なにやらアメリカのギャンブル年に大金を持ち込もうとした事件とか、あるいは彼女の娘の歌手としての成功談の余談としてでしかない。
七〇年当時は、時代を象徴する「艶歌」の星である、いや、これは「怨歌」である、などと作家・五木寛之まで巻き込んで、なにやら大変な扱いとなったものであるが、その後、歌手としての再評価がなされるでもなし、カラオケの場で彼女のヒット曲が歌われるのも聴いたことがない、というか、歌われそうな空気というものが想像できない状態だ。なにか、あまりにも時代の空気と密着し過ぎる形で評価されたためにその歌は、時が流れ去るとともに強引に時のむこうに押しやられてしまったみたいに見える。
今、ここでこうしてこのアルバムを聴いてみても、懐メロとしての懐かしさもあまり感じない。ただ、”昔、このような歌があった”という感慨が残るのみで、歴史を伝える旧跡を見て回る気分だったりする。
かって五木寛之に、「このように幼い少女がここまで深い表現を」と息を飲ませたデビュー時の藤圭子の歌声も、今、私としては「ロックに出会いそこなったロック少女の歌」などと定義を思いついたりしている次第だ。歌いまわしの独特な癖に、ちょっとした「萌え」を感じたりもしている。まあこれは、時が流れ、そして聞き手の私もそれなりに人生の時を重ねた、という事情あっての話なのだが。
このアルバムが出たばかりの頃、五木の賛辞の尻馬に乗るように、サブ・カルチュアの世界でも藤圭子の歌声は一つの権威として横行してしまっており、私としては鼻白む思いがしないでもなかった。
そんな、あの当時の異様な入れ込み気分に基づく熱に相当するものが今日の我々の社会にはなく、ために”あの頃”の藤圭子の歌声は受け皿もなく、ただ暗闇に響いているだけと感じられる。
そして、これは私の個人的な感想にしかならないのだろうが、そんなアルバムの中で、「柳ケ瀬ブルース」「東京流れ者」と続く二曲に、妙に自分の心が反応するのを感じた。とりあえず私にとってはこの2曲は「生きて」いる、などと勝手なことを言ってみる。
何が違っているのだろう。「柳ケ瀬ブルース」、この歌は、日本中に広がる夜の盛り場のネットワークを伝い、幻のように流れ生きて行く「流し」の演歌師の面影が漂う。一方、「東京流れ者」は、何やら硬派気取りの半端者が粋がった革ジャン姿で夜の都会に繰り出す血の騒ぎが歌われている。
どちらも夜の中で輪郭の定かではなくなった現実の中を幻のように流れる、そんな寄る辺ない魂の彷徨がテーマとなっていると解した。
五木が高い評価を与えた”夢は夜ひらく”のような、時代に楔を穿つような表現とは別方向に、今、流れ出す人影の幻。なにかその先に見えてきそうなのだが、まあ、他なるアルコールの見せた虚妄なのかも知れない。