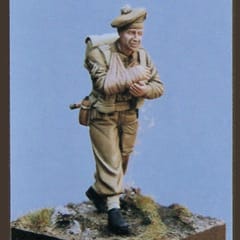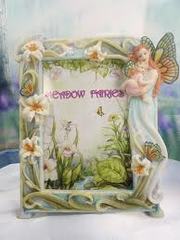先日来、妙な夢に襲われている。
夢の舞台は現代アメリカの、地方小都市のようだ。そこに7~8人の子供たちを持つ、貧しい黒人の一家があり、夢の中で私は、その兄弟の長男のようだ。地味なスーツにネクタイなど締め、どうやら真面目な会社員として、一日の家計を支えているようだ。
窓の外に田園風景が広がる古びた家に住むその一家だが、ある日、その子供たちのうちの次男と三男が、自分たちの兄弟、両親、祖父母など、ともかく一緒に暮らしていた家族全員を惨殺してしまったのだ。そしてそこに、仕事を終えて、何も知らない長男たる自分が帰宅する、という夢だ。
血の池と化した居間や玄関、無残な死体となって転がる家族たち。虚ろな目をして呆然と立ちすくむ”犯人”たる、まだネィーン・エイジャーの次男と三男。彼らの手には凶器となった血まみれの刃物などが握られたままだ。
お前たちはなんということをしてしまったのだ、と怒鳴りつけたいのだが、こうしてしまった彼らの気持ちもわかる、みたいな感情が、夢の中の自分にはある。こうして文章を書いている私には、なんの事情もわからないのだが。
家の惨状、この状況をどうすればいいのだと途方にくれる自分、などといったシーンの断片が何度も繰り返し夢に出てくる。時間はとりあえず、夢の中ではそのシーンのまま、進んでいないようだ。
・・・という夢。夜の夢の中に、これは出てくることはない。日中、退屈している時間、あるいは食後の満腹状態でウトウトしている時など、うたたね状態のつかの間の夢の中に、この悪夢は現れる。相当の緊迫感を持って。目が覚めると、「ああ、夢でよかった」とホッとするくらいの。
なんだろうねえ、この夢。サスペンス映画かホラー映画のオープニングみたいな感じがあるのだが、こんな映画は見た記憶もなし。夢判断で言えば、どうなるのだろうか。
先日来、ちょっと風邪気味で、これ以上悪化しないといいなあ、などと思っているのだが、体調不良のせいかなあ、こんな夢を見るのは。