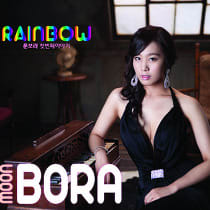”려 (Scent of Trot)”by 유지나( Yujina )
という訳で、もはや我が一推しの韓国トロット演歌歌手と成りました、ユ・ジナ女史の新譜であります。国楽パンソリで鍛えたハガネの喉を武器に、パワフルな演歌を真正面から叩きつける彼女の迫力に私、すっかり参っておるのであります。あ、”最愛の”という表現は、もう少し歌の頼りなくて若い女の子の歌手のためにとっておきますが。ひひんひん。”レインボウ”のボラちゃん、早く次のアルバムを出さないかなあ。
まあ、それはそれとして。私が勝手な事を言うのは良いのですが、ユ・ジナの肝心の韓国での人気はどうなっているのか?などと思っておりましたが、ここに登場した最新盤、ジャケなどちょっとした写真集仕立ての豪華変形ジャケでありまして、ユ・ジナもさまざまに衣装を替え、こちらの目を楽しませてくれます。
肝心の音のほうも、バックにストリングスつきフルバンドをハッシと従え、期待通りの堂々の歌唱を聞かせてくれます。冒頭の温泉小唄調、”善男善女”なる曲が楽しい。
ともかく非常に安定した出来上がりという感じで、一瞬、このまま安定成長を続けると人畜無害な演歌のオバサンになってしまうんじゃないかと危惧の思いも過ぎったんだけど、大丈夫だ。6曲目、ちょうど半分まで行った所に収められた、同じレコード会社のボデイコンイケイケ姐ちゃん、キム・ヤンのヒット曲カヴァー、”愛のショショショ”あたりから様子が変わってきて、ポンチャク的というか、なんでもありの雰囲気になってきた。
ユ・ジナもそれまでの悠然たる歌いっぷりをかなぐり捨て、次の”情深い女”では情緒纏綿たる絶唱を、民謡調の8曲目、”スリラン”では得意のパンソリっぽい唸りも聴かせてくれる。なんか前半が公式サイド、後半が本音サイドって気もするな。
そしてどうやらヒット曲になったらしい9曲目、”空の星を探して”だ。良い曲です。日本では昭和30年代以来死に絶えたみたいな、悠然たる股旅演歌の王道を行く曲。
寄る辺ない放浪者、今夜はどこに体を横たえる。
布団は空、枕は夜露。疲れた体で眠りにつく。
朝日の前に夢の中でお前の星を探すがいい。
アバウトな訳詞なんで突っ込まないように。なんか”生活の柄”みたいな歌詞内容でおかしいね、と言いたかっただけだから。
そして最終曲の”祈る女”、これこそパンソリの流れを汲む地を這うようなスローバラード恨み節、血を吐くような絶唱演歌でありまして、うっわー聞いてるうちに、猛烈に酒が飲みたくなって来た!突然ですが、これで終わらせていただきます。
という訳で、もはや我が一推しの韓国トロット演歌歌手と成りました、ユ・ジナ女史の新譜であります。国楽パンソリで鍛えたハガネの喉を武器に、パワフルな演歌を真正面から叩きつける彼女の迫力に私、すっかり参っておるのであります。あ、”最愛の”という表現は、もう少し歌の頼りなくて若い女の子の歌手のためにとっておきますが。ひひんひん。”レインボウ”のボラちゃん、早く次のアルバムを出さないかなあ。
まあ、それはそれとして。私が勝手な事を言うのは良いのですが、ユ・ジナの肝心の韓国での人気はどうなっているのか?などと思っておりましたが、ここに登場した最新盤、ジャケなどちょっとした写真集仕立ての豪華変形ジャケでありまして、ユ・ジナもさまざまに衣装を替え、こちらの目を楽しませてくれます。
肝心の音のほうも、バックにストリングスつきフルバンドをハッシと従え、期待通りの堂々の歌唱を聞かせてくれます。冒頭の温泉小唄調、”善男善女”なる曲が楽しい。
ともかく非常に安定した出来上がりという感じで、一瞬、このまま安定成長を続けると人畜無害な演歌のオバサンになってしまうんじゃないかと危惧の思いも過ぎったんだけど、大丈夫だ。6曲目、ちょうど半分まで行った所に収められた、同じレコード会社のボデイコンイケイケ姐ちゃん、キム・ヤンのヒット曲カヴァー、”愛のショショショ”あたりから様子が変わってきて、ポンチャク的というか、なんでもありの雰囲気になってきた。
ユ・ジナもそれまでの悠然たる歌いっぷりをかなぐり捨て、次の”情深い女”では情緒纏綿たる絶唱を、民謡調の8曲目、”スリラン”では得意のパンソリっぽい唸りも聴かせてくれる。なんか前半が公式サイド、後半が本音サイドって気もするな。
そしてどうやらヒット曲になったらしい9曲目、”空の星を探して”だ。良い曲です。日本では昭和30年代以来死に絶えたみたいな、悠然たる股旅演歌の王道を行く曲。
寄る辺ない放浪者、今夜はどこに体を横たえる。
布団は空、枕は夜露。疲れた体で眠りにつく。
朝日の前に夢の中でお前の星を探すがいい。
アバウトな訳詞なんで突っ込まないように。なんか”生活の柄”みたいな歌詞内容でおかしいね、と言いたかっただけだから。
そして最終曲の”祈る女”、これこそパンソリの流れを汲む地を這うようなスローバラード恨み節、血を吐くような絶唱演歌でありまして、うっわー聞いてるうちに、猛烈に酒が飲みたくなって来た!突然ですが、これで終わらせていただきます。