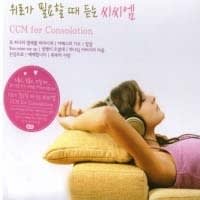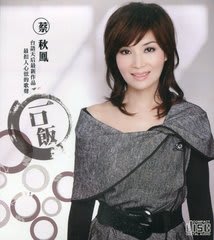”YOU KERE YOU WOWO”by TUNDE NIGHTINGALE
トゥンデ・ナイチンゲール(1922-1981)なるジュジュ・ミュージックのアーティストに関しては、サニー・アデがワールドミュージック・ブームの波に乗って世界を舞台に飛躍を始めたその頃に聴いたことはあった。当時、通っていたレコード店の店主氏が当時としては入手が非情に困難だったらしいナイチンゲールの盤をカセットに入れて、「参考までに」とプレゼントしてくれたものだった。
とりあえず、ナイジェリアのローカル・ポップスたるジュジュ・ミュージックが成熟して行く過程で、オリジネイターがおりエレクトリック化の旗手がおり、といった流れの中の、新旧世代の橋渡しのようなポジションにいた人とか、そんなぼんやりとした理解があったが、それで正しいのかどうか、いまだに分からない。
聴いてみたその音は、正直言ってかなり退屈で、世界を舞台にゴージャスなジュジュ・ミュージックを叩きつけるアデたちに比べると、昔ながらのハイライフ音楽の尻尾をくっつけた古臭い音楽としか思えなかったのだった。
そんな時代もはるか彼方に去った今。ほんの気まぐれで久しぶりに聴いてみたトゥンデ・ナイチンゲールの音楽は、あれあれなんだか不思議に心惹かれるものがあり、一発ですっかりファンになってしまったのだった。時の流れはいろいろなものを変える。
そのナイチンゲールなる芸名のいわれなのだろう甲高い鄙びた歌声は、奇妙にすっとぼけた鄙びたファンキー感覚を伝えて来て、ワイルドに刻まれるギターと、ナイジェリア名物トーキング・ドラムとの絡み合い織り上げるリズムも心地良く、実に心地良くこちらの疲弊した心をマッサージしてくれる。
なんとも愛嬌のあるサウンド展開に身を任せているうちに私の脳裏に浮かんできたのは、昔読んだ赤塚不二夫の漫画に出てきたチビ太の姿だった。いつも串に刺したオデンを片手に掲げ、走り回っていた下町のガキの姿。なんだかあれとナイチンゲールの音楽が二重写しになって来た。ビンボにもめげずに無心に遊びまわる少年の幼いバイタリティの発露と、甲高いがゆえに醸し出される”成長を拒んだ子供”的雰囲気が独特の邪気となって放出されているナイチンゲールの音楽世界に、通ずるものがあるような気がして来た。
それからこれは、無茶な話なんで小さな声で言うのだが、そのギター・サウンド、フレーズの作りや曲自体の構造の奥には、なにやらロック・ミュージックに通ずるようなエッジの鋭さを時に感じたりもする。
いやまあ、ナイチンゲールの生年から言って、そんな音楽の影響があるはずはないんだけどね。
全体的にナイチンゲールの音楽って、マンガっぽくないか?それも、昔あった貸し本屋の安っぽくも暖かい、懐かしいマンガ本のイメージ。なんて、限定された層にしか通じないような事を、まあ、言いたかったわけですな。すいません、長くなりすぎたんで、ボロボロのままですが話を終えます。