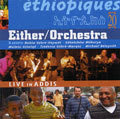エチオピア音楽に関しては、結局、甲斐のない期待をさせられてしまったのかなあと、妙なむずがゆさを覚える私である。というか、これはエチオピア音楽界にしてみれば勝手なインネンをつけられる、といった性質の不満であり、責任はあちらにはない。私にも多分、ないと思うのだが。
あれはもう20年も前の話になろうか。エチオピアにも(当然)面白い音楽があるようだ、なんて情報が断片的にもたらされ始めた頃。私はそこに記された現地情報に好きものの血を大いに騒がされたものだった。いわく。
「エチオピアの空港に降り立つと、日本人はかなりの驚きを感じるであろう。あちこちから聞こえてくる音楽が、まるで日本の演歌の如くであるからだ。何かの間違いと思いつつタクシーに乗ると、空港からホテルに至る道のりで、カーラジオから聞こえて来るのはエチオピア語の、どう聞いても日本の演歌。それどころではない、現地のカセット・ショップでは、エチオピア版の三波春夫や村田英雄の作品に出会うという、さらなる驚異が用意されているのだ」
そんな文章だった。
これは面白そうではないか。アジアから中東を経てきたアフリカに至る、広大なイスラム圏のコブシ音楽ベルト(?)を思えば、そのような音楽がエチオピアの地に存在すること、何も不思議ではない。
おお。早く聴きたい。どれほどそれは日本の演歌に似ているのか。どの部分が似ていないのか。などと言っているうちにも、エチオピアの隣国、スーダンに存在する、あの河内音頭に極似した音楽が、ヨーロッパのワールドミュージック関係のレーベルから紹介される。おいおい、これはますます気になるじゃないか。
と気ばかり焦れども、音の実物が入ってこない。ちょっと現地に行って聴いてみるというにはアフリカの地はあまりに遠し。だがまあ、それほど興味深い音楽であるならば当然、わが国にも大々的に紹介される日は来るに違いない。のんびり待とうと私決めた。というか、そうするしかなかったのであるが。
が。月日は流れども、エチオピア演歌のわが国への紹介はなされず。つい最近になってから、エチオピア音楽の黄金時代のレコーディングがシリーズ化され紹介されているのだが、そしてそれは十分に興味深い音楽ではあるのだが、それは冒頭に紹介した音楽ライター氏によるエチオピア音楽紹介文にあった、”日本の演歌そっくり”の物件ではない。演歌に似ていると言える部分もないとはいえない音楽ではあるのだが、三波春夫ではない。村田英雄でもない。
あの文章は何だったのかなあ。知り合いの輸入レコード店主に尋ねても、この件に関しては私といい勝負の知識量の彼であり、「なんだったんでしょうね?そんな音楽がエチオピアのどこかにまだ未紹介であるのかなあ」などと首をかしげるばかり。
お立会い。この”演歌の国、エチオピア”に関する情報をお持ちではありませんか?お持ちでしたらご教示願えれば幸いです。しかし、いるのかなあ、ほんとに。エチオピアの三波春夫。村田英雄。あの記事を書いたライターのでっち上げだったら怒るぜしかし。20年越しで無駄な期待をさせられたんだからなあ。
(画像は、昭和初期から高知県で”土佐名物”として売られていると言う”エチオピア饅頭”のパッケージ。銘々の理由は、寡聞にして知らない)