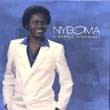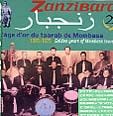”Studio Cameroon”
by Sally Nyolo and the Original Bands of Yaounde
明けましておめでとうございます。
さて、新春初聴きはこれ。アフリカはカメルーンのベテラン女性歌手、サリー・ニョロのプロジェクトによる実験作です。かの地の伝承音楽を基にした、創作ポップス集。アフリカど真ん中の地に根ざした、カラフルな不可思議サウンドが楽しめます。
使用楽器も、ギターやドラムやシンセの絡むものから、ほぼ民族楽器のみ、みたいな素朴なものまで。でも、ちゃんと統一感があって、全体で一つのサウンドと聴けますな。
といってもややこしいお芸術作品やハッタリかました”世界を標的”の商品じゃなく、彼女が身近かなカメルーンの伝承音楽を基に遊んでみた新しいサウンドの試み、といったところ。欧米から白人のプロデューサーなんかが”降臨”して、現地の音楽を勝手にいじくり回したわけじゃないんで、奔放ながらもなかなかに人懐こい暖かい音が楽しめます。
特に冒頭の3曲などは、使われている音階の日本民謡との近似性や、漂うユーモア感覚など、なんというか”子供好き”のするひょうきんな音なんで、このままNHKの”みんなの歌”とかで流しても通用してしまうのではないかって気がします。
アルバムの主催者、サリー・ニョロって、この作品を聴く限りでは結構インテリの人じゃないかって感じがするんだけど、それが冷たい方に作用せず、むしろ”機知に富む”という形で音楽に投影されている、それが良かったみたいですな。先にあげた冒頭の数曲などに現われたユーモアの感触も、その現われではないでしょうか。
ともかく、まだまだアフリカから楽しめる音は出てきそうだなと、これを聴いて安心した次第。