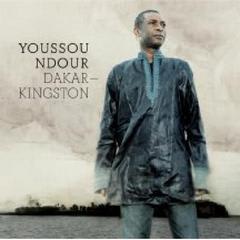”THE MBIRA MUSIC OF GOLDEN NHAMO ”
南部アフリカにジンバブエなる国があるが、確かこの国名は「石の家」と言う意味であったと記憶している。この国に古くから存在する石造建築物にちなんだものと聞いている。
ジンバブエはまた、ブラック・アフリカ全域において使われている親指ピアノの音楽のとりわけ盛んなところであるが、上のような話を聴いた連想から、かの国のミュージシャンが演奏する親指ピアノを聴くたびに、ごろんと横たわる石塊に向って思索を行なう哲学者、みたいなイメージが浮んで仕方がなかったりする。
永久の時間を沈黙して過ごして来た岩石に向って、人生の意義や宇宙の謎について楽器をかき鳴らしつつ問う、寡黙な哲学者。ここに紹介するゴールデン・ナモもまた、ジンバブエの哲学者の面影漂う(まあ、私が勝手に夢想しているだけだが)親指ピアノのプレイヤーである。
その人生の前半分を軍人として過ごし、司令官なる地位にまで上りつつも、突然その職を辞し、故郷に帰って親指ピアノのプレイヤーとしての研鑽に務めた、などという戦国時代の変わり者の武将みたいなエピソードもまた、彼の思索家イメージを深める。
その演奏自体もアブストラクトというのか、彼独自の不思議な手触りを持っている。アフリカ大陸では当たり前のように聞こえる複合リズムの一種ではあるが、他のミュージシャンの演奏とは一味違う奇妙に歪んだリズム構成と、それに乗って織りなされる聴いたこともないような和音の響き。
その、まるでクラシック音楽のフィールドで”現代音楽”と呼ばれるジャンルの作曲家が作りでもしたような、ある種不安定な構成の楽の音。それは、遠くジンバブエを離れて生きる我々の今の心境にもぴったりとフィットする、非常に今日的な先鋭的な響きを奏でている。
興味深いプレイをもっともっと聴きたいと願うのだが、残念ながら演奏者のナモは、この、彼にとってはじめてのアルバムが世に出た年の暮れ、ほんの短い患いの後、世を去ってしまっている。まだ50代の若さであった。
このユニークな演奏家が形として残した音楽遺産が、あまりにも少ないことに唖然としてしまうのだが、せめて彼の残したこのアルバムを聴き込み、彼の残した謎の回答へと一歩でも近尽きたいと願うのみである。