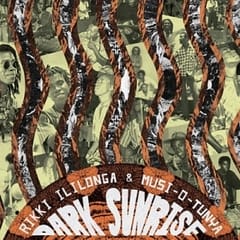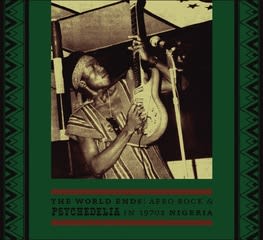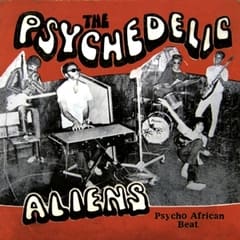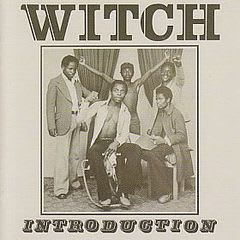”RAW ELECTRIC BLUES FROM BAMAKO, BWATI KONO”by LOBI TRAORE
70年代あたりを中心に、ということでいいのだろうか、かってアフリカの各ローカル・シーンでだけ愛好されていた地域ポップス、ロック&ファンクなどのレコーディングが、あの”アナログ・アフリカ”のシリーズなどにより、もはやブームと言っていいような勢いで発掘されている。
それらは続々とCD復刻されているが、そのどれもが非常に刺激的な出来上がりとなっており、どの盤からも目を離すことが出来ない。
特に当時、アフリカ独特の解釈で演奏されていたロック・ミュージックという奴が私には非常に魅惑的に感じられ、これまで描いてきたアフリカ音楽のビジョンを再検討するべきではないかと思い始めているのだった。
もう、「アフリカに先祖がえりしたアフロ・キューバン音楽がアフリカ的洗練を加えられ」なんて悠長で聞き飽きた話はどうでもいのであって。カッコいいじゃないか、アフリカのロック!猥雑なパワーと素っ頓狂とも云いたいイマジネーションに支えられて荒れ狂う黒いサイケの嵐!
それはいいのだが。これら、70年代や80年代に咲き誇ったロックの花々は結局どうしたのだ?今日、これらの音楽の後継者と言えるようなサウンドは、アフリカの最前線からは聴こえてこない。あれらは結局、アフリカの大地を覆う古きハイライフやリンガラの密林の片隅で、ひととき咲き誇ったアダ花として消え去ってしまったのか。(もちろん、その一方で”音楽どころではなかった国情”というシビアな現実もあったのだが)
そんな訳で、70年代のアフロロックのミュージシャンたちがその実力を十分に発揮する機会を得ていたらどんな音楽を今頃、やっているのだろうなんてことは想像するしかないのだが、たとえばこのロビ・トラオレあたりに、その幻想を当てはめてみるのも一興かも知れない。
この1960年代、西アフリカはマリ出身のギタリストは、アフリカ版のジミヘン、なんて持ち上げられ方をして、だから見ろ、先日、ジミの真似して早逝をしてしまったじゃないか(おいおい)
まあジミヘンはともかく、非常にイマジネイティブなロックギターを聞かせてくれるプレイヤーであったのは確かだろう。現地の民俗楽器であるジェンベ&バラフォン(木琴)を加えたバンドはワールドミュージック的興味をかき立てるが、ロビの各種エフェクターをかけて音を変形させたエレキギターのフレーズが宙を舞いはじめると、そんなものはどうでも良くなってしまう。
そのゆがめられ、ひしゃげられた不良な弦の響きはようするに”ロック”なのであって、それで十分。その土地の民族色なんてちまちましたものは、もはや彼の飛翔のためのカタパルトでしかない。
きっとトラオレはガキの頃の私と同じように、あの退屈な田舎の街の夕暮れに、どこからか流れてきたサイケな最新のロックに胸ときめかしていたに違いないんだ。飛べ、トラオレ。宇宙の彼方まで。
・・・などと思ってみるトラオレのいない春の夜。