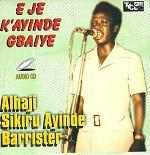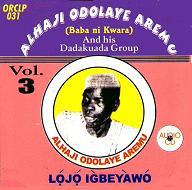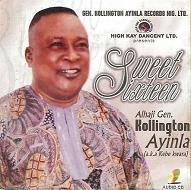"Isese L'agba" by Asabioje Afenapa
ナイジェリアの女性歌手のアルバム。ジャケ写真の印象が、あのビヨンセの振り真似をやる日本の女芸人に似ていて、ちょっと面白い。
さっき、検索をかけてみたのだが、複数の人がこのアルバムをブログで取り上げている。が、その文章がどちらも、「ヨルバの伝統音楽」とか「ドスの聴いたいい声」とか「キズだらけながらも音とびもなく聴けるCD」など同じ文章、同じ内容、同じような長さであるのはなぜだ?謎ですわねえ。
で、伝統だかなんだか知らないけどさ。聴いた感じ、これまで馴染んできたナイジェリアのヨルバ民族によるイスラム系大衆音楽、フジやアパラなんかに通じる構造の音楽だ。パーカッションのアンサンブルとラフでディープなコーラスをバックに、コブシたっぷりのボーカルがうねるように流れて行く。
ただこのアルバムの歌手は、やたら明るい芸風の人で、そのスコンと空に突き抜けるような歌声は、フジやアパラの持っている地の底から聴こえて来るような、ある種不気味さとは逆の、ずいぷんポジティブなメッセージを伝えてくる感じだ。
欧米の通販レコード店の紹介文には、”The inspirational and spiritual traditional Yoruba music that opens gates for prayers to Olodumare (God) ”なんて書いてある。宗教的なバックグラウンドがある音楽なんだろうか。
ともあれ。その洗いざらしみたいな感触がなにやら眩しい、私にしてみれば意外な手触りの一作であるのでした。