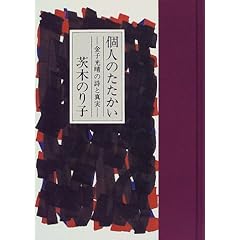池澤夏樹の独特のファンタジー。
偶然に一箇所に集まった子どもたちの共同生活。鉄道の世界、死とは何かを問いかける。
切手収集が趣味の小学生、イタル(遠山至)が有楽町にある切手店に行こうと有楽町で改札を出ようとしたがキップがない。
女性のフタバコに呼びかけられ、東京駅にある詰所に連れて行かれると、そこには大勢の子供たちがいた。彼らは改札をくぐって外に出ることなく、そこで生活している。食事は駅構内の食堂で、必要なものは持ち主のいない遺失物でまかなっていた。電車は乗りたい放題。そして、彼らは駅員さん、車掌さん、食堂のおばさん、キオスクのおばさんに見守られながら生きている。そして、彼らの仕事は、登校する小学生が安全に学校に通えるように、プラットフォームや電車のなかでのトラブルにあわないように、また危険なときには超能力で時間をとめて助けること。
彼等は人呼んでステーション・キッズ。ユニークな連中ばかりだ。ちょっと変わった集団で、変わり者がたくさんいた。フタバコさん、ロック、ポック、フクシマケン、タカギタミオ、ユータ、いつも一緒の緑、馨、泉。
その中にミンちゃんという女の子がいて、ほとんど何も食べない。駅長さんに聞くと、彼女はプラットフォームから落ちで轢死したのだった。まだ、あの世に往けないで、詰所で暮らしていた。
イタルはミンちゃんと一緒に目白に住むお母さんに会いにいく。そして、お母さんとの出会いのあと、ミンちゃんは北海道のグランマのところに行くといいだし、これが発展してステーション・キッズ皆なの旅行に。日高の方面の春立、というところでミンちゃんとはお別れ。彼女はもうひとつの世界にグランマに手をひかれて旅立っていった。キッズは東京に帰って解散。自身の家のドアを叩くのだった。
こんな筋です。久しぶりに魂が子どもの世界に戻ったような気がしました。切手のコレクションとか、蒸気機関車とか、駅弁とか・・・。懐かしいものがたくさん出てきます。しかし、設定は特殊な空間。テーマは「死」です。