○京都国立博物館 特別展覧会『宸翰(しんかん)天皇の書-御手(みて)が織りなす至高の美-』(2012年10月13日~11月25日)
企画を知った時から友人と「渋いよね~」と言い合っていた。臆面もなく、こういう展覧会を開いてしまう京博が大好きである。分かりやすい「鑑賞ガイド」を置いたり、いろいろ工夫をしているけれど、どう考えても入館者数狙いの企画とは思えない。
構成は、まず「宸翰のかたちと種類」で、時代を無視して名品に触れ、典型を学ぶ。後陽成天皇の大字「龍虎」「梅竹」は分かりやすくていいなあ。→次、早くも「書の手本 三筆と三跡」。空海の平素の走り書き(六行分)の断簡が美しくて見とれる。行成の『書簡(本能寺切)』は「水」や「楽」の字が優美で好き。「伝・行成筆」ばかり見ていると、印象が混乱してこのひとの真価が分からなくなってしまう。意識して真筆だけ見るように心がけたい。ここは同時代(平安前期)の天皇の宸翰として、後朱雀天皇の短い消息が展示されているが、これともう1点しか伝わらないそうだ。真面目そうな人柄のしのばれる筆跡である。「当今御筆 長久五年」という添え書きも同時代人によるのだと思うと、感慨深かった。
次「宸翰様のはじまり」→「きらめく個性」と続き、嵯峨、高倉、後白河、後鳥羽、花園…と、書風も人柄も(治世の有り様も)個性豊かな天皇が次々登場。嵯峨天皇って「三筆」の一人に数えられているけど、『光定戒牒』が唯一の遺墨なのか。楷書・行書・草書を自在に行き来する見事な筆跡だが、巧みすぎて厭味に感じられるのは、乾隆帝みたいだ。近衛家熈がこれを双鉤填墨で写しているが、臨模にしか見えない。すごい。
私は高倉天皇の「唯一の遺墨」だという消息に惹かれた。異母兄の守覚法親王に宛てたもので、平明で穏やかな筆跡である。身内宛てのせいか、癖のある書体を隠そうとしていないところに好感が持てる。
後白河院は例の『文覚四十五箇条起請文』、後鳥羽院も『御手印置文』。後白河院の手形が、長い指を行儀よく揃えているのに対し、後鳥羽院は、指の間を広げて、ぺたりと両手を押しあてているのが、なんだか生々しい(死の直前だったと言うしな)。花園天皇の書風はいいな~。
中央の大展示室では「書の達人 伏見天皇」を特集。和漢の書を自在にこなしたというが、前期は漢文が目立つ。後期(11/6~)は、もう少し仮名文字が増えるようだ。ただし、小野道風筆『屏風土代』と伏見天皇による臨模を並べて見ることができるのは前期のみ。なぜか、漢詩の順序が一致しないのが不思議だった。
後半「個性を受けつぐ」→「新しい書を求めて」は南北朝に入る。後醍醐天皇を筆頭とする「情熱の赤」の南朝の書風、「理知の青」の北朝の書風が合体して「個性の紫」を生み出す、という見立てが面白かった(いま記憶で書いているので、間違っていたらすみません)。私は、光厳、崇光など北朝の書をいいと思った。どんな生涯をすごし、どんな事蹟を残した天皇か、よく知らなくても、遺墨を見ていると、不思議になつかしく感じられてくる。
最後の「新時代の書」は、江戸から一気に近代まで。大正天皇の一行書「仁智明達」が素晴らしくいい。床の間に飾りたい。最後は昭和天皇で〆る。
あまりに面白くて、時間の経つのをすっかり忘れた。非常に多くの宸翰を残している天皇もいれば、わずか1点、または数点しか残していない天皇もいるんだなあ、と初めて知った。時代によるわけでもなく、必ずしも生涯の長さや書の巧拙によるわけでもないらしい。それと、仁和寺が「天皇家のアーカイブ」として果たしてきた役割の大きさを感じた。
開館(9:30)とほぼ同時に入ったのだが、気がつけばもう12時過ぎ…。がーん。大津歴博行きは断念。強くなってきた雨空を見ながら、次の行き先を考える。
企画を知った時から友人と「渋いよね~」と言い合っていた。臆面もなく、こういう展覧会を開いてしまう京博が大好きである。分かりやすい「鑑賞ガイド」を置いたり、いろいろ工夫をしているけれど、どう考えても入館者数狙いの企画とは思えない。
構成は、まず「宸翰のかたちと種類」で、時代を無視して名品に触れ、典型を学ぶ。後陽成天皇の大字「龍虎」「梅竹」は分かりやすくていいなあ。→次、早くも「書の手本 三筆と三跡」。空海の平素の走り書き(六行分)の断簡が美しくて見とれる。行成の『書簡(本能寺切)』は「水」や「楽」の字が優美で好き。「伝・行成筆」ばかり見ていると、印象が混乱してこのひとの真価が分からなくなってしまう。意識して真筆だけ見るように心がけたい。ここは同時代(平安前期)の天皇の宸翰として、後朱雀天皇の短い消息が展示されているが、これともう1点しか伝わらないそうだ。真面目そうな人柄のしのばれる筆跡である。「当今御筆 長久五年」という添え書きも同時代人によるのだと思うと、感慨深かった。
次「宸翰様のはじまり」→「きらめく個性」と続き、嵯峨、高倉、後白河、後鳥羽、花園…と、書風も人柄も(治世の有り様も)個性豊かな天皇が次々登場。嵯峨天皇って「三筆」の一人に数えられているけど、『光定戒牒』が唯一の遺墨なのか。楷書・行書・草書を自在に行き来する見事な筆跡だが、巧みすぎて厭味に感じられるのは、乾隆帝みたいだ。近衛家熈がこれを双鉤填墨で写しているが、臨模にしか見えない。すごい。
私は高倉天皇の「唯一の遺墨」だという消息に惹かれた。異母兄の守覚法親王に宛てたもので、平明で穏やかな筆跡である。身内宛てのせいか、癖のある書体を隠そうとしていないところに好感が持てる。
後白河院は例の『文覚四十五箇条起請文』、後鳥羽院も『御手印置文』。後白河院の手形が、長い指を行儀よく揃えているのに対し、後鳥羽院は、指の間を広げて、ぺたりと両手を押しあてているのが、なんだか生々しい(死の直前だったと言うしな)。花園天皇の書風はいいな~。
中央の大展示室では「書の達人 伏見天皇」を特集。和漢の書を自在にこなしたというが、前期は漢文が目立つ。後期(11/6~)は、もう少し仮名文字が増えるようだ。ただし、小野道風筆『屏風土代』と伏見天皇による臨模を並べて見ることができるのは前期のみ。なぜか、漢詩の順序が一致しないのが不思議だった。
後半「個性を受けつぐ」→「新しい書を求めて」は南北朝に入る。後醍醐天皇を筆頭とする「情熱の赤」の南朝の書風、「理知の青」の北朝の書風が合体して「個性の紫」を生み出す、という見立てが面白かった(いま記憶で書いているので、間違っていたらすみません)。私は、光厳、崇光など北朝の書をいいと思った。どんな生涯をすごし、どんな事蹟を残した天皇か、よく知らなくても、遺墨を見ていると、不思議になつかしく感じられてくる。
最後の「新時代の書」は、江戸から一気に近代まで。大正天皇の一行書「仁智明達」が素晴らしくいい。床の間に飾りたい。最後は昭和天皇で〆る。
あまりに面白くて、時間の経つのをすっかり忘れた。非常に多くの宸翰を残している天皇もいれば、わずか1点、または数点しか残していない天皇もいるんだなあ、と初めて知った。時代によるわけでもなく、必ずしも生涯の長さや書の巧拙によるわけでもないらしい。それと、仁和寺が「天皇家のアーカイブ」として果たしてきた役割の大きさを感じた。
開館(9:30)とほぼ同時に入ったのだが、気がつけばもう12時過ぎ…。がーん。大津歴博行きは断念。強くなってきた雨空を見ながら、次の行き先を考える。

















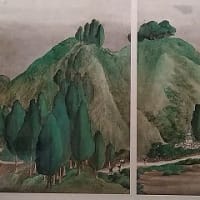
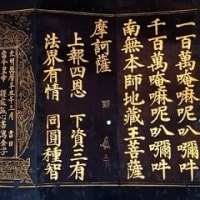
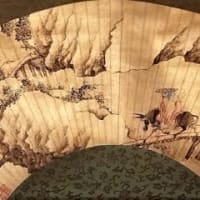





印象に残ったものを列記すると、まず、桜町天皇が妙心寺に賜った諡号勅書は、実に見事で、とても16歳の少年の手とは思えない字で感動しました。桜町天皇の少年期と青年期の比較なども精進されたことが良くわかり面白かったです。
逆にこう申してはなんですが、明治天皇は、かなり御歴代の中では、例外的な悪筆で驚きました(何か斜めに書く癖があるような・・・)。
また、大正天皇の一行書は確かに良いですね。また、日本外史の書き込みは、よく展示できたものと驚きました。他人に見せることを意識しない普段の字が良くわかり面白かったです。
昭和天皇が妙心寺に賜った「無想」の号は、禅僧のような字でこれも良い意味で意外でした。
紹介文がなかったら、恐らくいかなかったと思います。ありがとうございました。