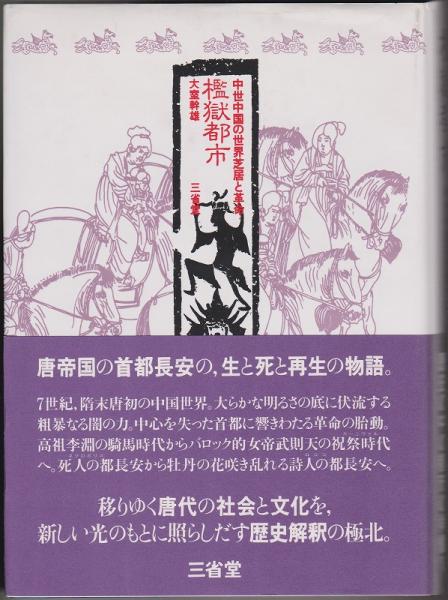〇高口康太『中国「コロナ封じ」の虚実:デジタル監視は14億人を統制できるのか』(中公新書ラクレ) 中央公論新社 2021.12
 2020年に始まったコロナ禍は、地球規模のパンデミックとなったため、各国の保険医療や政治体制の違い、さらには文化の違いについて、いろいろ考える機会になった。
2020年に始まったコロナ禍は、地球規模のパンデミックとなったため、各国の保険医療や政治体制の違い、さらには文化の違いについて、いろいろ考える機会になった。
本書は、中国がいかにしてコロナを封じ込めたか、その手法、体制について検討したものだ。中国の「コロナ封じ込め」に疑いを持つ人もいるが、著者は中国の「成功」を是認する立場である。ただし「上に政策あらば下に対策あり」の中国で、人々に外出自粛やロックダウンを守らせるのは容易なことではない。中国人のしたたかさを知るがゆえに、この成功には、驚きが大きいという。
日本ではその答えを、デジタル技術を駆使した監視社会に求める人も多い。しかし、実際にはドローンやVRの活用はまれで、封鎖式管理の実務に動員されたのは「社区」の居民委員会(農村では村民委員会)だったという。建国直後の単位(ダンウェイ)や人民公社に代わって、1980年代以降、社会サービスを担ってきた組織である。日本の町内会に近いけれど、国から給与を貰う公務員でもある。ちなみに台湾にも、里(村)という類似の基層自治体があるそうだ。中国では、2010年代から、さらに社会サービス/社会管理の密度を増す「網格(グリッド)化」を進めており、コロナ対策には、全土で450万人近い網格員が動員されたという。ちょっと古代の保甲制を彷彿とさせる。
デジタル技術も大動員を支えた。ひとつは「本人確認」で、中国ではすべての行政データが国民IDに統合され、携帯電話番号とも紐づけられている。国民IDの導入に成功したのは、韓国、台湾、エストニアなどの後発福祉国家で、アメリカやイギリス、日本などの先発福祉国家は、行政サービスごとに個別の管理体系が構築されており、統合にはコストがかかる上に、市民にとってのメリットが乏しいのだという。つらいなあ。
あまり上手くいっていなかった「データ共有」も、コロナによって一気呵成に進展した。「省人化」や「不正防止、エラー防止」も同様である。隔離期間中、はじめはチャットで体温を報告する方式だったものが、途中から入力フォームが設けられたり、紙に訪問者の名前や電話番号を記録する方式から、QRコードの読み取りに変わったり、小さな改善が次々に実現しているのはうらやましい。ただ、デジタルサービスを使いこなせない中高年の存在は、悩ましい社会問題だという。また、IT企業の巨大な実力を知ってしまった中国共産党が、これからIT企業をどのように扱っていくかという問題提起には、かなり不穏な匂いがする。
次に、デマと世論の統制について。2020年1月、新型コロナウイルスにいち早く警鐘を鳴らした李文亮医師が行政処分を受ける事件が起きた。李医師は2月にコロナ感染により死亡。その後、中国政府は李医師を英雄として表彰している。本書によれば、李医師が情報を流したのは、同僚医師グループのクローズドなチャットだったのに、政府の監視システムに引っかかったのだという。怖い。
しかし、正しい情報を握りつぶしたことが批判されているが、ネットには1つの真実とともに99のデマが流れていた。社会秩序を守るため、ネット監視と迅速なデマ潰しは必要なのだ。これは『三体』の作者、劉慈欣の発言(大意)である。確かに近年、言論の自由が保障された日本やアメリカ、イギリスなどで、とんでもないデマやフェイクニュースが広がり、社会秩序を動揺させる事態を見ていると、劉慈欣の発言に同意したくもなる。
しかし、やっぱり怖いといえば怖い。今や中国政府のネット検閲はますます巧妙になり、「検閲されている」ことすら気づかないうちに、予防的にトラブルの芽が摘み取られていく。なお、こうしたネット世論対策は、政府が開発した技術ではなく、民間企業によって育て上げられたテクノロジーに依存しているという指摘は興味深い。中国社会のいわゆるラスボスは誰なのか?と考えさせられる。
習近平政権は、社会の「正能量(ポジティブエネルギー)」の増進を目標に掲げており、ここから、デマ・邪教・ポルノなどの撲滅、さらにアイドル経済抑え込み等の政策が導き出されている。中国民衆が清く正しく生きることが、統治者の徳(統治能力)と支配の正当性の証明になる、というのは、脈々と続く中国の伝統文化なのだろう。こういう文化圏に生きるのは、民衆も統治者も、つくづく大変だなあと感じた。