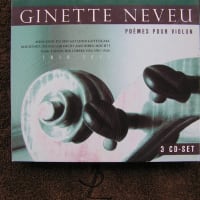3週間ほど前に訪問させていただいた四国の「AXIOM80」の愛好家「S」さん宅の音について、ブログの中でどう表現しようかと、ほんとうに迷った。単に「とてもいい音でした」では芸がないので(笑)。
そこで、苦し紛れに「音楽&オーディオは直接的な感覚の世界なので基本的に言語表現には適しておらず、何を言っても正鵠を射ていない気がする」と予防線を張ったところ、すかさず当事者の「S」さんから次のようなメールが届いた。(抜粋)
「音の表現ほど難しいものはないと思っています
ワインのソムリエが「干し草のような」「キノコのような」と表現すると
そこには一種の共通認識があるおかげで 言葉からある程度イメージが可能なのですが 音の表現となると・・・
Axiom80の音を言葉で表現した若き瀬川冬樹氏はやはり名を成しただけあって 言語化が上手だったと思います
モナリザだって嫌いな人もいるでしょうから 皆 それぞれ 自分の好きなものを追い求めるしかないようで 理想の音は こうありたい自分を反映しているかもしれません
感覚過敏気味の自分にはaxiom80が相性が良かったのかもしれませんが
おおらかに ゆったりと余裕のあるヒトになりたくもあり 普通の音を目指しつつ 毒(狂気)が同類には匂いでわかるといったところでしょうか」
以上のとおりだが、たしかに仰る通り「瀬川冬樹」(故人:オーディオ評論家)さんの表現力は別格でしたね。丁度いい機会だとばかり次の画像の本を読み直してみたところ、ただただ頷くばかり。
たとえば、20頁にこういう表現があった。
「その音が鳴ったとき、わたくしは思わずあっと息を飲んだ。突然リスニングルームの中から一切の雑音が消えてしまったかのように、それは実にひっそりと控えめで、しかし充足した響きであった。
まるで部屋の空気が一変したような清々しい音であった。わたくしたちは一瞬驚いて顔を見合わせ、そこではじめて音の悪夢から目覚めたようにローラ・ボベスコとジャック・ジャンティのヘンデルのソナタにしばし聴き入ったのであった。」といった調子。
ところで、どうしてこういう話題を持ち出したかというと、最近読破した「思索紀行」(立花隆)の中の「ワインの香りと味」についての表現が実に豊かなんですよね~。
たとえば、抜き書きしてみると、
✰ ワインのプロの間では試飲の仕方が完全に様式として確立されている。そして言葉で匂いと味わいを表現しなければならない。さらには、その表現力をどれだけ身に付けているかで「匂いと味きき」の能力が試される。
✰ 匂いの表現方法にはなんと百種以上ある。たとえば天然の香りが次々にあげられ、初めはたいてい花の香りから始まる。スミレ、ジャスミンなど、あらゆる花の名前が登場してきて、次に果物の香りとしてリンゴ、イチゴさらにはアーモンドなどのナッツ類も登場する
ほかにも、本書では「味覚」「嗅覚」の表現の豊かさについて事細かに述べられているが、それに比べると「聴覚=音」の表現の貧しさについては嘆かざるを得ない。
たとえば「スミレの香りみたいな音」といってもチンプンカンプンですよね(笑)。
したがって「音の表現」についてもワインのように様式として確立し、もっと豊かで感覚的に分かりやすい表現ができないものかといつも思う。
ちなみに、「音」に関して常用される言葉としてはアトランダムに「光沢」「色艶」「彫琢」「奥行き感」「スケール感」「透明感」「いぶし銀」「色気」「音像定位」「原音」などで、ほかにもいろいろありそうだがすぐには思い浮かばない。
そういえば、2年ほど前のブログで「ドレミの7音は虹の色」と題して投稿したことがある。
要約すると「音を聴くと色を思い浮かべる特殊な知覚「共感覚」の持ち主が感じる「ドレミファソラシ」の7音の名前が虹の色「赤・橙(だいだい)・黄・緑・青・藍(あい)・紫」と、ほぼ順序よく対応しているとの調査結果を新潟大学のチームがまとめ、英科学誌電子版に発表した。
つまり「ドは赤」「ミは黄」「ソは青」「シは紫」といった具合。
メカニズムは不明だが「なぜ音楽に心を動かされるのかという未解明の問題にヒントを与えてくれるかもしれない。
共感覚とは「音に色を感じる」、「味に形を感じる」といった二つ以上の感覚が結びつく知覚現象のことで、音楽家ではシベリウスやリストが知られている。」
というわけで、低音域の豊かな音は「赤系の音」、中音域では「緑系の音」、高音域の音は「紫系の音」といった具合だが、それでもまだ正確に言い表せない気がする。
味覚細胞や嗅覚細胞には対象となる微粒子が直接触れてくるが、聴覚細胞に届くのはせいぜい「空気の波」に過ぎないのだから仕方がないのかもしれませんね。
どなたか、表現方法でいい知恵をお持ちじゃないですかね?(笑)
この内容に共感された方は励ましのクリックを →