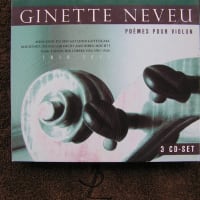前回からの続きです。
☆ 近代指揮者の誕生
19世紀初頭、次々に画期的な交響曲を生み出していたベートーベンの指揮振りが細かく伝えられている。少し長くなるが引用してみよう。
「彼は様々な身振りをして間断なく忙しかった。ディミヌエンド(次第に弱くなる)を表わすために段々低くかがみこみ、ピアニッシモ(きわめて弱い)では机の下にほとんど腹這うばかりになった。
音量が大きくなるとあたかも奈落からせり上がるように立ち上がり、オーケストラが力いっぱい奏するところに入ると爪先で立って巨人もかくやとばかり大きくなり、両腕を振り回して空に舞い上がるかのように見えた。」
いささか滑稽な様子だが、ベートーベンならさもありなんと思えそうな記述である。ここから読み取れるのは、ベートーベンが拍子の指示だけではなく音楽の表現力を楽団員に意識させることを実践していたことだ。
バトン・テクニックは問題ではなくて、意識は全て音楽に向けられ身体全体で表現を試みており、練習中にもテンポはもちろん細かい音のニュアンスにも気を配り一人ひとりの楽員達と話し合っていたそうだ。
明らかに近代指揮者への道をベートーベンは踏み出していた。
19世紀初頭は指揮の歴史の大きな変わり目であり、その方向を決定付けたのはヴェーバー、メンデルゾーン、ベルリオーズ、ヴァーグナーなどだった。彼らは指揮の仕事が作曲家の考えを見極め、音楽を統一体としてとらえ的確にかつ柔軟に表現する、いわば解釈としてのレベルに引き上げた。
なかでも、ベルリオーズとヴァーグナーは「指揮法」に関する著作を有するが、これは自分の作品が時代を超えて完全な表現を求めた結果の産物だった。
☆ 何故、指揮者がそこにいるのか
オーケストラのコンサートで、ひとりの人間が皆より遅れて舞台に登場し中央に立って挨拶もそこそこに聴衆に背を向けて手にした棒を振り回すという図は改めて見直せば奇妙に思えるかもしれない。
しかも、プログラムや広告でオーケストラの前に必ずその人間の名前が特筆大書されるのはどういう理由だろうか。
自ら音を出さない人間がどうしてそれほど重んじられるのか。果たして指揮者は必要なのだろうか。
アプローチのひとつとして指揮者無しの状態を考えてみよう。
小規模楽団の場合→ヴァイオリンの首席奏者の首の動きで奏きはじめる。
大規模編成の楽団の場合→1922年モスクワで人民が主役の政治という発想から指揮者無しのオーケストラがつくられ、コンサートが行われた。
作曲家プロコフィエフはその主要な難点はテンポを変える点にあると見ていたという。音楽の流れを緩急自在に変化させるのは奏者全員の総意にしたがってというわけにはいかず(到底、間に合わない!)、少なくとも演奏の開始は誰かが合図しなければ始まらない。ちなみに、この団体は1932年に解散したという。
しかし、指揮者の存在は全体の始まりやまとめるだけの役割に過ぎないのだろうか。指揮者次第でオーケストラが一変し聴衆を感動の渦に巻き込むのは何故だろうか。
ここで、シャルル・ミュンシュ著の「指揮者という仕事」93頁~95頁にその大事な回答が示されているので要約して引用しよう
「指揮者は楽員達の意欲を刺激し、音楽が自分の中に生じさせるあらゆる感情を楽員達に吹き込むためにその場にいなければならない。指揮者にはそのために使える重要な手段が二つある。身振りと眼差しである。多くの場合、眼差しの表現は手や指揮棒より重要である。」
「身振りについては柔軟さが大切で右手は音楽を”線で描き”左手は”色彩を与える”ようにして、いろんな動きの中に音楽のニュアンスと同じくらい微妙な差異がなければならない」
「こうやって、指揮者からオーケストラへ伝わる火花、電流、霊気、それにリハーサルで入念に準備された演奏がコンサートの晩を素晴らしいものにする。」
以上の記述で指揮者の存在理由が大体説明できそうな気がするがどうだろうか。
☆ オーケストラ楽員は指揮者に何を期待するか
アメリカで実際にアンケートをとった結果があるのでいくつかピックアップして紹介しよう。
・音楽について際立った解釈をして楽員を奮い立たせること。
・ソロ(単独演奏)が力まないでもはっきり聴き取れるようにオケのバランスをとること
・明瞭なビート(拍子の指示)は基本的な役割
・本番中に事故(演奏者が思わず犯すミス)が起きても気づかない振りをすべき。
・トスカニーニの時代は去ったことを悟るべきだ。芸術上の独裁者は良くない。
・指揮者は最小限の「発言」で意思伝達が出来るように。トスカニーニは実に非凡でそれをバトンテクニックの技のうちに秘めていた。
・リハーサルで奏きそこないがあるたびに冒頭に戻る習慣は、楽員たちの反感を買うだけだ。
・奏者と楽器の両方の能力と限界を知っている専門家であるべき。
・教師であり、指導者であり、最高の専門家であり、そして音楽史上の偉大な作曲家達の最も深遠な思想が通り抜けねばならない煙突である。
指揮者トスカニーニが亡くなって(1957年)60年以上経つが、いまだに言及されていることが興味深い。トスカニーニはその強烈な個性もあっていまだに指揮者の象徴的存在なのだろう。
なお、「指揮台の神々」(ルーペルト・シェトレ著)254頁によると、東京のある音楽大学の入学試験で、「尊敬し模範とする指揮者は?」との設問に対して全員がフルトヴェングラーと回答したそうですよ(笑)。
最後に高校時代の同窓生でカメラマンの「T」君が撮影した「棚田の夕陽」(九州)をご覧になっていただこう。
この内容に共感された方は励ましのクリックを →