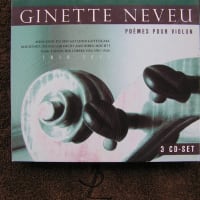毎日、飽きもせず、懲りもせず楽しんでいる音楽とオーディオだが、いい歳をしてどうしてこんなに熱中するんだろうと、遅まきながら考えることがある。
とはいえ、「そもそも熱中するのに理由など要るものか!」という向きもあるでしょうが、まあそう仰らずに~(笑)。
まず、何といっても挙げられるのは「芸術鑑賞としての役割」でしょうか。
「音楽&オーディオ」のいいところは日常生活の中で手軽に一流の「芸術」に親しむことができるところにあると思います。
軽く300年以上もの伝統を持つクラシック音楽を機器のスイッチを入れるだけでいとも簡単に楽しめるんですからこれほどありがたい趣味はないでしょう。
これに関連して「中高年における芸術鑑賞の必要性」について、元文化庁長官で国際的な「ユング心理学」の第一人者「河合隼雄」(かわいはやお)さん(故人)が次のようなことを言われているので紹介しておきましょう。
(出典:2002年12月24日号「エコノミスト」誌の「現代病が中高年を襲う」)
この記事は当時社会問題となっていた中高年の自殺についてその原因と対策を心理学の立場から分析したもので、およそ20年前のテーマだが現在でもいささかも古びていないと思います。
少々舌足らずだが要約して、箇条書きにしてみると・・、
✰ 人生の前半と後半では生きることの意味が変化することに早く気づくべき。つまり、前半は地位、財産が向上するが、後半は死に向かって下降していく
✰ 中年期は価値観の転換とともに「老」「死」に対する準備を始める時期
✰ そのためには、仕事だけでなく幅広く文化的なことや芸術に関心を向ける
✰ 一流の文化や芸術はその底流に「死」を内在させていることに気付くことにより、「死」をいかに受け止めるか自然と考えるようになる。
✰ しかし忙しい現代人にはあまり悠長なこともいっておられないのでとりあえず「こころの出家」を薦める。
✰ 「こころの出家」とは、日々の生活の中で今まで居たところから「出て」外から自分を眺めてみること。
以上の通りだが、そういわれてみると自分の場合は「音楽&オーディオ」を通じて「こころの出家」をしているのかもしれないですね~。
で、この内容について少し立ち入ってみましょう。
「一流の芸術はその底流に死を内在させている」って、意味わかります?
これは以前のブログ「一度は行ってみたかったバイロイト音楽祭」の中でいみじくも紹介した村上春樹さんの次の言葉とも関連してきます。
「優れた芸術とは多くの奥深い疑問を我々に突き付けるテキストのことだ。そしてたいていの場合、そこには解答は用意されていない。解答は我々一人ひとりが自分の力で見つけていくしかない。」
「多くの奥深い疑問」っていったい何だと思われますか?
もちろん、人それぞれに疑問をお持ちなのだろうが、自分がモーツァルトを聴きながらときどき思うのは、
「人間の肉体はたかだか80年前後で朽ち果てていくのに、生み出された作品の方はまるで一人歩きするかのように人の心に感動を与えながら何百年もの命を謳歌している。この永遠の生命力はいったい、どこに由来するんだろうか?」
難問です! 自分の力で解答を見つけていくのは至難の業だと思います(笑)。
そこで「チャットGPT」さんの出番です。そっくり投げかけてみました。
「これはとても興味深い問いですね。人間の肉体は有限でありながら、作品は時を超えて生き続ける。この「永遠の生命力」は、いくつかの要因に由来すると考えられます。
-
普遍的なテーマ
優れた作品は、人間の本質や普遍的な感情(愛、悲しみ、希望、葛藤)を描いているため、時代や文化を超えて共感を生む。たとえば、シェイクスピアの戯曲や古代の神話が現代でも感動を与えるのは、人間の根源的な感情を捉えているからです。 -
記録技術と伝承
作品が残るのは、それを保存し、伝える技術があるから。文字、印刷、デジタル技術によって、作り手の想いが時間の壁を越えて受け継がれていく。 -
人の心に刻まれる影響力
単に物理的に残るだけでなく、人々の心に深く刻まれ、そこから新たな創作の源となる。たとえば、文学や音楽が他の芸術に影響を与え、新しい形で生まれ変わることがあります。これは作品が「一人歩き」するように見える理由のひとつかもしれません。 -
受け手が作品を生かし続ける
作品は、それを受け取る人がいてこそ存在し続ける。読む人、観る人、聴く人が作品に意味を与え、新たな解釈を加えながら、それを未来へとつなげていく。つまり、作品の生命力は、人々の心の中にこそあるのかもしれません。
結局のところ、「永遠の生命力」とは、作品そのものの中にあるのではなく、それを受け取る私たちの中に生まれ続けるものなのかもしれませんね。
という内容でした。ご参考になりましたでしょうか?(笑)。