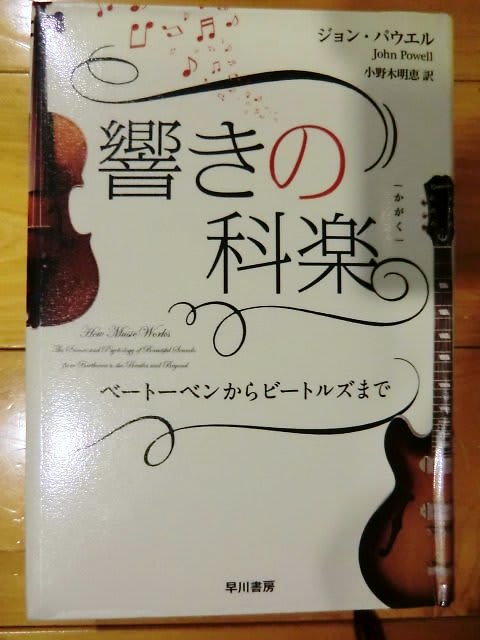今年(2017)から「月曜日」に限って、過去記事の中で今でもアクセスが絶えないものをピックアップしてお届けしているが、いわば「プレミアム セレクション」とし、カテゴリーは「復刻シリ~ズ」に分類している。
今回は5年半ほど前に投稿したタイトル「音楽こぼれ話」である。それでは以下のとおり。
たまには肩の凝らない話ということで音楽家についてのエピソードや笑い話をいくつか紹介。
いずれも実話で、たわいない話のかげにも芸術家のちょっとした人間性が伺われるところが面白い。
「休止符のおしゃべり」(渡辺 護著、音楽の友社刊)

☆ ドイツの大ピアニストであるウィルヘルム・バックハウスが中米のある町で演奏したときのこと、客席に一人の女性が幼児を連れて座っていたが、その子が笑ったり、ガタガタ音を立てたりしてうるさくてしようがない。
バックハウスはマネジャーを通じてその夫人に立ち去るよう要請した。彼女は立ち去り際に、憤慨した様子で聞こえよがしにこう言った。
「ふん、一人前のピアニストとはいえないね。私の妹なんかは、この子がそばでどんなに騒いでいても、ちゃんとピアノが弾けるんだよ!」
☆ 名指揮者カール・ベームは友人とチレア作曲のオペラ「アドリアーナ・ルクヴルール」を見に行った。しかし、ベームはどうしてもこのオペラにあまり感心できない。
見ると客席の二列前にひとりの老人が気持ち良さそうに眠っていた。ベームは連れの友人に言った。
「あれを見たまえ、このオペラに対する最も妥当な鑑賞法はあれだね!」
「しっ!」友人は驚いて、ベームにささやいた。「あの老人はほかならぬ作曲者のチレアなんだよ!」
☆ 1956年6月、ウィーン国立歌劇場で「トリスタンとイゾルデ」がカラヤン指揮で上演された。
その総練習のとき、イゾルデ役を演じるビルギット・ニルソンのつけていた真珠の首飾りの糸が切れて、真珠が舞台上にばらまかれてしまった。
みんながそれを拾いはじめたが、カラヤンもまた手助けして数個を拾いあげた。
「これは素晴らしい真珠ですね。きっとスカラ座出演の報酬でお求めになったのでしょう」と、当時ウィーン国立歌劇場総監督の地位にあったカラヤンが皮肉を言った。
ニルソンも負けてはいない。「いいえ、これはイミテーションです。ウィーン国立歌劇場の報酬で買ったものです。」
☆ 「あいつがぼくよりギャラが高いのは、いったいどういう訳なんだ!」音楽家の間でのこういう”やっかみ”はよく聞かれること。
作曲家ピエトロ・マスカーニはあるとき、ミラノのスカラ座から客演指揮を依頼された。
「喜んでやりましょう」、彼は答える、「ただその報酬の額についてだが、トスカニーニより1リラだけ高い額を支払ってくださることを条件とします。」
スカラ座のマネジメントはこれを承知した。マスカーニの指揮が成功のうちに終わったあとスカラ座の総監督は彼にうやうやしく金一封を捧げた。
マスカ-ニがそれを開けてみると、ただ1リラの金額の小切手が入っているばかり。「これは何だね?」、総監督は”ずるそう”に笑って答えた。
「マエストロ(トスカニーニ)がスカラ座で振って下さるときは、決して報酬をお受け取りにならないのです。」
☆ 新米の指揮者がオーケストラから尊敬を得るようにするにはたいへんな努力が要る。ある若い指揮者は自分の音感の鋭さで楽団員を驚かせてやろうと一計を案じた。
第三トロンボーンのパート譜のある音符の前に、ひそかにシャープ(♯)を書き入れておいた。
そして、総練習のとき強烈なフォルティッシモの全合奏のあと、彼は演奏を止めさせ、楽団員に向かって丁寧に言った。
「中断して申し訳ないが・・・、第三トロンボーン、あなたはDから八小節目で嬰ハ音を吹きましたね。これはもちろんハ音でなければならないのです。」
そのトロンボーン奏者はこう返した。
「私は嬰ハ音を吹きませんでしたよ。どこかの馬鹿野郎がハの音符の前にシャープを書き入れたんですが、私はそうは吹きませんでした。だってこの曲を私は暗譜しているんですから」