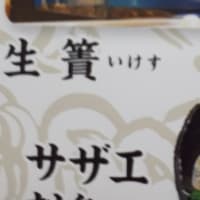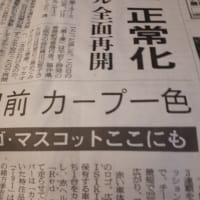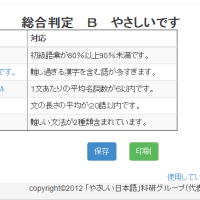要旨
現代を生きる私たち日本人にとって、ひらがな・カタカナ・漢字・句読点は日常に溢れているものであって、特に注意を払うことはない。しかし、これらがどの程度の頻度・割合でそれぞれ使用されているのかを考えることは、構造的に小説の詳細に迫ることにつながる。そこで私は小説におけるそれらの一般性や個別性を調査する。
明治期と大正期の短編小説を選んで比較したのだが、相違点よりも共通点の方が多かった。両作品の共通点としては「の」や「タ行のひらがな」が多用されており、漢字よりもひらがなの占める割合が大きかった。また相違点としては「刺青」では漢字の占める割合が40%であるのに対して、「蜜柑」では漢字は約30%だった。明治から大正にかけて漢字が少なくなった傾向が見られるが、基本的には、多用されるひらがなの種類、ひらがなと漢字の占める割合、句読点の出現頻度等に大きな差は見られなかった。
現代を生きる私たち日本人にとって、ひらがな・カタカナ・漢字・句読点は日常に溢れているものであって、特に注意を払うことはない。しかし、これらがどの程度の頻度・割合でそれぞれ使用されているのかを考えることは、構造的に小説の詳細に迫ることにつながる。そこで私は小説におけるそれらの一般性や個別性を調査する。
明治期と大正期の短編小説を選んで比較したのだが、相違点よりも共通点の方が多かった。両作品の共通点としては「の」や「タ行のひらがな」が多用されており、漢字よりもひらがなの占める割合が大きかった。また相違点としては「刺青」では漢字の占める割合が40%であるのに対して、「蜜柑」では漢字は約30%だった。明治から大正にかけて漢字が少なくなった傾向が見られるが、基本的には、多用されるひらがなの種類、ひらがなと漢字の占める割合、句読点の出現頻度等に大きな差は見られなかった。