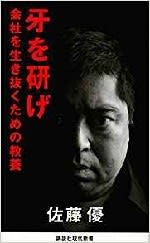(1)三一論の議論は難しいが、こういったことがわかっていると、国際ニュースの背景がよくわかるようになる。
2016年2月に、キューバでローマ教皇フランシスコとロシア正教会キリル1世が会った。1054年に東西教会が分裂して以降初めての東西和解だ、と見出しをつけた新聞もあったが、これは間違いだ。こういう記事を書いた記者は、キリスト教史の基本的な知識を欠いている。
1964年に、当時のローマ教皇がコンスタンティノポリスの総主教(世界総主教)と会談して、東西教会は和解している。
(2)正教は、カトリック教会のようなかたちでのヒエラルキーにはなっていない。
カトリック教会は銀行と同じつくりで、ローマ教皇は代表権を持っている代表取締役兼会長だ。
対するに正教は、商店会だ。文房具や、用品店、ラーメン屋のそれぞれが商店会に加盟しているが、商店会会長に指揮・命令権はない。商店会の会長のような役割をコンスタンティノポリスの総主教が世界総主教の名でおこなっている。だから、商店会の文房具屋が会長だからといって、ラーメン屋に何を売れとか売るなとか指示できないのと同じで、各教会についての権限はない。
そういったことがわかってないので、ロシア正教会の言い分だけを聞いて歴史的和解などと言って話を大きくしているのだ。
(3)今回の対話に隠されているテーマは、じつはウクライナだ。「イスラム国」の問題は二次的だ。
1517年、ルターの宗教改革がはじまると、その影響がチェコ、ハンガリー、ポーランドにも強く及んだ。このことに危機感を覚えたカトリック教会は、トリエントで公会議をおこなって、カトリック教会の構成を変えるとともに、腐敗を一掃して教皇直属の軍隊をつくった。この軍隊がイエズス会だ。このイエズス会がプロテスタント討伐をめざして、ヨーロッパで戦争をはじめた。
問題は、イエズス会が強過ぎたことで、チェコやハンガリー、ポーランドを席巻するのみならず、ベラルーシやウクライナまで入って行ってしまった。ベラルーシやウクライナは、ロシア正教の世界だ。ロシア正教の人たちは改宗を嫌がった。
ロシア正教会は、神父が①キャリア組と②ノンキャリア組(在俗司祭)に分かれる。②は結婚できるが、①は結婚できない。カトリック教会は全員結婚できないが、プロテスタント教会は全員結婚できる。
正教会の場合は、②のトップと①のビリがちょうど同じ階級になるようになっている。霞が関のキャリアシステムに似ている。
ほかにも、イコン(聖画像)を拝むかどうか、神父の服といったことを見ても、ロシア正教会とカトリックでは違う。
そこでローマ教会は、二つだけ譲歩するように頼んだ。
(a)ローマ教皇が一番偉いということ(教皇首位権)。
(b)フィリオクェ。【注1】
正教会は、「父、子、聖霊」のうち聖霊は父から発出する、という立場だ。他方、カトリック教会は、父と子から聖霊が発出する。このカトリック教会の「子からも」(フィリオクェ)という立場を認めればいい、ということでつくられたのがユニエイト教会だ。直訳すると統一教会だが、日本語では何か独特な印象があるので、東方典礼カトリック教会、東方帰一教会などと言われている。
ユニエイト教会がなぜ政治的な意味を持ってしまうかというと、この教会は西ウクライナで強く、ウクライナ民族主義の母体になっているからだ。1945年、ソ連の赤軍がウクライナを占領した2年後の1947年に、ユニエイト教会は「自発的に」ロシア正教会に合同した。むろん、秘密警察が入ってきて、脅し上げてだ。この教会とナチス・ドイツに協力したウクライナ独立運動の人たちが、1950年代の真ん中ぐらいまでは、西ウクライナの山にこもって反ソ武装闘争をやっていた。だから、スターリンはこの教会を嫌った。
その後、この地下教会、ユニエイト教会に所属して、バチカンとつながっていることがわかった場合には、軽くて7年ぐらい、ひどいと25年くらいのシベリア流刑に遭った。実際に、殉教者も出ている。
(4)そうした経緯があったので、ウクライナ独立のときは、このユニエイト教会の権利を認めろ、ということが、大きな要素になった。原罪の反ロシアのナショナリズム、それにドネツクやルガンスクなどでの対立の原因になった、西ウクライナ派の台頭の核になるのがこの教会だ。だから、この教会は、見た目は正教会、しかし実質はカトリックだ。
この教会を活動させるな、というのがロシア正教会の要請だ、プーチンの考え方だ。
それに対してカトリック教会は、ウクライナだけでなくてロシアのなかでもユニエイト教会の活動を認めろ、という立場だ。
(5)2016年に、この両者がキューバで会ったのは、どういう意味を持つのか。
キューバは無神論国家だ。もちろん伝統的にカトリック教会が強いが、政治的な影響力は限定的だ。正教は関係ない、しかしロシアとの関係は強い。
暴力団の抗争が起きたとき、どちらかの支配下では手打ちをやらない。それと同じで、キューバは場所を貸して手打ちを手伝ったのだ。ウクライナについてはもうお互いに静かにしましょう、その代わりイスラム過激派という共通の敵があるから、それに向けて団結しようではありませんか、と、こういう枠組みをつくった。まさに政治そのものの会談だったのだ。【注2】
【注1】「【佐藤優】父、子、聖霊/三一論 ~『牙を研げ』~」
【注2】「【佐藤優】テロリズムに対する統一戦線構築 ~カトリックとロシア正教~」
□佐藤優『牙を研げ 会社を生き抜くための教養』(講談社現代新書、2017)の第2章の「⑭ロシア正教とカトリックの和解に隠されたテーマ」
↓クリック、プリーズ。↓



【参考】
「【佐藤優】キリスト教の特徴、三一論(父・子・聖霊の関係) ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】キリスト教共同体とローマ法 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】復活という現象の科学的説明 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】プレモダンとしてのカトリックと正教 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】ユダヤ教、キリスト教、イスラムの「罪」 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】論理が発達する理由 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】天照大神vs.須佐之男命 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】仏教や神道とは違う、一神教の思考法 ~『牙を研げ』」
「【佐藤優】国教は習慣というかたちをとる ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】紅白歌合戦の、カオスからコスモスへ ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】武士政権成立前後のグローバリゼーションと反グローバリゼーション ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】プロテスタンティズムという思考の鋳型 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】日本兵は捕虜になるとよくしゃべる理由、米軍の日本研究 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】ソ連軍の懲罰部隊が強かった理由、日本軍の「生きて虜囚の辱めを受けず」 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】『牙を研げ 会社を生き抜くための教養』 ~各章の小見出し~」
「【佐藤優】『牙を研げ』 ~まえがき~」
「【佐藤優】『牙を研げ 会社を生き抜くための教養』 ~目次~」
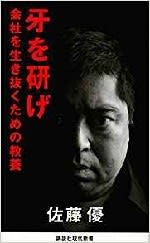
2016年2月に、キューバでローマ教皇フランシスコとロシア正教会キリル1世が会った。1054年に東西教会が分裂して以降初めての東西和解だ、と見出しをつけた新聞もあったが、これは間違いだ。こういう記事を書いた記者は、キリスト教史の基本的な知識を欠いている。
1964年に、当時のローマ教皇がコンスタンティノポリスの総主教(世界総主教)と会談して、東西教会は和解している。
(2)正教は、カトリック教会のようなかたちでのヒエラルキーにはなっていない。
カトリック教会は銀行と同じつくりで、ローマ教皇は代表権を持っている代表取締役兼会長だ。
対するに正教は、商店会だ。文房具や、用品店、ラーメン屋のそれぞれが商店会に加盟しているが、商店会会長に指揮・命令権はない。商店会の会長のような役割をコンスタンティノポリスの総主教が世界総主教の名でおこなっている。だから、商店会の文房具屋が会長だからといって、ラーメン屋に何を売れとか売るなとか指示できないのと同じで、各教会についての権限はない。
そういったことがわかってないので、ロシア正教会の言い分だけを聞いて歴史的和解などと言って話を大きくしているのだ。
(3)今回の対話に隠されているテーマは、じつはウクライナだ。「イスラム国」の問題は二次的だ。
1517年、ルターの宗教改革がはじまると、その影響がチェコ、ハンガリー、ポーランドにも強く及んだ。このことに危機感を覚えたカトリック教会は、トリエントで公会議をおこなって、カトリック教会の構成を変えるとともに、腐敗を一掃して教皇直属の軍隊をつくった。この軍隊がイエズス会だ。このイエズス会がプロテスタント討伐をめざして、ヨーロッパで戦争をはじめた。
問題は、イエズス会が強過ぎたことで、チェコやハンガリー、ポーランドを席巻するのみならず、ベラルーシやウクライナまで入って行ってしまった。ベラルーシやウクライナは、ロシア正教の世界だ。ロシア正教の人たちは改宗を嫌がった。
ロシア正教会は、神父が①キャリア組と②ノンキャリア組(在俗司祭)に分かれる。②は結婚できるが、①は結婚できない。カトリック教会は全員結婚できないが、プロテスタント教会は全員結婚できる。
正教会の場合は、②のトップと①のビリがちょうど同じ階級になるようになっている。霞が関のキャリアシステムに似ている。
ほかにも、イコン(聖画像)を拝むかどうか、神父の服といったことを見ても、ロシア正教会とカトリックでは違う。
そこでローマ教会は、二つだけ譲歩するように頼んだ。
(a)ローマ教皇が一番偉いということ(教皇首位権)。
(b)フィリオクェ。【注1】
正教会は、「父、子、聖霊」のうち聖霊は父から発出する、という立場だ。他方、カトリック教会は、父と子から聖霊が発出する。このカトリック教会の「子からも」(フィリオクェ)という立場を認めればいい、ということでつくられたのがユニエイト教会だ。直訳すると統一教会だが、日本語では何か独特な印象があるので、東方典礼カトリック教会、東方帰一教会などと言われている。
ユニエイト教会がなぜ政治的な意味を持ってしまうかというと、この教会は西ウクライナで強く、ウクライナ民族主義の母体になっているからだ。1945年、ソ連の赤軍がウクライナを占領した2年後の1947年に、ユニエイト教会は「自発的に」ロシア正教会に合同した。むろん、秘密警察が入ってきて、脅し上げてだ。この教会とナチス・ドイツに協力したウクライナ独立運動の人たちが、1950年代の真ん中ぐらいまでは、西ウクライナの山にこもって反ソ武装闘争をやっていた。だから、スターリンはこの教会を嫌った。
その後、この地下教会、ユニエイト教会に所属して、バチカンとつながっていることがわかった場合には、軽くて7年ぐらい、ひどいと25年くらいのシベリア流刑に遭った。実際に、殉教者も出ている。
(4)そうした経緯があったので、ウクライナ独立のときは、このユニエイト教会の権利を認めろ、ということが、大きな要素になった。原罪の反ロシアのナショナリズム、それにドネツクやルガンスクなどでの対立の原因になった、西ウクライナ派の台頭の核になるのがこの教会だ。だから、この教会は、見た目は正教会、しかし実質はカトリックだ。
この教会を活動させるな、というのがロシア正教会の要請だ、プーチンの考え方だ。
それに対してカトリック教会は、ウクライナだけでなくてロシアのなかでもユニエイト教会の活動を認めろ、という立場だ。
(5)2016年に、この両者がキューバで会ったのは、どういう意味を持つのか。
キューバは無神論国家だ。もちろん伝統的にカトリック教会が強いが、政治的な影響力は限定的だ。正教は関係ない、しかしロシアとの関係は強い。
暴力団の抗争が起きたとき、どちらかの支配下では手打ちをやらない。それと同じで、キューバは場所を貸して手打ちを手伝ったのだ。ウクライナについてはもうお互いに静かにしましょう、その代わりイスラム過激派という共通の敵があるから、それに向けて団結しようではありませんか、と、こういう枠組みをつくった。まさに政治そのものの会談だったのだ。【注2】
【注1】「【佐藤優】父、子、聖霊/三一論 ~『牙を研げ』~」
【注2】「【佐藤優】テロリズムに対する統一戦線構築 ~カトリックとロシア正教~」
□佐藤優『牙を研げ 会社を生き抜くための教養』(講談社現代新書、2017)の第2章の「⑭ロシア正教とカトリックの和解に隠されたテーマ」
↓クリック、プリーズ。↓
【参考】
「【佐藤優】キリスト教の特徴、三一論(父・子・聖霊の関係) ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】キリスト教共同体とローマ法 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】復活という現象の科学的説明 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】プレモダンとしてのカトリックと正教 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】ユダヤ教、キリスト教、イスラムの「罪」 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】論理が発達する理由 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】天照大神vs.須佐之男命 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】仏教や神道とは違う、一神教の思考法 ~『牙を研げ』」
「【佐藤優】国教は習慣というかたちをとる ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】紅白歌合戦の、カオスからコスモスへ ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】武士政権成立前後のグローバリゼーションと反グローバリゼーション ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】プロテスタンティズムという思考の鋳型 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】日本兵は捕虜になるとよくしゃべる理由、米軍の日本研究 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】ソ連軍の懲罰部隊が強かった理由、日本軍の「生きて虜囚の辱めを受けず」 ~『牙を研げ』~」
「【佐藤優】『牙を研げ 会社を生き抜くための教養』 ~各章の小見出し~」
「【佐藤優】『牙を研げ』 ~まえがき~」
「【佐藤優】『牙を研げ 会社を生き抜くための教養』 ~目次~」