 常にタイトルに凝りまくる片岡が「吉永小百合の映画」と名のっているのだから当然吉永小百合の本ではない。
常にタイトルに凝りまくる片岡が「吉永小百合の映画」と名のっているのだから当然吉永小百合の本ではない。
彼女がデビューしてから「キューポラのある街」にいたるわずか数年間(59年3月から62年4月まで)の時代を、「影の外に出る」と同様、観客にすべてさらされているカード(日活のプログラムピクチャー)を通して活写。おみごと。なにしろ、冷静で、しかも映画界のアウトサイダーだから言うことに遠慮がないのがいいです。
その鋭い指摘を、いくつか紹介しましょう。
戦後の日本は五年きざみで質的な激変を重ねた、という説を僕は持っている。質的な激変とは、それまでの日本とはまったく別の日本となり、日本人はまるで別人になってしまう、というほどの意味だ。1945年の敗戦から数えて、四度目の激変の入口をくぐり抜けたのが、1960年の日本だった。(略)この突進的な大変化のなかで、変化に適応しない映画との距離が開けば開くほど、映画は人々にとっての魅力を失った。距離が決定的に開き始めた最初の年が、1960年だったと理解すると正しい。
1960年8月「疾風小僧」
結婚に直結してすべてのエピソードが重なっていくから、恋愛のエネルギー・コストといった余計な波瀾はいっさいないほうがいいという、抽象化の力が物語全体に働いている。
その力から抜け出すためには、男とは女とは、あなたという人は、きみという女は、といった単純化に決別して、恋愛のコストを支払い続ける具体的な複雑さのなかに、恋愛の当事者のひとりとして身を置くにかぎる。結婚しても経済はもちろん、生活ぜんたいが安定する保障はもはやない。むしろ不安定要素が相乗的に増していくだけだ。生活の質も、結婚と同時に目に見えて低下する、という現実がすでに広くある。
1960年12月「美しき抵抗」
セーラー服とはなになのか、という問いを解く鍵はここにある。勤労に勤労を重ねる、ひたすらな労働の日々を目前にしつつも、まだ世の中に放り出されてはおらず、それゆえに学校の勉強を中心に友だちと夢を語り合うことなどの可能な、したがってその意味では輝ける青春の日々とも言える、庶民が前もって体験する唯一の晴れ姿なのではないか。
1961年1月「大出世物語」
真面目で平凡な高校生という道をはずれると、非行グループやちんぴらたちの世界が待ち受けているという前提で進んでいく物語は、まぎれもなく1960年代初めの頃のものだ。若者文化というような分厚い緩衝地帯は、当時の日本にはまだなかった。真面目で平凡でも、あるいは常に危なっかしくても、荒々しい現実から至近距離のところに、少年たちはいた。現実という巨大なおろし金で体を削られる可能性を、誰もが危ういところですり抜けていた。
1961年8月「太陽は狂ってる」
吉永小百合が日活と契約してからの出演作品は、この「上を向いて歩こう」で二十五本目となる。日活が彼女のために用意した、あるいは彼女をはめこんだ、役どころや役柄、さらにはキャラクテールといった言葉も使えるかと思うが、そういったことぜんたいの限界が、この作品にもっともはっきりと出ているのを、僕という観客は見なくてはいけない。吉永小百合がその能力を発揮できるような役が、ストーリーのなかにごく不充分なかたちでしか作られていないにもかかわらず、そのストーリーぜんたいが体現する信条のようなものを、台詞だけで念押しする役割を彼女は担わされてきた。このことが持って当然の限界を、二十五本目にしてまだ観客に見せてしまう日活は、二十五本も使っていったいなにをしてきたのか。
1962年3月「上を向いて歩こう」
……そして翌月、二十六本目の作品として「キューポラのある街」(監督浦山桐郎)が封切られる。“吉永小百合の時代”に、日本は突入するのだ。そして以降、時代を象徴しすぎていたために『使えない』女優となっていた彼女を、しかし一変させたのは「細雪」(東宝)だったと思う。












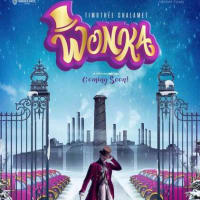













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます