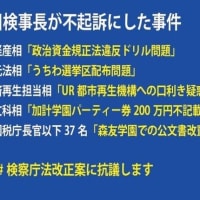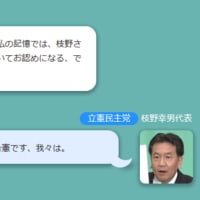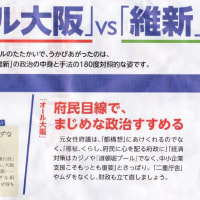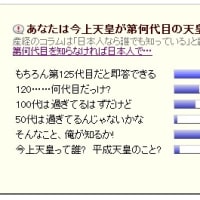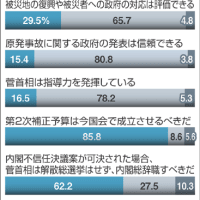前回の記事で述べたように、
という嶋田繁太郎の供述は、たしか東條も東郷も同趣旨のことを述べていたと記憶しているし、これに反する証言を聞かないので、おそらく事実なのだろう。
そして政府は交渉継続を断念し、11月5日の「帝国国策要領」どおりに12月初旬の開戦を最終決定した。
だが、政府外には、それでもなお開戦すべきではないと考えた人々は存在した。
その一人が、戦後首相を務めた吉田茂である。
吉田は外交官出身で外務次官や駐英大使を務めたが、自由主義者として排撃され当時は無官だった。
以前にも取り上げた吉田の「思出す侭(まま)」というエッセイ(中公文庫の吉田著『日本を決定した百年』に所収)で、吉田は「ハル・ノート」について次のように述懐している。
さらに、12月1日に米国のグルー駐日大使から会見を求められ、会うと、
吉田は斡旋に動いたが、東郷は言葉を濁して会う気配はなかったという。
吉田は佐藤に言われたとおり、牧野伸顕伯爵(元内大臣、吉田の妻の父)にも見せたところ、
牧野は大久保利通の次男である。また東郷外相は鹿児島県出身である。
吉田は東郷や当時の政府、重臣を次のように批判している。
注意すべきは、吉田も牧野も「ハル・ノート」を受諾すべきだったと言っているのではない。交渉を断念してこちら側から開戦すべきではないと言っているのだ。
「ハル・ノート」の内容が苛烈だった、最後通牒に等しかったからといっても、それはわが国から開戦すべき理由にはならない。最後通牒とは戦争を仕掛ける側が戦争回避のための最終条件として出すものであって、通牒を受け取った側が、従わなければ開戦すべきという性質のものではない。
「ハル・ノート」が日米開戦を決定したと見る論者には、その視点が抜け落ちている。
なお、吉田は、東郷が終戦に尽力したことにも触れ、その労を讃えている。
付記
これら吉田の見解については、吉田の回顧録『回想十年』の1巻(新潮社、1957、のち中公文庫、1998)にも同趣旨の記述があることにあとで気付いた。
上で引用した「思出す侭」は1955年の7月から9月にかけて『時事新報』夕刊に連載されたものなので、こちらの方が早い。『回想十年』のこの箇所については「思出す侭」を元にしているものと思われる。
ハル・ノートの受諾を主張した者は、政府内にも統制部内部にも一人もいなかった。その受諾は不可能であり、その通告はわが国の存立をおびやかす一種の最後通牒であると解せられた。この通牒を受諾することは、祖国、日本の滅亡に等しいというのが全般的意見だった
という嶋田繁太郎の供述は、たしか東條も東郷も同趣旨のことを述べていたと記憶しているし、これに反する証言を聞かないので、おそらく事実なのだろう。
そして政府は交渉継続を断念し、11月5日の「帝国国策要領」どおりに12月初旬の開戦を最終決定した。
だが、政府外には、それでもなお開戦すべきではないと考えた人々は存在した。
その一人が、戦後首相を務めた吉田茂である。
吉田は外交官出身で外務次官や駐英大使を務めたが、自由主義者として排撃され当時は無官だった。
以前にも取り上げた吉田の「思出す侭(まま)」というエッセイ(中公文庫の吉田著『日本を決定した百年』に所収)で、吉田は「ハル・ノート」について次のように述懐している。
国務長官ハルの名前で日本に送られた十一月二十六日付のこの通牒は、最も激しい調子で日本を非難したもの、到底受諾し難い条件を強要したものとして当時伝えられ、事実上の最後通牒であるとして取り扱われたことは、多くの人々の記憶するところであろう。だが私はこの機会において、ぜひ国民諸君の注意を呼び起こしたいことがある。これはこの「ハル・ノート」の本当の意味が果して最後通牒であったかどうかという点に関する私の疑問についてである。
確か十一月二十七日であったかと思うが、東郷外相の代理として現参議院議員の佐藤尚武氏が平河町の私の家を訪ねて来た。佐藤氏は当時外務省顧問という役目だったと記憶する。佐藤氏は一通の英文の文書を示し、これはアメリカから来たものだが、重大なものだと思われるので、お前から牧野に見せてくれという意味の外相の口上を伝えた。それがいわゆる「ハル・ノート」であった。内容は日本の主張部分と、それに対するアメリカの主張部分とを詳しく書き(このアメリカ側の主張だけが当時公表された)特に左の上の方にテンタティヴ(試案)と明記し、また「ペイシス・オブ・ネゴシエーション(交渉の基礎)であり、ディフィニティヴ(決定的)なものではない」と記されていた。実際の腹の中はともかく外交文書の上では決して最後通牒ではなかったはずである。(p.186-187)
さらに、12月1日に米国のグルー駐日大使から会見を求められ、会うと、
「あのノートを君は何と心得るか」というので、私は「あれはテンタティヴであると聞き及んでいる」と返答したら、大使は卓を叩いて語調も荒く「まさにその通りだ。日本政府はあれを最後通牒なりと解釈し、日米間外交の決裂の如く吹聴しているが、大きな間違いである。日本側の言分もあるだろうが、ハル長官は日米交渉の基礎をなす一試案であることを強調しているのだ。この意味を充分理解して欲しい。ついては東郷外相に会いたい。吉田君から斡旋してもらえないか」という。(p.187-188)
吉田は斡旋に動いたが、東郷は言葉を濁して会う気配はなかったという。
会ったらどうなっていたか。今から思えば結果は同じだっただろう。当時既に奇襲開戦の方針が決定していて艦隊は早くも行動を起こしていたらしい。外相としては会うのが辛かったのであろうが、外交官としては最後まで交渉をするのが定跡だと信ずる私としては誠に痛恨に堪えなかった。(p.188)
吉田は佐藤に言われたとおり、牧野伸顕伯爵(元内大臣、吉田の妻の父)にも見せたところ、
手にとって読んでゆく牧野の顔は次第に険しく「随分ひどいことが書いてあるな」といいながら黙っている。そこで私は「外務大臣があなたに見せる以上は何か意見を聴きたいという意味でしょう」というと、暫く考えて「明治維新の大業は鹿児島の先輩西郷や大久保の苦心によって成就した。この際先輩たちの偉業を想起し慎重に考慮すべきであると伝えよ」という。戦争すべきでない、先輩の大きな夢を崩すことになるという意味である。私はこの牧野の言葉をそのまま佐藤氏に伝えたところ、氏は目に涙して「必ず外相に伝達します。私は戦争になればいまの地位(外務省顧問)をやめるつもりです」といっていた。私はこの写しを当時やはり浪人していた幣原喜重郎氏にも見せた。私はさらに東郷外相を訪ね執拗にノートの趣旨を説明し注意を喚起した。東郷は「お説の通り、なお米国側と折衝するつもりでいる」ということであったので、私は少々乱暴だと思ったが「君はこのことが聞き入れられなかったら外務大臣を辞めろ。君が辞めれば閣議が停滞するばかりか軍部も多少反省するだろう。それで死んだって男子の本懐ではないか」とまでいったものである。(p.188-189)
牧野は大久保利通の次男である。また東郷外相は鹿児島県出身である。
吉田は東郷や当時の政府、重臣を次のように批判している。
東郷外相もさることながら問題は当時の重臣といわれている人達にもあったと思う。内心は戦争反対の者が多かったにかかわらず、十一月二十九日の重臣会議で陛下の御下問に率直な意見をいう者が一人としていなかったようである。
無論軍部の強圧に押されたのでもあろうが、また或いは勝てるかも知れないとする淡い希望などが交錯していたのでもあろうか。それにしても最後の土壇場まで外国使臣と会談すべき立場にある外務大臣が、開戦までなお日を残していたにかかわらず、グルー大使との会見を拒否したことは、外務大臣たるもののとるべき態度にあらず、まことに痛恨事であったといわねばならぬ。(p.191)
当時わが政府は日米関係の救うべからざるを観念してか、ハル・ノートを接受したのを機会に、その訳文に多少手を加え、国民の感情を刺激するようなニュアンスをもったものにして、枢密院に回付したようである。ノートの原文は日米両政府の主張を対照列配し、さらに特に冒頭に、これは最後通牒にあらず、両国政府交渉の基礎たらしめんとする試案であるとの意味を附け加えてあった。勿論これは開戦の場合公表されても差支えないように意を用いて書かれたものだから、米国政府の主張を明記し、米国側に有利に書き上げた嫌いはあるが、わが政府が直ちに開戦を決意せず、交渉に応ずる考えがあれば、無論その余地はあったのである。(p.288)
第一次世界大戦において、英国外相グレー氏は独仏両大使との交渉会談や〔原文ママ〕開戦の間際まで続けたという事実がある。斯かる事実は外務当局者の常に念頭におくべきことであると思う。(p.289)
注意すべきは、吉田も牧野も「ハル・ノート」を受諾すべきだったと言っているのではない。交渉を断念してこちら側から開戦すべきではないと言っているのだ。
「ハル・ノート」の内容が苛烈だった、最後通牒に等しかったからといっても、それはわが国から開戦すべき理由にはならない。最後通牒とは戦争を仕掛ける側が戦争回避のための最終条件として出すものであって、通牒を受け取った側が、従わなければ開戦すべきという性質のものではない。
「ハル・ノート」が日米開戦を決定したと見る論者には、その視点が抜け落ちている。
なお、吉田は、東郷が終戦に尽力したことにも触れ、その労を讃えている。
牧野伯の意見には、東郷外相も当時強く印象づけられたものと思われるが、後に終戦内閣の外相として同じ東郷氏が鈴木首相を助け、事態を収拾して終戦に導き、そのため非常な努力を払われたそうである。これは東郷外相が開戦に対する責任観念より終戦の外相として時局収拾に死力を尽されたのであると信ずる。(p.289)
東郷氏は寡黙、無表情、無愛想な人である。最終閣議にのぞんだ時の外相の風貌今にして思いやらるるものがある。終戦促進によって戦禍の拡大を防ぎ得たるは今日においては明かであるが、終戦にまでこぎつけるためには、鈴木総理の決断が土台になったことは勿論で、その上東郷外相及び米内海相が総理を補佐してここに至らしめた功績は決して没すべきではない。(p.290)
付記
これら吉田の見解については、吉田の回顧録『回想十年』の1巻(新潮社、1957、のち中公文庫、1998)にも同趣旨の記述があることにあとで気付いた。
上で引用した「思出す侭」は1955年の7月から9月にかけて『時事新報』夕刊に連載されたものなので、こちらの方が早い。『回想十年』のこの箇所については「思出す侭」を元にしているものと思われる。