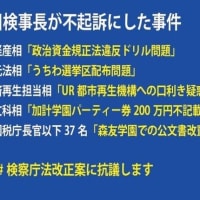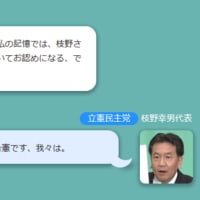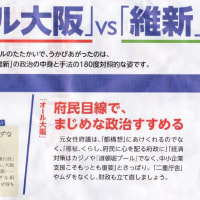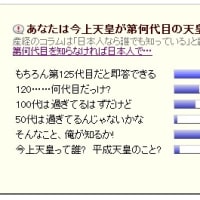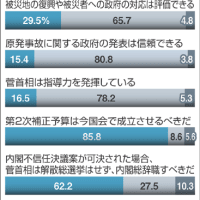先月の記事「ハル・ノートは開戦を決定づけたか」に関連して。
以前述べたように、「ハル・ノート」はわが国の開戦決意を後押しはしたが、決定的要因ではなかった。
にもかかわらず、こんにちにおいても、「ハル・ノート」によってわが国は開戦に踏み切らざるを得なかったと唱えられることが多い。
その原因の一つは、わが国の当事者によってそのような主張がなされていたためだろう。
しかし、それは客観的に見て妥当な評価と言えるだろうか。
前野徹『戦後 歴史の真実』(扶桑社文庫、2002)を読み返していると、次のような記述があった。
第二次近衛内閣とあるのは第三次の誤りか。
ハル・ノートの受諾を主張した者が政府にも軍部にもいなかったという点については、東條も東郷も同趣旨のことを述べていたと記憶している。おそらくそうなのだろう。
だが、この嶋田の主張には、2つの重要な事実が伏せられている。
1つは、以前の記事で述べたとおり、昭和16年11月5日に御前会議で決定された帝国国策要領においては、
とされており、ハル・ノートが来ようが来るまいが、対米交渉が12月1日午前零時までに成功しなければ12月初旬に開戦することは決定済みであったこと。
そしてもう1つは、わが国における主戦派の存在である。
嶋田は、「ハル・ノートを突きつけられるまで、政府、統帥部中、誰一人として、米英と戦争を欲したものはいなかった」と、ハル・ノートこそが開戦の元凶であり、それまではわが国の政府と統帥部中には積極的に開戦を望む者などいなかったかのように表現している。
しかし、わが国にも開戦を望む勢力は存在した。
そんなことは、当時の歴史を少し突っ込んで調べればすぐにわかることだ。
戦史家の故・児島襄による古典的な作品『太平洋戦争(上)』(中公新書、1965、のち中公文庫)は、わが国の参謀本部第20班(戦争指導)が記した「機密戦争日誌」を引用して、次のように述べている。
東郷外相の没後に刊行された回顧録『時代の一面』(改造社、1952)にも、ハル・ノートについての次のような一節がある。
軍の多数派は主戦派であり、「ハル・ノート」がますますそれを助長したと東郷が考えていたことがうかがえる。
嶋田は「誰一人として、米英と戦争を欲したものはいなかった」と言うが、そりゃあ、米英と戦争せずに、わが国が従来どおり米国から石油や屑鉄の輸入を受けられるのなら、あるいは蘭印などの資源を確保できるのなら、それにこしたことはなかっただろう。
そういう意味では、誰も戦争を欲しなかったとは言えるだろう。戦争それ自体が目的ではないのだから。
しかし、そうした資源確保が不可能なのであれば、開戦もまたやむを得ないと当時の指導者層が考えたこともまた事実だろう。
そして、注意すべきは、前野が引用している上記の嶋田の主張は、いずれも東京裁判で語られたものだということだろう。
被告が、自分に有利になるように法廷で主張することは、何ら非難されるべきことではない。
しかし、それを客観的事実とみなすべきかどうかは、また別の問題であろう。
(引用文中、パソコンで出せない旧字や記号については適宜修正を施した)
注1 Amazonで検索したが、こんなタイトルの本はなかった。
次の本がヒットした。
冨士信夫『こうして日本は侵略国にされた』(展転社、1997)
以前の記事でも述べたが、前野徹という人(元東急エージェンシー社長)は、実業家としてはどうだか知らないが、文筆家としてはやはりいいかげんな人物のようだ。
注2 扶桑社文庫版の原文には、「体して」の「体」に「てい」とルビが振ってある。
たしかに「体」は「てい」と読むこともあるが(体裁、体たらくなど)、「体(てい)する」などという日本語はない。ここは「たい」とルビを振るべきだろう。
このルビを前野が振ったのか編集者が振ったのかはわからないが、彼らの程度が知れると言えるだろう。
以前述べたように、「ハル・ノート」はわが国の開戦決意を後押しはしたが、決定的要因ではなかった。
にもかかわらず、こんにちにおいても、「ハル・ノート」によってわが国は開戦に踏み切らざるを得なかったと唱えられることが多い。
その原因の一つは、わが国の当事者によってそのような主張がなされていたためだろう。
しかし、それは客観的に見て妥当な評価と言えるだろうか。
前野徹『戦後 歴史の真実』(扶桑社文庫、2002)を読み返していると、次のような記述があった。
東條内閣の海軍大臣で、御前会議の一員としてつぶさに一部始終を見た嶋田繁太郎は、東京裁判の被告として法廷に出廷した折り、当時の御前会議の模様を次のように伝えています。
「十一月二十六日、ハル・ノートを突きつけられるまで、政府、統帥部中、誰一人として、米英と戦争を欲したものはいなかった。日本が四年間にわたって継続し、しかも有利に終結する見込みのない日支事変で、手一杯なことを政府も軍部も知りすぎるほど知っていた。天皇は会議のたびに、交渉の成り行きを心から憂いていた。そして、第二次近衛内閣も東條内閣も平和交渉に努力せよという天皇の聖旨を体して〔引用者注2〕任命され、政府の使命は日米交渉を調整することにかかっていた」(冨士信夫『日本はこうして侵略国にされた』〔引用者注1〕)
しかし、ハル・ノートは、日本の戦争回避の願いを木っ端みじんに打ち砕きます。嶋田被告は、東京裁判の法廷でこう陳述しました。
「それはまさに青天の霹靂であった。アメリカにおいて日本の譲歩がいかなるせよ、私はそれを戦争回避のための真剣な努力と解し、かつアメリカもこれに対し歩み寄りを示し、もって全局が収拾されんことを祈っていた。しかるにこのアメリカの回答は、頑強不屈にして、冷酷的なものであった。それは、われわれの示した交渉への真剣な努力は少しも認めていなかった。ハル・ノートの受諾を主張した者は、政府内にも統制部内部にも一人もいなかった。その受諾は不可能であり、その通告はわが国の存立をおびやかす一種の最後通牒であると解せられた。この通牒を受諾することは、祖国、日本の滅亡に等しいというのが全般的意見だった」
第二次近衛内閣とあるのは第三次の誤りか。
ハル・ノートの受諾を主張した者が政府にも軍部にもいなかったという点については、東條も東郷も同趣旨のことを述べていたと記憶している。おそらくそうなのだろう。
だが、この嶋田の主張には、2つの重要な事実が伏せられている。
1つは、以前の記事で述べたとおり、昭和16年11月5日に御前会議で決定された帝国国策要領においては、
帝国は現下の危局を打開して自存自衛を完了し大東亜の新秩序を建設する為此の際対米英蘭戦争を決意し左記措置を採る
一、武力発動の時機を十二月初旬と定め陸海軍は作戦準備を完整す
〔中略〕
五、対米交渉が十二月一日午前零時迄に成功せば武力発動を中止す
とされており、ハル・ノートが来ようが来るまいが、対米交渉が12月1日午前零時までに成功しなければ12月初旬に開戦することは決定済みであったこと。
そしてもう1つは、わが国における主戦派の存在である。
嶋田は、「ハル・ノートを突きつけられるまで、政府、統帥部中、誰一人として、米英と戦争を欲したものはいなかった」と、ハル・ノートこそが開戦の元凶であり、それまではわが国の政府と統帥部中には積極的に開戦を望む者などいなかったかのように表現している。
しかし、わが国にも開戦を望む勢力は存在した。
そんなことは、当時の歴史を少し突っ込んで調べればすぐにわかることだ。
戦史家の故・児島襄による古典的な作品『太平洋戦争(上)』(中公新書、1965、のち中公文庫)は、わが国の参謀本部第20班(戦争指導)が記した「機密戦争日誌」を引用して、次のように述べている。
▽十一月三日 大風一過昨日の興奮も醒めたり。明治節の佳節に方り、皇国の前途を祝福せんとす。願わくば外交成功せざらんことを祈る。
▽十一月十三日 来栖大使の飛行機遅々たるは可。
「ル」大統領、来栖大使を迎うるの態度に熱意なきが如きは、また可なり。
乙案成立を恐る。
▽十一月十七日 昨は妥結、今日は決裂、一喜一憂しつつ時日は経過す。一国も速やかに十二月一日の来らんことを祷る。
▽十一月二十一日 野村電到着。乙案提示せるところ、「ハル」は援蒋中止に関し、これは援英中止要求と同様なりとて、大いに不満の態たりしが如し。さもあるべし。
これにて交渉はいよいよ決裂すべし。芽出度芽出度。
▽十一月二十三日 対米交渉の峠もここ数日中なり。願わくば決裂に到らんことを祈る。
この「機密戦争日誌」の意見は、必ずしもそのまま陸軍の総意ではない。「日誌」はあくまで参謀本部第二十班のもの。述べられているのは記録係の班員(中・少佐)の意見である。しかし、同時に「日誌」は決して個人の日記ではない。公式記録である。その公式記録で堂々と、上司を批判し、国策に我意を通そうとする気持ちを表明する。ここに、当時の少壮将校の思いあがりと、“実力”のほどがうかがえるが、だからといって開戦を主張したのは、彼らだけだったとはいえない。
東郷外相が就任早々、松宮順元仏印特派大使、重松宣雄文書課長ら四人を辞任させたように、外務省にも主戦派はいたし、他の官庁、財界にもいた。海軍もむろん例外ではない。現に、開戦と決するや、海軍軍人の間には「いまや、海軍が主役を演ずるときがきた」(十二月五日、「香椎」艦長訓示)とする者が少なくなかった。したがって、海軍にも“機密戦争日誌”があったならば、そこにあるいは参謀本部少壮将校と同じような意見をみることができたかもしれない。
さらにまた、「日誌」が開戦を主張するのは、その意思が彼ら少壮将校のだけのものではなく、すでに指摘したように、参謀本部の幹部もまた、同意していたからにほかならない。決して下克上の成果ではない。(中公文庫版、p.34-35)
東郷外相の没後に刊行された回顧録『時代の一面』(改造社、1952)にも、ハル・ノートについての次のような一節がある。
戦争を避ける為めに眼をつむつて鵜呑みにしようとして見たが喉につかえて迚も通らなかつた。自分ががつかりして来たと反対に軍の多数は米の非妥協性を高潮し、それ見たかと云ふ気持で意気益々加はる状況にあつて、之に対抗するのは容易なことではなかつた。(p.249-250)
軍の多数派は主戦派であり、「ハル・ノート」がますますそれを助長したと東郷が考えていたことがうかがえる。
嶋田は「誰一人として、米英と戦争を欲したものはいなかった」と言うが、そりゃあ、米英と戦争せずに、わが国が従来どおり米国から石油や屑鉄の輸入を受けられるのなら、あるいは蘭印などの資源を確保できるのなら、それにこしたことはなかっただろう。
そういう意味では、誰も戦争を欲しなかったとは言えるだろう。戦争それ自体が目的ではないのだから。
しかし、そうした資源確保が不可能なのであれば、開戦もまたやむを得ないと当時の指導者層が考えたこともまた事実だろう。
そして、注意すべきは、前野が引用している上記の嶋田の主張は、いずれも東京裁判で語られたものだということだろう。
被告が、自分に有利になるように法廷で主張することは、何ら非難されるべきことではない。
しかし、それを客観的事実とみなすべきかどうかは、また別の問題であろう。
(引用文中、パソコンで出せない旧字や記号については適宜修正を施した)
注1 Amazonで検索したが、こんなタイトルの本はなかった。
次の本がヒットした。
冨士信夫『こうして日本は侵略国にされた』(展転社、1997)
以前の記事でも述べたが、前野徹という人(元東急エージェンシー社長)は、実業家としてはどうだか知らないが、文筆家としてはやはりいいかげんな人物のようだ。
注2 扶桑社文庫版の原文には、「体して」の「体」に「てい」とルビが振ってある。
たしかに「体」は「てい」と読むこともあるが(体裁、体たらくなど)、「体(てい)する」などという日本語はない。ここは「たい」とルビを振るべきだろう。
このルビを前野が振ったのか編集者が振ったのかはわからないが、彼らの程度が知れると言えるだろう。