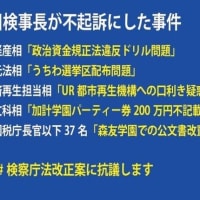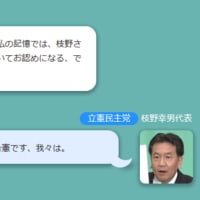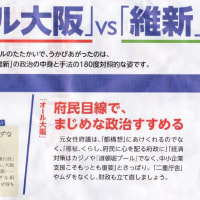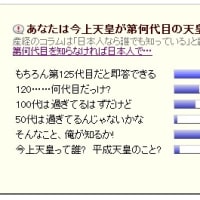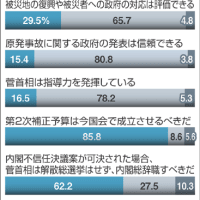(承前)
いわゆる南京大虐殺についての、次の記述は興味深い。
そして著者はこう続ける。
しかし、著者はさらに次のように、南京大虐殺の責任論について反駁している。
著者は、こう反駁しながらも、「南京占領後における日本軍の南京市民に加えた暴行が相当ひどいものであったこと」は認め、軍紀の乱れがあったことも認めている。この点、よく見る「南京大虐殺」批判論とは一線を画している。これは私には意外だった。
なお、著者が「南京虐殺の噂があまり高いので」と記しているように、支那事変における日本軍の暴行が相当ひどいものだったという話は、戦中期にも日本人にはある程度伝わっていたものと思われる。細川護貞の『細川日記』の昭和20年9月3日の項には、
とあるし、矢内原忠雄は1945年10月に行った講演(『日本精神と平和国家』(岩波新書、1946)に収録)で、
と述べている。悪名高いラジオ番組「真相はかうだ」の開始は1945年12月、東京裁判開廷は1946年5月であるから、そうした宣伝や報道より前から、ある程度は知られた話だったのだろう。
また、フランスの検察官がフランス語による陳述に固執したことに絡んで飛び出した、「八紘一宇」についての著者の見解も興味深い。
このフランスの検察官が冒頭陳述でわが国による侵略と述べた仏印進駐について、著者は、現地陸軍の専断によるものと批判している。
また林銑十郎が持ち出されている。
仏印進駐を専断したとされる佐藤賢了(1895-1975)は、前回述べた大島浩や畑俊六と同様、A級戦犯として東京裁判で起訴され、終身禁錮刑の判決を受け、独立後に仮釈放された。近衛内閣時代の帝国議会での国家総動員法審議における「黙れ」事件の主でもある。
当人は「黙れ」の一言でA級戦犯とされたかのように語ることもあったようだが、このように仏印進駐を実行したほか、戦中期には陸軍省軍務局長も務めた重要人物であり、決して「黙れ」だけの人物ではない。
もう一人の安藤利吉(1884-1946)は、1944年に第十方面軍司令官兼台湾総督となり、敗戦後戦犯として中華民国に拘束され、上海監獄に収監中に自殺したという。
(続く)
いわゆる南京大虐殺についての、次の記述は興味深い。
南京虐殺の事実を立証するために検察側が提出した書証、人証は莫大な量に達している。南京事件の主なる証人を列挙すれば、
南京虐殺事件当時南京大学に在職していた米人医師ロバート・ウィルソン氏
南京陥落後国際委員の一員として難民救済に当った紅卍会副会長許伝音博士
南京にあるアメリカ監督派基督教伝道師ジョン・ガスピレー・マギー氏
南京陥落後司法院にいた南京市の警官伍長徳氏
南京市民陳福宝氏
同 尚徳義氏
等である。七月二十九日、証人台に立った徐節俊氏は、昭和十七年五月に行われたビルマ・雲南公路における日本軍の残虐行為について言及した。
私はこれらの証人が語った残虐行為をここに載録するに堪えない。これらの証人の中には危く日本兵の虐殺の手から逃れた人々も交っているから、彼らは南京占領後に繰りひろげられた地獄図をまざまざと描いている。怨恨と復讐の念とに燃え上っているこれら証人の言に虚偽と誇張のあることは、その反対尋問の速記録を見ただけでもわかる。しかし、彼らの言に多少の誇張があるにしても、南京占領後における日本軍の南京市民に加えた暴行が相当ひどいものであったことは、蔽〔おお〕い難き事実である。当時私は北京に住んでいたが、南京虐殺の噂があまり高いので、昭和十三年の春、津浦線を通って南京に旅行した。南京市街の民家がおおむね焼けているので、私は日本軍の爆撃によって焼かれたものと考え、空爆の威力に驚いていたが、よく訊いてみると、そらの民家は、いずれも南京陥落後、日本兵の放火によって焼かれたものであった。南京市民の日本人に対する恐怖の念は、半歳を経た当時においてもなお冷めやらず、南京の婦女子は私がやさしく話しかけても返事もせずに逃げかくれした。私を乗せて走る洋車夫が私に語ったところによると、現在南京市内にいる姑娘〔クーニャン。若い未婚の女〕で日本兵の暴行を受けなかった者はひとりもないという。国民政府の首都南京をおとし入れて講和の機を掴〔つか。原文では手へんに國〕もうというのは、随分馬鹿気た考えであった。首都抜かれて国に何の面目があるか。相手が死物狂いになってトコトンまで抗戦するのは知れたことである。国民軍は首都南京の防禦には死力を竭〔つく〕して戦った。激戦のあった南京の城壁は、私が行ったときまでも、日本兵の血で彩られていた。(下巻 p.95-96)
そして著者はこう続ける。
南京虐殺は、この国民軍の頑強なる抵抗によって沸き立った日本兵の敵愾心にも一因がある。通州事件による中国兵の残虐行為が南京攻囲軍の将兵の間に知れ渡ったことも亦その一因である。しかしその最大の原因は、軍の統率が失われ、軍紀が紊乱したことにある。大元帥陛下をないがしろにした将官たちは、佐官たちにないがしろにせられる。将官たちをないがしろにした佐官たちは、尉官たちにないがしろにせられる。一般行政権を離れて独立した統帥権は、軍を私兵化した。朝鮮越境を敢えてした軍は、軍人の軍であって国民の軍ではなくなってしまっていた。私兵化した軍隊に下剋上の風が行われるのは、必然の成行きである。軍の実権はやがて佐官級に移り、尉官級に移り、果ては下士官級に移って行った。将校の言うことを聴かなくなった下士官級によって統率される兵卒が、暴行、掠奪を行うに至ったのは是非もない次第である。私は南京視察後東京に帰り、私が九大で教授をしていた時の法文学部長であった美濃部達吉先生にお目にかかり、「今日において日本を匡救する途如何」と問うたところ、先生は「林銑十郎大将を処刑しない限りは、日本を匡救する途はない」と言われたが、今にしてその正理なることを痛感する。下剋上の風によって仆れる大廈〔たいか。大きな建物〕は、松井大将の一本の能く支え得るところではない。南京虐殺の責を一身に背負わされて絞首台の露と消えた松井石根大将個人は、むしろ同情に値するものと言えよう。(下巻 p.96-97)
しかし、著者はさらに次のように、南京大虐殺の責任論について反駁している。
今次の戦争において行われた日本軍の残虐事件が、軍首脳部の諒知と同意とに依って行われたものであるという中国検察官の見解は、復讐に血迷った見解である。向哲濬氏も検察官としての立場においてかく論告したのであって、内心その非なることは自覚していたのかも知れない。軍の首脳者が、部下将兵の残虐行為を制圧し得なかった責任は免れ得ないと思うが、彼らが捕虜を虐殺してもよいというような乱暴な命令を出したというのは、人を誣〔し〕うるのはなはだしいものである。彼らがそれほど猛悪な意思をもっていたとしたならば、俘虜収容所などは設けなかったはずである。中国において軍隊ならざる民衆が多く殺戮を被ったのは、軍隊が便衣を着用し、難民に化けて日本軍を攻撃する卑劣なる戦法をとったからである。便衣隊と難民とをゆっくり区別している暇のない日本軍が、難民を射殺したことは自衛上已むを得ない。難民虐殺の責のみが問われて、便衣隊の交戦法規違反が咎められないことは、正理に反している。故に弁護側は、これらの証人の反対尋問にあたって、便衣隊の活動を鋭く衝いている。(下巻 p.97-98)
著者は、こう反駁しながらも、「南京占領後における日本軍の南京市民に加えた暴行が相当ひどいものであったこと」は認め、軍紀の乱れがあったことも認めている。この点、よく見る「南京大虐殺」批判論とは一線を画している。これは私には意外だった。
なお、著者が「南京虐殺の噂があまり高いので」と記しているように、支那事変における日本軍の暴行が相当ひどいものだったという話は、戦中期にも日本人にはある程度伝わっていたものと思われる。細川護貞の『細川日記』の昭和20年9月3日の項には、
米兵暴行事件、ニ、三あり。我兵が支那にて為せる暴行に較ぶれば、真に九牛の一毛なるも、その事実を知らざる者は、米兵のみを怨み、やがては彼等に危害を加ふるに到るべし。
とあるし、矢内原忠雄は1945年10月に行った講演(『日本精神と平和国家』(岩波新書、1946)に収録)で、
殊に日本精神をやかましく唱えた人々自身、日本精神による教育を重んじ、日本精神の権化であると言われた軍隊や学校の中にも、周章狼狽して幹部が非常な私心を発揮した実例を聞いているのであります。支那やフィリッピンに於いて日本の軍隊が暴行を働いたということを、支那の方はまだ公に暴露せられておりませんけれども、フィリッピンの事に就いてアメリカの方から発表があって、国民が苦い思いをさせられた。日本の軍隊が全体としてそういう行動をしたのではないでしょうし、軍全体の方針としてしたのではないでしょう。それを以て全班を推すことは間違だろうと思いたいのでありますが、併し或る部分に於いてはああいう事実があったのでしょう。
と述べている。悪名高いラジオ番組「真相はかうだ」の開始は1945年12月、東京裁判開廷は1946年5月であるから、そうした宣伝や報道より前から、ある程度は知られた話だったのだろう。
また、フランスの検察官がフランス語による陳述に固執したことに絡んで飛び出した、「八紘一宇」についての著者の見解も興味深い。
東京裁判では「八紘一宇」という言葉が日本の世界征服の野望を露呈した言葉として問題になったが、この言葉には慥〔たし〕かにそうした意味もある。この言葉は『日本書紀』に見える神武天皇即位の詔にある〔中略〕語から出た言葉である。東京裁判では、検察側がこの言葉をあまり問題にするので、日本人弁護団では「八紘一宇調査委員会」なるものを作り、鵜沢団長親〔みずか〕ら委員長となり、私も委員の一員となってこれが調査研究に当ったが、「八紘一宇」というような言葉を、神武天皇が使われる道理はない。八紘という言葉は、私がここで博学を衒って、こちたき中国の古典を博引して旁証するまでもなく、中国で出来た言葉である。書紀に見える古の言葉は、日本書紀の編纂者太安麻呂もしくはその下に使われていた中国・朝鮮の帰化人の言葉であって神武天皇の御言葉ではない。太安麻呂の編纂した日本書紀は六朝時代の漢文で書かれていて、江戸時代の漢学者斎藤拙堂の如きは、これを六朝文学の一例と見ている。「八紘一宇」なる言葉は、六朝時代の帝王が盛んに用いた文句であって、そこには五胡によって践〔ふ〕み荒らされた中国を統一して、中国人の中国となさんとする意義があらわれている。書紀に見える神武天皇の詔勅はシナ思想であって、日本思想ではない。そこには江南に追い詰められた六朝の天子のひがんだ思想があらわれている。こんな思想が日本精神だと思ったら大間違いである。故に本居宣長は、書紀に見える神武天皇の詔勅などは頭から問題にしなかった。この詔勅を大きく採り上げたのは、本居歿後の弟子と欺称する天下の大山師平田篤胤である。軍の思想を率いた荒木、小磯の思想の系統を辿ってゆくと、平田篤胤に到達する。日本帝国陸軍というレッキとした名称があるのに、これを「皇軍」と呼んでみたり、馬賊あがりの湯玉麟を討伐するいくさを「熱河聖戦」と仰々しくいったのは、荒木貞夫である。〔中略〕東條首相が尊重していた伊勢の神宮皇学館大学長山田孝雄博士も、亦平田篤胤の亜流で、博士には篤胤に関する著作がある。日本人は忘れっぽいから、もう忘れていると思うが、山田博士が日本全土が大空襲に見舞われる一年ほど前に、「日本は神国であるから、アメリカの飛行機は日本を襲い得ない」と堂々とN・H・Kから放送したことは、記録にとどめておいてよい。日本書紀と古事記との区別もわからない軍人どもは、「八紘一宇」を日本精神と考え、三国同盟締結のときには、この文句を国家の公文書に入れもした。また関東軍では、その発する文書にやたらに「八紘一宇」の印を押していたら、これは織田信長の「天下布武」印の真似である。帝国軍人は、織田信長の私兵のようなものに成り下がっていたのである。日本人がこんな大きな間違いを犯すのも、もとはといえば、国語を尊重しないからである。マゴコロはマゴコロであって、真心でも至誠でもない。況〔いわ〕んや仁でもなければ、義でもないのだ。ビールはビールと言わなければ、ビールの味がせんではないか。ビールを麦酒〔バクシュ〕と呼んで、塗りの椀に注いで飲めば、気が抜けてうまくないようなものだ。フランス語問題で一日を費やしたことは、われわれにとっても無駄ではなかった。(下巻 p.132-134)
このフランスの検察官が冒頭陳述でわが国による侵略と述べた仏印進駐について、著者は、現地陸軍の専断によるものと批判している。
仏印進駐は、日本の侵略意図の明瞭なるあらわれとして、日米交渉を行き詰らせ、アメリカをして戦争決意を固めさす契機となったものであることは、日米交渉の段で詳述せるとおりである。東京裁判にあらわれた仏印進駐の記録の中で、私が特に読者諸君の注意を惹きたいことは、参謀本部がフランス政府と交渉して平和裡に北部仏印進駐を行うつもりであったのが、南支派遣軍司令官安藤利吉中将、同参謀長佐藤賢了少将の専断によって、それが武力進駐となり、三千の我が将兵の命と八百の仏軍の命とを失わしめたことである。ハノイにあってこの報に接した日本委員会首席西原少将は、「統帥乱れて信を中外に失う」と激烈な非難攻撃の電報を参謀本部に送っている。閑院宮殿下はこの責めを負うて参謀総長の職を去られたのである。木戸内大臣も、同年九月二十六日の日記の中で「大局を弁〔わきまえ〕ざる出先の処置は遺憾なり、大事を誤るはこの輩なり。」と慨嘆している。功名心にかられて猪突する職業軍人ほど始末のわるいものはない。またスターリン元帥は、功名心にかられて軍律を犯した将校の肩に肩章を載せ、胸に勲章を宛て「お前の欲しかったものはこれであろう。今こそこれを授ける。」といって、肩章と勲章の上から五寸釘を打ち込ませてこれを刑殺したというが、日本の将校にもこの刑罰に値する者が頗〔すこぶ〕る多かった。私の親しかった陸軍中将は、「戦わずして敵を屈せしめるのは、兵の上たるものであるが、そういうことをやったのでは部下が承知しない。それで已むを得ず我が軍が苦戦に陥るような作戦を採用する。苦戦の末、やっと某要地を占領したということになれば、甲一級の勲章がもらえる。」と語った。職業軍人の勲章の犠牲になって戦死した兵隊こそ浮ばれまい。「一将功成り万骨枯る」のは已むを得ないが、「一将功を成さんとして万骨を枯らす」不義不道は、天人ともに赦〔ゆる〕さざるところてせある。しかし中央の命令に従わず「大事の誤り」「信を天下に失う」ようなことをやらせた者は誰か。それは勅命を用いずして越境した朝鮮軍司令官林銑十郎その人である。(下巻 p.135-136)
また林銑十郎が持ち出されている。
仏印進駐を専断したとされる佐藤賢了(1895-1975)は、前回述べた大島浩や畑俊六と同様、A級戦犯として東京裁判で起訴され、終身禁錮刑の判決を受け、独立後に仮釈放された。近衛内閣時代の帝国議会での国家総動員法審議における「黙れ」事件の主でもある。
当人は「黙れ」の一言でA級戦犯とされたかのように語ることもあったようだが、このように仏印進駐を実行したほか、戦中期には陸軍省軍務局長も務めた重要人物であり、決して「黙れ」だけの人物ではない。
もう一人の安藤利吉(1884-1946)は、1944年に第十方面軍司令官兼台湾総督となり、敗戦後戦犯として中華民国に拘束され、上海監獄に収監中に自殺したという。
(続く)