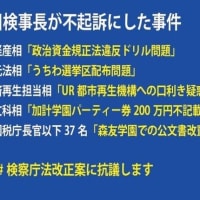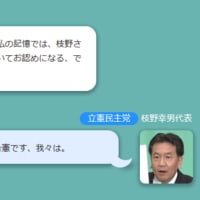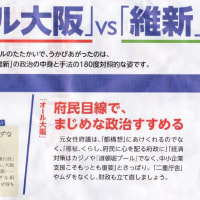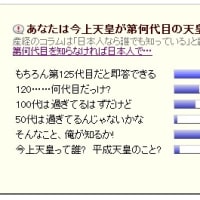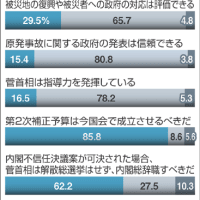(承前)
下巻に入ると、こうした戦前・戦中期の軍部や指導者層を批判する記述はさらに多くなる。
大内兵衛、滝川幸辰の両教授が、検察側に有利な証言を行ったことについて。
一見、わが国の立場を正当化しようとしているように見える。
だが、注意して読むと、ソ連はともかく、中国と米国については、「中国人に、日中抗争の責任が全然なかったとは考えられない」「アメリカの言い分に十分理があるものとは、私には到底考えられぬ」と、「全然」「十分」と留保をつけている。
ということは、逆に言えば、日中抗争の責任の大部分は日本人にあった、アメリカの言い分にも幾分かの理はあったということになる。
「好戦的、侵略的になった日本の軍人もわるいが、何が彼らをそうせしめたのか」というのだから、我々も悪かったが、100%我々だけが悪かったのではないだろうという主張である。
満洲事変当時に奉天の総領事館に勤務していた外交官の森島守人が、関東軍の将校から脅迫を受けたと証言したことについて。
著者は続いて統帥権の問題についてこう述べる。
さらに、後の方ではこんなことも。
そしてついには。
もはや、東京裁判をさばいているのか 自らA級戦犯をさばいているのかわからなくなるほどの激越な批判である。
念のため付記しておくが、ここで名指しされている大島浩(1886-1975)と畑俊六(1879-1962)は、どちらもA級戦犯として東京裁判で起訴された人物である。
ともに終身禁錮刑を宣告され、独立後に仮釈放された。
「大元帥陛下をないがしろにした」越境将軍林銑十郎は、戦時中の1943年に死去している。
(続く)
下巻に入ると、こうした戦前・戦中期の軍部や指導者層を批判する記述はさらに多くなる。
大内兵衛、滝川幸辰の両教授が、検察側に有利な証言を行ったことについて。
満洲事変以来、軍部の執拗なる圧迫と迫害に辛酸を嘗め尽されたこの両氏が、当時は軍の首脳者であった被告に対して不利な証言をされたとて、それを多く非難するには当るまい。青年将校を使嗾〔しそう〕して五・一五事件を起さしめた極右派によって、生命の危険を感ぜしめられ、大学教授の地位から追われて満洲に逃避し、つぶさに憂き艱難を嘗めさせられた私としては、両氏の心情に深く同情できる。当時の軍部の指導者や極右派の思想家、暴力団に対する怨恨の情は、今も私の心から消えてはいない。満洲にいる日本人の民間人を置き去りにして、自分たちだけが特別列車を仕立てたり、軍の飛行機に乗って日本内地に逃げ帰った関東軍の軍人軍属に対しては、今なお憎悪の念に燃えている。しかし、私は満洲事変以来日本が戦った戦争のすべてが侵略戦争であったとは考えられない。「鏖殺〔おうさつ。皆殺しの意〕倭奴」の宣伝ビラを国中に撒きちらし、国民を極端な反日侮日に駆り立て、罪なき居留民の婦女子を辱めた中国人に、日中抗争の責任が全然なかったとは考えられない。不戦条約を蹂躙し、火事泥的に満洲の資材を本国に運び去ったソ連が、日本の侵略を被ったなどとは、私には考え及ばないところである。中立国の義務に違反して敵に軍需物資を送り、日本の玄関先ともいうべきアリューシャン沖で海軍の大演習を行い、揚句のはてはハル・ノートを突附け、真珠湾の奇襲を食って自ら「生き残るための戦争」というアメリカの言い分に十分理があるものとは、私には到底考えられぬ。好戦的、侵略的になった日本の軍人もわるいが、何が彼らをそうせしめたのか。日本人の優越感も唾棄すべきであるが、有色人種に対して賤視感を懐く白人の世界に、独立国民として生きてゆくためには、日本人が明治時代の抑遜した態度をいつまでも持続してゆけない事情もあったと思う。〔中略〕軍教〔軍事教練の略か〕が軍の強制によって行われたことは、厳然たる事実である。また満洲事変以来、数々の戦争が行われたことも事実である。証人として宣誓した以上、真実を語るのは、人間としての義務である。しかし、戦われた戦争が侵略戦争であるか自衛戦争であるかは、各人の意見問題である。大内、滝川の両氏は、これを侵略戦争と見られたかもしれないが、その反対の見解もあり得る。両氏が感情に囚われることなく、その深い観察と広い知見の上からそう判断せられたとあれば、それも致し方がない。しかし、軍閥者流に対する反感から、特にその中の個人に対する私怨から、この結論に到達されたものであれば、私はこれに対して遺憾の意を表せずにはおられない。(p.70-72)
一見、わが国の立場を正当化しようとしているように見える。
だが、注意して読むと、ソ連はともかく、中国と米国については、「中国人に、日中抗争の責任が全然なかったとは考えられない」「アメリカの言い分に十分理があるものとは、私には到底考えられぬ」と、「全然」「十分」と留保をつけている。
ということは、逆に言えば、日中抗争の責任の大部分は日本人にあった、アメリカの言い分にも幾分かの理はあったということになる。
「好戦的、侵略的になった日本の軍人もわるいが、何が彼らをそうせしめたのか」というのだから、我々も悪かったが、100%我々だけが悪かったのではないだろうという主張である。
満洲事変当時に奉天の総領事館に勤務していた外交官の森島守人が、関東軍の将校から脅迫を受けたと証言したことについて。
我々〔森島ら〕はこの事件(柳条溝事件)の調整の努力をするに当つては、平和的手段に訴へるべきである、又自分はこのやうにして満足に解し得ると信ずるといふことを彼に説得しようと試みた。すると板垣大佐は私を叱咤して、総領事の任務は軍の指揮権に干渉するように企図されたかどうか知りたいものだといつた。私は軍の指揮権の干渉に触れる問題は何もない。しかし私はこの事件は、普通の交渉により円満に調整し得るものと確信し、また後者の課程が日本政府の権益の立場より観て望ましいであろうといふことを主張した。話がこの点にきたとき、花谷少佐は怒った様子をして、刀を抜き、軍の指揮権に干渉することを主張するなら、その結果を負ふ覚悟をせよといつた。彼は更に左様に干渉をする者は、誰でも殺してしまふと言つた。花谷少佐のこの感情の爆発は、会話を途絶し、私は詳細に報告を作成するため事務所に帰り、報告を作成した。
板垣被告の面前でこの口供書が朗読されたことは、板垣被告にとっては癪に触ることでもあり、また悲しいことでもあったであろう。しかし森島領事が板垣大佐や花谷少佐の暴力に屈してスゴスゴと総領事館に引上げたそのかみの無念さは、それ以上であったことを忘れてはならぬ。花谷少佐は、満洲国官吏や満鉄社員から蛇蝎の如く忌み嫌われていた関東軍の将校で、溥儀執政が満州国皇帝となられた後も、公の席上で「溥儀が」「溥儀が」と呼び捨てにしていたほどの乱暴者であるから、このとき森島領事に対してどんな暴言を吐いたかは、充分想像され得る。森島氏が東京裁判の法廷でこんなことを言ったからといって、私は森島氏を非難する気にはなれない。(下巻 p.83-84)
著者は続いて統帥権の問題についてこう述べる。
統帥権の問題は、幣原喜重郎男の証言の中でも触れられているが、私は一般行政権と統帥権とが対立したことが敗戦の最大の原因であったと思う。〔中略〕この対立は、国家が平穏無事であるときには表面にあらわれず、何とか胡魔化してゆけるが、日本が戦争に直面するというような場合には胡魔化し切れない。軍縮に伴う失業でウンと痛めつけられた軍人は、政党政治の腐敗につけ込んで必死に一般行政権に反抗し、統帥権の独立をどこまでも主張する。戦争中にはよく「軍・官・民」という言葉が使われたが、同じ日本国民の間に、統帥権に服する軍人、軍属と一般行政権に服する官民とができてくる。大川周明一派の右傾団が暴動を起そうとたくらんだのは、暴動そのものが目的ではなくして、暴動によって戒厳令を布〔し〕くことが目的である。戒厳令が布かれれば、一般行政権の行使は停止せられ、統帥権のみが行使されることになる。犬養首相が奉勅命令を得て満洲で妄動する軍人を押えようとしたのは、一般行政権を統帥権の上に置こうとしたものである。満洲事変の起る頃には、統帥権独立の思想は、軍のすみずみにまで浸み渡っていた。大阪市で起ったゴー・ストップ事件は、一般行政権と統帥権との対立がその末端において発火したものとして注目に値する。たとえ三名でも軍人が隊伍を組んで行進するのは統帥権の発動である。ゴー・ストップの信号で、巡査が交通を整理するのは行政権の作用である。故に軍人はゴー・ストップの信号を無視してもよいというのが、この事件のおこりである。〔中略〕軍が五・一五事件で暴行した青年将校を普通裁判所の裁判に附することを肯ぜず、軍法会議にかけてこれを庇護したことは、軍が一般行政権を打倒したことであって、日本国家の分裂はここに始まったのである。一般行政権を無視することは天皇をないがしろにすることである。天皇をないがしろにすることは、やがて統帥権の根元である大元帥陛下をもないがしろにすることまで発展せざるを得ない。林銑十郎大将が勅許を得ずして朝鮮軍を越境せしめたことは、大元帥陛下をないがしろにしたものであり、畑元帥が大命既に降下せる宇垣内閣に陸軍大臣を送ることを拒んで、これを流産せしめたことは、天皇陛下大元帥陛下をともにないがしろにしたものであって、日本帝国はポツダム宣言の受諾を待たずしてこの時に既に亡んでいるのである。この一般行政権から離れてしまった統帥権が、糸の切れた紙鳶〔たこ〕のようになって満洲で荒れ狂うたのが満洲事変であって、東京裁判でかたきを取られた板垣、花谷両軍人の帝国外交官侮辱事件も、大阪のゴー・ストップ事件に少し毛の生えたものと見てよい。(下巻 p.84-86)
さらに、後の方ではこんなことも。
満洲事変以来、軍閥の勢力が政府のあらゆる部門に浸透し、軍の首脳者が天皇に代わって全国民を支配したというタヴェナー検察官の陳述は、事実である。この点に関しては、タヴェナー検察官の陳述には誇張はない。昭和九年三月、熱河討伐の直後、私は北京に旅行して交民巷の日本大使館を訪れたが、大使館附の衛兵が大使の出入に当って敬礼もしない事実を見て驚いた。統帥権の独立はここまで徹底していたのである。昭和十二年八月、私が満洲国総務庁嘱託兼満鉄嘱託として北京に赴いたときには、武官府、特務部、憲兵隊の勢力は大使館を完全に圧倒し、興亜院ができてからも、軍人と話をしなければ、北京で何ひとつすることができなかった。リッペントロップがこの情勢を呑み込んで大島武官と防共協定の交渉をつづけた事情は、私にはよく諒解できる。総力戦ということを強調しながら、軍人は外交専門家の知識経験を外交に用いることをなさず、実業家にその企業意欲と実行力を伸展せしめることをなさず、何もかも軍人の素人考えでやってのけた。それが失敗に終らない道理はない。軍の威力を背負って天皇の任命した駐独大使をないがしろにし、ついにはその地位を簒奪した大島武官が独外相リッペントロップに奔弄せられ、ゴム人形のように踊らせられた情景は、タヴェナー検察官が法廷に提出したドイツ外交部の機密文書に躍如としているが、この凡庸な軍人が外交のかけ引においてリッペントロップの敵でないことは、わかり切った話である。参謀肩章を吊った若い将校が陸士や陸大で教わったヘッポコ経済学やヘッポコ国際法の知識で、戦時産業や戦時外交が旨くゆくなら、誰も苦労はしない。それくらいのことはわかっていなければならないはずであるのに、軍人があらゆる国家の重要なポストを占めなければ承知ができなかったのは、彼らの増長慢と権勢慾に起因もするが、最も大きい原因は、彼らの眼に軍人以外の日本人が日本人に見えなかったことにある。軍縮によって有能な軍人が多数首にされて以来、軍人は国民を敵として戦ってきた。幣原喜重郎男は、軍人がメチャをやり出した原因は、軍人の国民に対する不満にあると言われたが、私は至言であると思う。軍縮以後の軍人は、統帥権に直属しない日本人を「地方民」と呼び、彼らを自分たちと同じ日本人とは思っていなかったのである。(下巻 p.125-126)
そしてついには。
大島大使は、日独の軍事同盟に条件を附せよという日本政府の訓令に従わず、自らの主張する無条件軍事同盟案にして聴かれずんば辞任する旨、有田外相に電報したのみならず、自分の辞任は内閣の倒壊を意味すると脅迫している。日独軍事同盟の不成立によって駐独大使を辞任した後も、大島は強引に暗躍をつづけ、ついに畑陸相と気脈を通じて三国同盟に反対する米内内閣を倒壊せしめた。国法を紊〔みだ〕るの罪は、彼が最も重い。国民裁判にかければ、彼こそは極刑に値するであろう。米内内閣を倒した畑俊六は、更に陸軍の元老として宇垣内閣に陸相を送ることを拒み、これを流産せしめた。大命が降下しても畑がウンと言わなければ内閣はできなかったのであるから、畑は天皇以上の者である。私は畑俊六を昭和の弓削道鏡と呼ぶことに躊躇を感じない。道鏡の天位覬覦〔きゆ〕は未遂に終わったが、畑元帥の天位蔑視は既遂である。後世の史家は、必ずや道鏡に加えたと同じ筆誅を畑俊六に対して加えることであろう。(下巻 p.128)
もはや、東京裁判をさばいているのか 自らA級戦犯をさばいているのかわからなくなるほどの激越な批判である。
念のため付記しておくが、ここで名指しされている大島浩(1886-1975)と畑俊六(1879-1962)は、どちらもA級戦犯として東京裁判で起訴された人物である。
ともに終身禁錮刑を宣告され、独立後に仮釈放された。
「大元帥陛下をないがしろにした」越境将軍林銑十郎は、戦時中の1943年に死去している。
(続く)