年会のシンポジウムは、「民俗学とは何か」をテーマに、基調報告を島村恭則氏、報告者が3人で野口憲一氏「農業とは何か?-最先端の科学技術(大規模植物プラント・生物学・ハイテク機械)を用いた株式会社による『野菜生産販売事業』は『農』業か」、真鍋昌賢氏「演者とは誰かー動態的な浪曲史記述の可能性ー」、村上紀夫氏「政治史と『民俗』のあいだー六孫王権現社『再興』過程の史料論ー」でした。
島村氏の基調報告を中心に、「民俗学とは何か」考えてみましょう。島村のレジュメによれば、「世界の民俗学を俯瞰したとき、日本において柳田國男が構想した民俗学は、個別資料としての民間伝承そのものの探求をめざす研究ではなく、一種の「社会変動論」といえるものであった」といい、「柳田の社会変動論は、欧米の近代化を普遍的な尺度とする欧米産「近代化論」の単純なあてはめではなく、また社会学における近代化論とも異なり、人びとの生世界、とりわけそこで生み出され、生きられてきた言葉、芸術、情動、信仰、人と自然のかかわり、女性の日常、子どもたちの文化的創造性といった人文的な要素が、社会の構造的変動の中でどのように変化しているのか、あるいは、社会の構造的変動の中で、それらのうち捨て去るべきものは何で、また残すべきものと新たに取り入れるべきものはどのようなものかを問うものであり、また残すべきものと新たに取り入れるべきものとをどのように組み合わせて未来に向かってゆくべきか、を考えるものでもあった。そして、このような一連の考察は、生活当事者自身によって行われるべきものべきものだともされていた」という。そして、このような社会変動論こそが「柳田民俗学のプロトタイプ(典型)であり」、社会変動論としての民俗学を展開するための主たる資料が、人びとの世界で生み出され生きられていた民間伝承群だといいます。
経世済民としての民俗学、内省の学としての民俗学を丁寧に説明したものとして、これはよくわかりますが、「社会変動論」とは何か、初めてききましたから、すぐには理解できません。そこで、参考文献にあげてある、鶴見和子の社会変動論(『鶴見和子曼荼羅Ⅳ 土の巻』常民と世相史ー社会変動論としての『明治大正史世相偏』-)を開いてみました。
「『明治大正史世相偏』で示されているさまざまな具体的事例とその分析には、これまで近代化論の通説の中では見落とされていたこと、あるいはそれと一致しないような主張が、いくつかあらわれている」「社会変動の要因として、これまでは価値観やイデオロギーの変化が重要視されてきた。それらを探る方法として、知識社会学の方法が用いられてきた。これに対して、柳田はむしろ色や音や香りや味に対する常民の感化卯や、表情(目つきなど)やしぐさを通して観察することのできる情動の変化を重く見ている。見えるものと見えないものとの対応関係のパラダイムが、この接近法の底にあるに違いない」などと述べ、色や香り情動の記述の分析にはいっていくのです。これを社会変動などといわず、色の歴史、香りの歴史、情動の変化と継続などといってはいけないでしょうか。自分の実感から資料の、生活の変化に切り込んでいくことは、今もよくやる問題提起です。これは普通に私たちがする研究態度ではないですか。
生きられた日常とか、いまを生きる生活者の記録を記述し、研究するのが「民俗学」なのだ、といった論を展開するかと思いきや、今回の島村氏の報告は学史を整理したような形のものであったわけです。










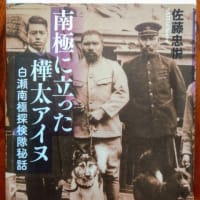

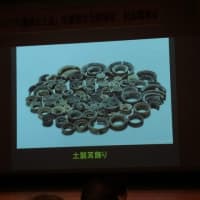


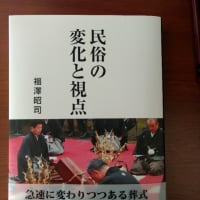




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます