まずは久高島の紹介をしましょう。人口は200人で50パーセント以上が65歳以上の年寄りだといいます。島では40代が若者だそうです。村人のうち20人程が漁業で暮らしていて、船のある物はサンゴ礁の外海にでかけて、カツオやマグロをとって本当の市場にだしているが、船のないものはサンゴ礁の浅瀬で素潜りや追い込みで魚をとっています。浅瀬で捕った魚は、本当の市場へ持って行ってもキロいくらという安い値段で商売にならないので、自分で食べたり島内で消費されています。島内の土地は、「総有地」で、個人の所有地はありません。ガイドの方は、一旦本島に出て生活していたが9年前に島に帰ってきたそうです。そして、島から林野を分けてもらい、そこを切り拓いて家を作ったそうです。島の生まれでない人が島に移住しようと思ったら、空き家をみつけてそこに3年住めば島の住人と認められるのだそうです。畑も家族の人数に応じて、「地割」して分割して栽培しています。年を取って自分で畑が作れない人は、隣の人に耕作権を譲って、隣の人が2軒分を栽培していることもあるそうです。畑はきれいに短冊形に分割され、境界には石が並べてありました。畑の作物といっても自給用で、売るために栽培することはない、というより本島にフェリーで出荷しても採算がとれないということでしょう。それにしても、神の島のこの制度、皆さんはどう思いますか。今はどこの国もない共産制が、小さなこの島、神への祈りを怠らないこの島にはあるのです。そして、誰もそのことを不思議にも思っていません。


イシキ浜の次に案内してもらったのは、島の北の端、カベール岬。人類の始祖、アマミキヨが天孫降臨した場所です。昨日、豊漁を願って神役4名の女性が祈願したという場所です。3か所の岬の突端で神役たちは祈願し、持ってきた重箱で会食したのだそうです。ガイドの方はピクニックだといってました。しか、男は見ることが許されていないのですが、白装束の女性が太平洋から打ちつける波しぶきに向かって祈願する姿を想像すると、鳥肌がたちます。今は神女は4人になってしまいましたが、過去の写真をみると10人も20人もいます。現在の神役は4名で、その内3名は島に住んでいるが4名は本島に住んでいるといいます。本島に住んでいない人も島で生まれた、あるいは島に出自をもつ女性で、嫁に行っても島に神事があると帰ってくるのだそうです。どういう人が神役になるんですか、若い人はいるんですかと、ガイドの方に質問すると、いい質問ですといわれました。神役には先祖代々、セジダカイ(霊力が高い)女性がなるのだといいます。だんだんそうした女性がいなくなったが、3年前島のある行事の時、参加していた28歳の若い女性が震えだし、神が降りたことがわかった。それで、神役たちが相談して神役に引き上げたのだという。この方が一番若いが、本島に住んでいるという。嫁に行っても島を出ても、神事があると島に帰ってこなければならないというのは、大変なことです。他家には嫁がないこと、島からでないことが前提のような制度に思われます。そうして女性が男性のことを祈った。祈られる男性は幸せですね。
次に案内されたのは、島最高の聖地、フボーウタキ。ウタキの中へは島の住人でも男性は入れません。掃除のとき、ウタキの円形広場の草刈りはオバーだけの仕事で、男性は広場(拝所)までの道作りだといいます。このウタキで行われた最大の神事は、イザイホーでした。イザイホーは午年に行われ、今年を含めて3度やられていないといいます。おそらく今後も行われることはない幻の祭りです。イザイホーとは、比嘉康雄『日本人の魂の原郷 沖縄久高島』 (集英社新書)によれば、こうあります。
久高島では、シマで生まれ育ち、一定年齢(丑年の三十歳から寅年の四十一歳)になった主婦は全員神女になることになっており、七十歳までつとめなければならない。この神職者の就任式が十二年ごとの午年、旧暦十一月の満月の日から十八日までの四日間にわたっておこなわれるイザイホーなのである。
イザイホーの語意に定説はない。神歌に見ると、神女の別の呼び方になっている。イザイホーの歴史は古く、五百年ほど前に「ノロ制度」が施行されたときに神職者組織を編成するためにおこなわれるようになったと思われる。ここで神職者に就任した神女は、祖母霊を守護神として家に祀り、この祖母霊を背景に家の祭祀をおこなうことになる。そして、やがてノロの祭祀に参加することになる。



左はフボーウタキへの入り口。ここから先は、真ん中のような立札があり、進入禁止です。右は内部の配置を示した図です。説明をききゆっくり見学できたのは、イシキ浜にいたときガイドの方に電話が入り、午後のフェリーが欠航ではなくなったためでした。島の風景を見たり、イザイホーの写真展を見たりして、そうそう山村留学の話や子どもたちが泊まっている施設をながめたりしてから、シマの食材で作ったお昼を食べ、予定通り1時のフェリーに乗って本島に戻ったのでした。次回はセイファーウタキです。










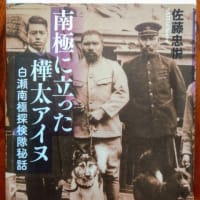

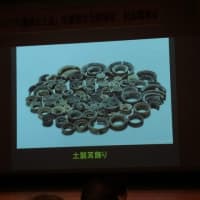


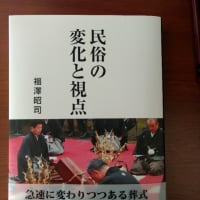




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます