昨年末から今年の夏にかけて、母親をはじめとして、その同世代の人々を送りました。自分が子どもたちに明日にも送られても不思議ではない年齢になっているのですから、一世代上の人々を送るのは当然です。それどころか、残るはおば一人となってしまいました。同世代として一人残されたおばは、どんなにか寂しいと思います。そんな思いでいて、ふと本棚に購入してそのままになっている新書をみつけました。中沢新一著『僕の叔父さん網野善彦』(集英社新書)です。網野さんには一度だけお会いしたことがありました。信濃史学会で講演をしていただき、そのあとの懇親会です。酒が強く談論風発だったような覚えがあります。民俗学のスーパースターが宮田登さんだったとしたら、歴史学のそれは網野さんだと思います。こうした先生方はなかなかいるものではありません。
なかなか哲学的でありながら愛情のこもった中沢新一の追悼文でした。優秀なおじとおいの夢のような時間に、嫉妬を感じるほどでした。そして「あとがき」の部分に。自分の今の感性といたく共感する箇所を見つけました。
私がそっと襖を開けると、人のいないはずの座敷には煌々と白色電球が灯り、そこに父親や網野さんが座って私のほうを見上げているのが、見えてくるようだった。「新、どこへ行っていたんだ」と父親が話しかけてくる。「新ちゃん、今まで勉強かい。入ってきていっしょに話をしよう」と網野さんが微笑みかけてくる。死んでしまったはずの人たちが、また昔のようにそこにいるように感じられ、忘れていたはずの思い出が、つぎからつぎへと驚くほどの鮮明さでよみがえってくるのであった。
本当にそうです。音だとか自分の動作など、何気ないことがきっかけとなって、そういえばあの時こんなふうだったと、亡き人がときどきよみがえってきます。こんな口癖があったと今になって思い出したりします。そして、中沢新一は続けてこんなことも書いています。
墓石や記念碑を建てても、死んでしまった人たちは戻ってこない。それではかえって死んだ人たちを遠くへ追いやってしまうだけだ。リルケの詩が歌っているように、記念の石などは建てないほうがよい。それよりも、生きている者たちが歌ったり、踊ったり、語ったり、書いたりする行為をとおして、試しに彼らをよみがえらせようと努力してみることだ。
墓じまいをしようと決めた自分の心に、真っすぐに響いてくる言葉でした。墓石など、後の代の者に供養を強いるだけのものです。記憶のある者の心に刻まれていれば十分ですし、記憶が薄れれば忘れてくれればいいのです。










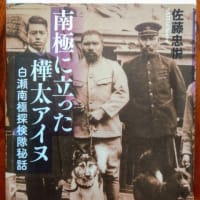

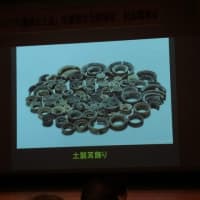


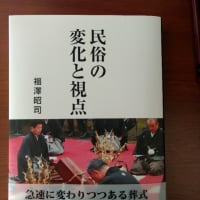




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます